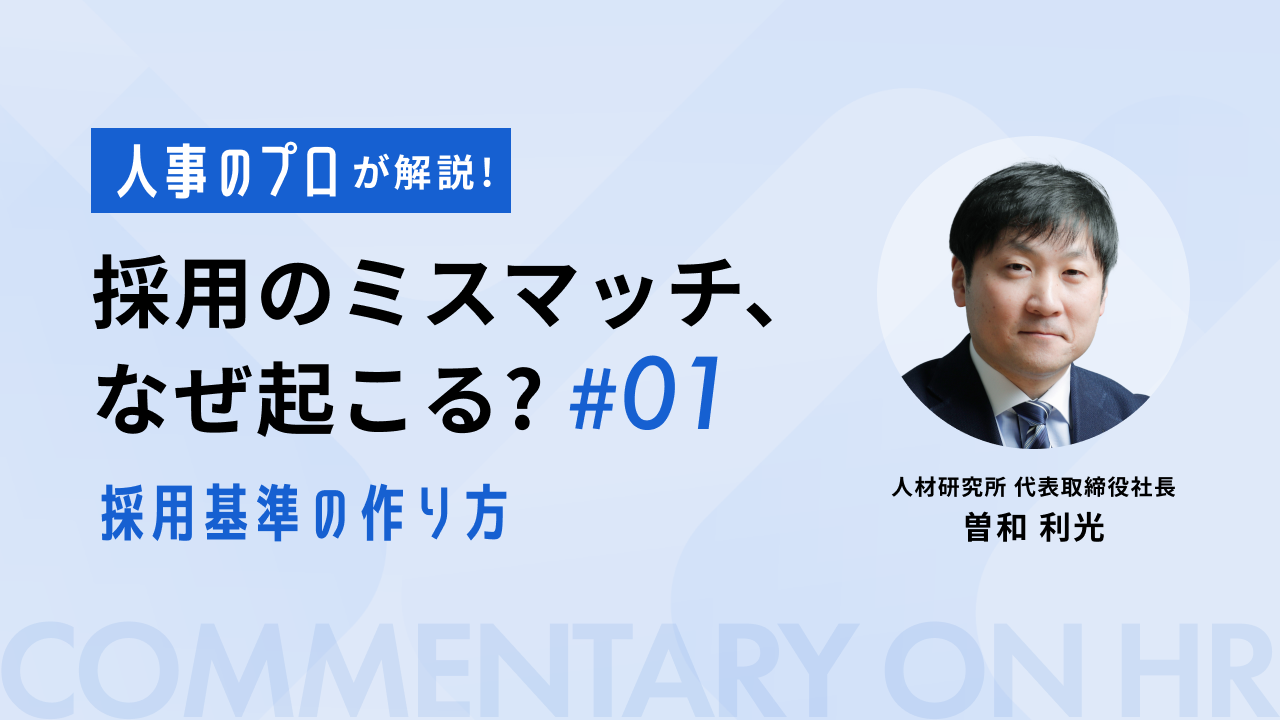せっかく採用したのにすぐ辞めてしまった、厳選採用した人材がなかなか活躍してくれない……など、採用のミスマッチに悩んでいる企業は少なくありません。なぜ、このようなミスマッチが起きてしまうのでしょうか?
人材採用のフローは、大きく次の4つに分けることができます。
| ①採用基準の設計 ②募集内容の検討 ③面接 ④内定者への動機づけ |
実は、いずれの段階においてもミスマッチのリスクをはらんでいます。しかし、ほとんどの企業がその事実に気づいていないのです。ミスマッチが起きる要因は主に4つ。具体的にどんなミスマッチ要因があるのか、それぞれ解説していきましょう。
「採用基準」がそもそもズレていませんか?
採用基準は、性格適性の特性、能力特性、志向・価値観の特性などをもとに設計されますが、この時点ですでに「本当に求めている人材像」とズレが生じている企業が少なくありません。なぜこのようなことになってしまうのでしょうか。一番の問題点は、採用基準の「作り方」にあります。
採用基準を作る際、多くの企業は経営者に求める人材像を聞いたり、社内のハイパフォーマーに好業績を上げている理由を聞いたりして参考にします。しかし、経営者が主観でイメージしている「欲しい人材像」と、実際に現場で活躍している人との間には、多くの場合大きなズレがあります。
そして、ハイパフォーマーが言う「好業績の理由」も、的を射ていない可能性があります。世のスーパープレイヤーは一般的に、「自分がなぜスーパープレイヤーなのか」を言語化する能力が低いと言われています。彼らは何をすれば成果が出るのかなんていちいち考えることなく、頭の中で最良の方法を自動処理して無意識のうちに動いているからです。
これらを測り違えないようにしないと、初めの一歩からズレが生じてしまい、その後のフローを経るごとにギャップがどんどん大きくなってしまいます。
このズレを防ぐには、主観的な意見だけでなく客観的な事実を重視して、採用基準を設計することが大切になります。たとえば社員向けの適性検査など、客観的なデータで多面的に「自社で活躍する人材像」を組み立てていくのがポイントです。
次回、残る3つのミスマッチ要因と、その対策についてご紹介していきます。
【本記事の執筆者】
曽和 利光(そわ・としみつ)
株式会社人材研究所 代表取締役社長
新卒で株式会社リクルートに入社後、ライフネット生命保険株式会社と株式会社オープンハウスを経て、2011年に株式会社人材研究所を設立。「人と、組織の可能性の最大化」をテーマに掲げ、人事、採用にコンサルティング事業などを展開。『人事と採用のセオリー』など、これまで多くの書籍を出版し、いずれも大きな話題を集めている。