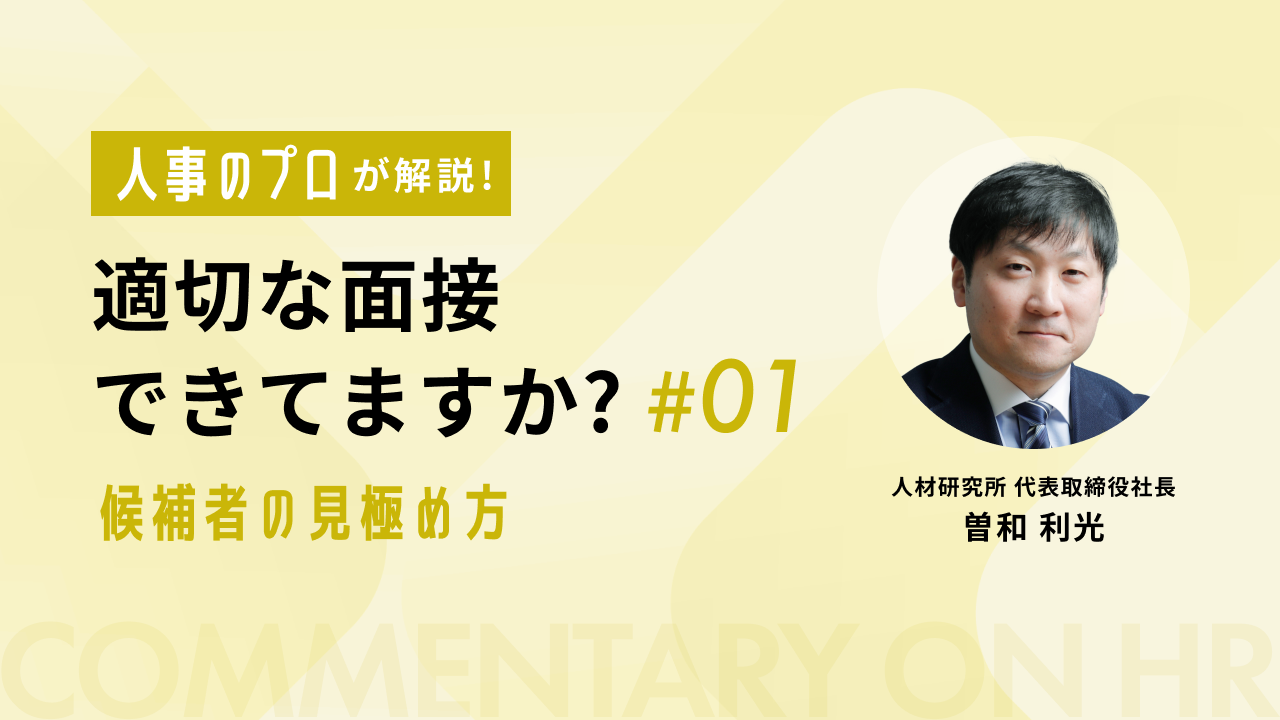採用した人が定着しない、活躍してくれないなどといった人材採用のミスマッチ。たとえ採用基準や募集内容の設計が完ぺきであっても、「面接」の段階で多くのミスマッチが起きているのが現状です。面接の精度を上げ、応募者を適切に見極めるにはどうすればいいのか、詳しく解説していきます。
面接では「思考」ではなく「事実」を確認する
面接ではどうしても、面接担当者の「心理的バイアス」がかかってしまうもの。どれだけ採用基準を正しく理解していたとしても、無意識のうちに自身の偏見や価値観、好き嫌い、得意不得意などで応募者を判断してしまうことがあります。心理的バイアスを完全に消し去るのは難しいですが、対策は考えられます。今回は、その具体的な方法について解説したいと思います。
面接は、大きく分けて次の3つのステップに分けられます。
①インタビュー
②アセスメント
③ジャッジ
インタビューは情報収集。アセスメントは情報から「どんな人なのか」を見立て、認識すること。そしてジャッジは、採用基準と照らし合わせて採用する・しないを評価することです。この3つのプロセスごとに、対策があります。
まずは「①インタビュー」。面接の中では主に、何をやってきたのか、何ができるのかという「事実」と、これから何がしたいのか、仕事やキャリアをどう捉えているのかという「思考」について確認します。
ただ、多くの面接担当者は応募者の「思考」ばかりを確認し、思考でその人物を判断しようとしている…と感じます。例えば、「志望動機は何ですか」「入社したらどんなことがしたいですか」「5年後、10年後にどうなっていたいですか」などといった質問です。これらの質問に対する答えは、すべて応募者個人が「思っていること」であり、事実であるとは言い切れません。
面接の基本は、「事実を聞く」こと。自社で決めた採用基準を満たしているかどうかは、思考ではなく事実から推測するのがセオリーです。そもそも、思考を問う質問には、誰しも「耳障りのいい答え」を言うに決まっています。面接の精度を上げたいのであれば、本当かどうか判断しかねる思考よりも、事実を積み上げるべきです。
もちろん、思考も応募者を知る大切な要素ではあり、排除する必要はありませんが、思考について聞きすぎて事実を確認する時間がなくなることが一番の問題。8:2ぐらいの割合で事実を尋ねる質問に時間を割かないと、採否の判定に必要な情報は得られないと肝に銘じてください。
具体的な情景が浮かぶまで、何度でもしつこく事実を確認する
ただ、事実を確認するのは意外に難しいものです。
日本人のコミュニケーションは、極めてハイコンテクト。「皆まで言わない」「一を聞いて十を知る」「空気を読む」を良しとする文化があり、相手が言ってないことを察する人がデキる人と評価されたりします。そして、面接にはその「デキる人」が駆り出されるケースが少なくありません。
空気を読んで察することは、ビジネスでは評価できますが、面接ではNGです。応募者が言っていないことを勝手に想像して「こういう人ではないか」と判断するのではなく、必要な情報は応募者にすべて言わせる必要があります。
ポイントは、具体的な情景が頭の中に浮かぶまで質問を重ねること。
例えば、「学生時代にカフェでアルバイトをしていました」という答えからは、具体的な情景は思い浮かびません。実際には何らかのカフェがぼんやり頭に浮かんでいるでしょうが、それは面接担当者が勝手に想像しているだけで、正しい情報ではありません。自身の想像ではなく、正しい情報を応募者から聞き出さなければ事実は把握できないのです。
具体的な情景を思い浮かべるためには、「固有名詞」や「数字」で確認し、掘り下げていくことが重要です。「カフェでアルバイト」ではなく、例えば「東京駅の近くにある1日約1000人が来店するスターバックスコーヒーで、週4日アルバイトをしていました。平日は5時間、土日は8時間入り、店長とアルバイト4人で切り盛りしていました」というレベルまで聞き出せれば、「1日1000人ということは、12時間営業として1時間に100人が来店するということ。相当な客数をさばいていたのだろうな」と想像でき、ひっきりなしに来る客に一生懸命対応する応募者の姿がリアルに浮かぶでしょう。
固有名詞や数字が重要である一方で、気を付けるべきは「形容詞」や「比喩的な表現」。いずれもあいまいで具体性がないので、答えの中に出てきたら「具体的には?」と聞き返しましょう。こそあど言葉も要注意です。「これ・それ・あれ・どれ」が何を指しているのかを確認し、これも「具体的には?」「例えば?」「どれぐらい?」で掘り下げましょう。
とにかく何度でも、しつこく事実を確認する。これが、ミスマッチを生まないインタビューの基本であると心得てください。
次回は、面接の3つのステップのうち、「アセスメント」と「ジャッジ」のポイントを紹介します。ステップごとのポイントを把握し、面接の精度を高めていきましょう。
【本記事の執筆者】
曽和 利光(そわ・としみつ)
株式会社人材研究所 代表取締役社長
新卒で株式会社リクルートに入社後、ライフネット生命保険株式会社と株式会社オープンハウスを経て、2011年に株式会社人材研究所を設立。「人と、組織の可能性の最大化」をテーマに掲げ、人事、採用にコンサルティング事業などを展開。『人事と採用のセオリー』など、これまで多くの書籍を出版し、いずれも大きな話題を集めている。