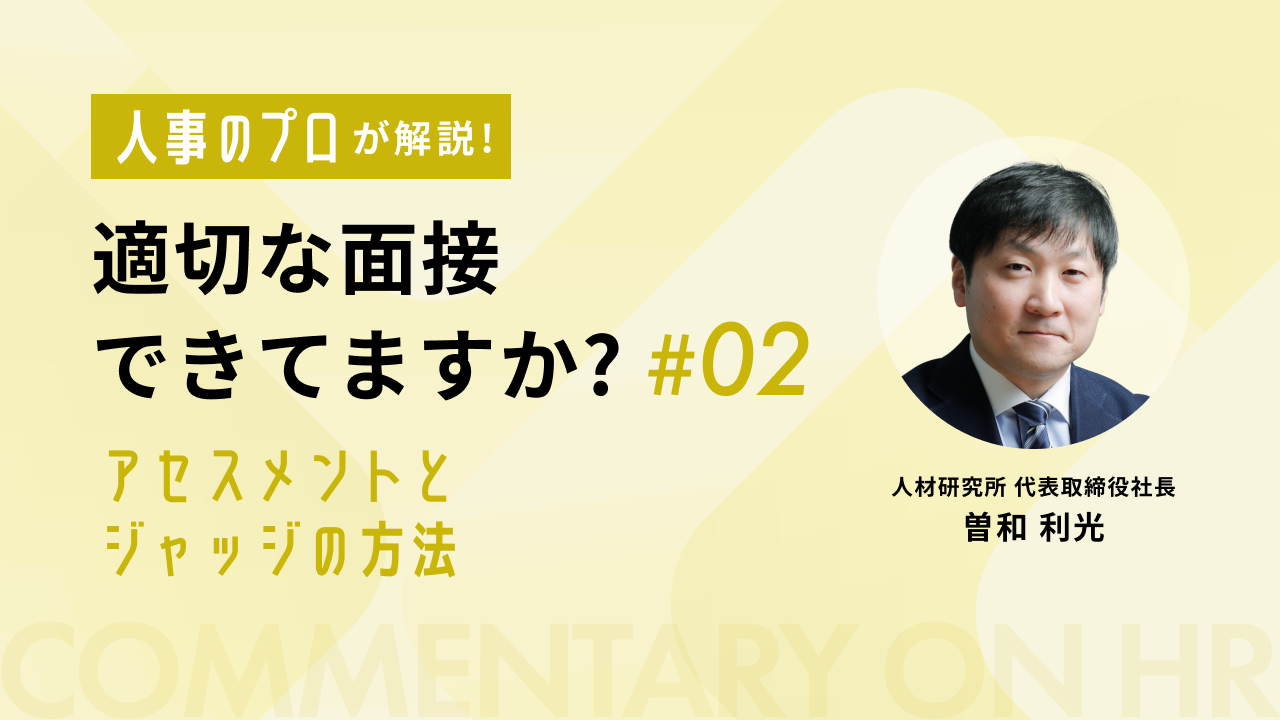採用した人が定着しない、活躍してくれないなどの人材採用のミスマッチ。たとえ採用基準や募集内容の設計が完ぺきであっても、「面接」の段階で多くのミスマッチが起きているのが現状です。
前回は、面接の3つのステップ「インタビュー(情報収集)」「アセスメント(認識)」「ジャッジ(評価)」のうち、インタビューの精度を上げる方法についてご説明しました。今回は、アセスメントとジャッジについて解説します。
アセスメント向上には、心理的バイアスを洗い出す作業が必要
アセスメントとは、インタビューで集めた情報から「どんな人なのか」を見立て、認識することを指します。
アセスメントにおける一番の問題は、言葉のミスマッチ。無意識のうちに自身の偏見や価値観、好き嫌い、得意不得意などといった心理的バイアスがかかってしまうため、同じ情報を見ていても、見立ての際に選ぶ言葉がズレてしまうのです。例えば、ある応募者を「好奇心旺盛」と解釈している人がいる一方で、「飽きっぽい、継続力がない」と判断する人もいます。同じように「慎重」を「臆病」と解釈したり、「チャレンジ精神がある」を「協調性がない」という言葉で表現する人もいます。
アセスメントの精度を上げるには、自身の心理的バイアスを理解することが大前提。理解さえできていれば、それを制御しつつ「情報をフラットに見よう」と努力することができるからです。そのためには、応募者の見立てを皆ですり合わせて、採用に関わる全員が自分の心理的バイアスを認識する必要があります。
例えば、一人の応募者を複数人で見て面接後に評価し、感想をすり合わせる、というトレーニングは有効です。初めは恐らく、予想以上に評価や感想がバラバラで驚くはずです。その「バラバラになったという事実」をもとに、なぜそのように評価したのかを一人ひとりが説明し、皆で議論することで、各々の心理的バイアスが洗い出せるでしょう。
ただ、1回やったぐらいでは心理的バイアスはそう変わりませんし、応募者によって出現する自身の偏見は異なります。毎回の面接ごとに行うことで、皆が自分の癖をつかめるようになり、徐々にアセスメントがフラットなものになるでしょう。
なお、このトレーニングは、できるだけ大人数で行うことが大切です。少人数で行うと、どうしても「面接経験が豊富な人や権力がある人の意見が正しい」という方向に流れがちになるからです。実はそういう人ほど、「優秀な人はこういう人であるべき」という固定観念が強くなる傾向にあり、ミスマッチを助長する原因になるので注意しましょう。
ジャッジの精度を上げるには「採用基準を正しく伝える」に尽きる
ジャッジとは、アセスメントによる「応募者の見立て」と、自社の採用基準とを照らし合わせ、採用すべきかどうか評価することを指します。
ジャッジの精度を上げるには、人事担当者が自社の採用基準をきちんと定義して、面接担当者に正しく伝えること。これに尽きます。なぜこの採用基準ができ上がったのか、家庭や意図も含めて伝えられれば、さらに精度を上げられるでしょう。
「募集内容の検討」の記事で、「〇〇力」などといった抽象度が高いワードは、採用基準を作る段階で意味を確定させておく必要があるとお伝えしましたが、それらを担当者に正しく伝えるのもポイント。例えば、「うちの採用基準における『コミュニケーション力』とは、わかりやすい語彙を選びながら物事を筋道立てて論理的に説明する力のことを指します」などと具体的に伝えることで、ジャッジのミスをなくすことができます。
また、短い時間の中で正しいジャッジを行うために、採用基準を「must条件」と「want条件」に分けておくことも有効です。
ただ、「インタビュー」と「アセスメント」の精度が上がれば、ジャッジでのミスは生まれにくくなるはず。特にアセスメント力が上がり、応募者の見立て・認識が正しく行われていれば、あとは採用基準に則ればジャッジがぶれることはないはずです。
「インタビュー」で事実を積み上げ、自身の偏見を理解したうえでフラットな「アセスメント」を行い、正しい「ジャッジ」につなげる。この流れを理解し、前述の方法で対策していただければ、面接でのミスマッチは格段に減らせるはずです。
【本記事の執筆者】
曽和 利光(そわ・としみつ)
株式会社人材研究所 代表取締役社長
新卒で株式会社リクルートに入社後、ライフネット生命保険株式会社と株式会社オープンハウスを経て、2011年に株式会社人材研究所を設立。「人と、組織の可能性の最大化」をテーマに掲げ、人事、採用にコンサルティング事業などを展開。『人事と採用のセオリー』など、これまで多くの書籍を出版し、いずれも大きな話題を集めている。