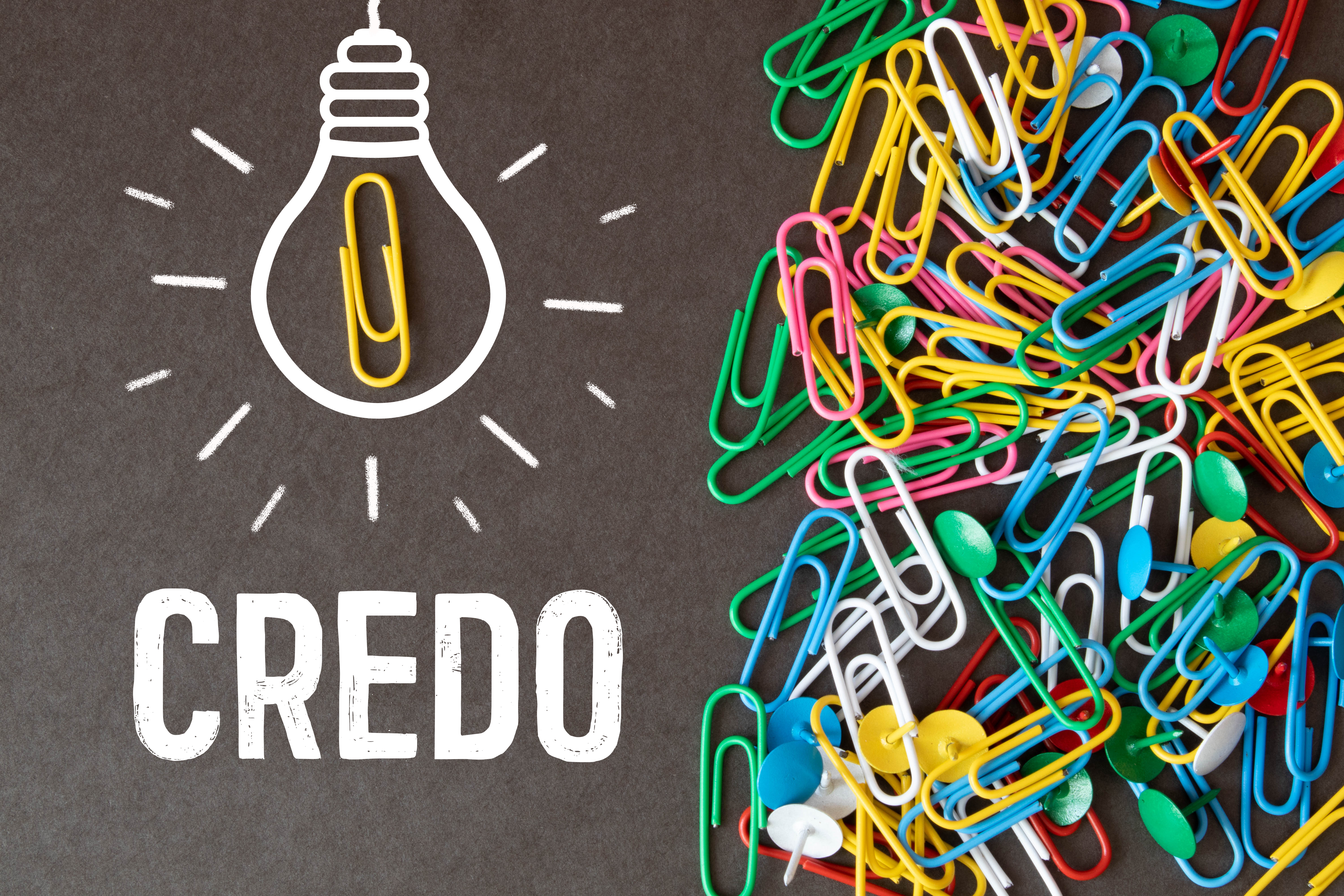「社員がバラバラだと感じる」「会社の方向性が見えにくい」そんな悩みを抱える企業が増えています。特にリモートワークの広がりや価値観の多様化により、組織の一体感を保つことが難しくなってきました。
そこで注目されているのが、企業の信条や価値観を言葉にして共有する「クレド」です。本記事では、クレドの基本的な意味や役割から、作成・浸透のための具体的なステップ、そして形骸化を防ぐための運用ポイントまでを解説します。
「自社らしい組織文化をつくりたい」と考える方にとって、クレドはその第一歩となるかもしれません。導入を検討している方はぜひ参考にしてください。
なぜ今、クレドが必要とされているのか

組織づくりや人材育成の支援を行う株式会社レンズアソシエイツの調査によると、部長・課長クラスの管理職の約65.6%が「会社全体に一体感を感じにくい」と答え、「経営者の考えが見えにくい」と感じる人も46.9%に上りました。
また、株式会社パーソル総合研究所の調査では、自分の会社の理念(ミッションやバリュー)を「十分に理解している」と答えた社員は41.8%にとどまっています。つまり、半分以上の社員が、会社が何を大切にしているのかをきちんと理解できていないという現状があります。
これらのデータから見えてくるのは、「自分たちは何を目指しているのか」が社員に伝わっておらず、組織としてのまとまりや共通の価値観が不足しているという課題です。会社の方向性が見えなければ、不安や迷いが生まれやすくなり、仕事の効率や社員の定着率にも悪影響を及ぼしかねません。
特にコロナ禍をきっかけにテレワークが増えたことで、「会社に属しているという実感が薄れた」と感じる人が増え、組織のつながりをどう保つかがあらためて問われるようになっています。
こうした背景の中、社員の意識をひとつにまとめ、会社の価値観や考え方をわかりやすく示す「クレド」が再び注目を集めています。
クレドは、企業の信条や大切にしていることを言葉にしてまとめたもので、いわば「社内のコンパス」のような存在です。全員が同じ方向を向いて進んでいくための土台として、今こそ必要とされているのです。
参考:
HRプロ「企業の一体感の欠如が浮き彫りに、部長・課長クラスの約6割が『感じにくい』と回答」
パーソル総合研究所「企業理念・行動指針の認知と浸透に関する定量調査」
Gallup “State of the Global Workplace: 2023 Report”
クレドとは何か?その意味と語源

「クレド(Credo)」は、ラテン語で「私は信じる」という意味の言葉です。日本語では「信条」や「信念」と訳され、人や組織の行動を導く考え方や姿勢を指します。
企業の中で使われるクレドは、会社が大切にしている価値観や信念をシンプルな言葉で表したものです。いわば、会社の「心の軸」をわかりやすく伝えるための言葉と言えるでしょう。
クレドの目的:価値観を共有し、行動の軸をつくる
クレドが果たす大きな役割は、「この会社は何を信じて、どんな行動を大事にしているのか」を全社員に伝えることです。
例えば、ジョンソン・エンド・ジョンソン社は1943年に「我が信条(Our Credo)」を制定し、「製品やサービスを使う人々への責任が第一」とする価値観を打ち出しました。このようにクレドは、企業理念やミッションに似た存在ですが、より具体的で日々の行動につなげやすいことが特徴です。
クレドがもたらす効果:組織に一体感と指針を与える
クレドがあることで、社員の判断や行動に共通の基準が生まれ、組織の方向性も明確になります。迷ったときに立ち戻る基準となり、意思決定の軸にもなります。
また、社員一人ひとりが「会社が大切にしていること」を理解できると、自分の仕事の意義や目標を再確認しやすくなり、やる気や一体感が生まれます。部門や世代を越えて共有できる「共通言語」として、組織内のコミュニケーションもスムーズになります。
クレドは単なる言葉ではなく、企業文化の土台として、社員の心と行動をつなぐ「組織の羅針盤」なのです。
参考:
Merriam-Webster “Definition of Credo”
Investopedia “Credo: Definition, Purpose, and Examples”
Rutgers University, CLEO “Vision, Mission, and Credo: What’s the Difference?”
クレド導入のステップ

クレドを導入し、組織に根づかせるにはどうすれば良いのでしょうか。ここでは、作成から社内への浸透までの流れを4つのステップに分けて紹介します。
1. 準備と体制づくり(関係者を巻き込む)
まずは、クレド作成に関わるメンバーを決め、進める体制を整えましょう。経営層の参加は欠かせませんが、トップダウンだけで作ってしまうと、現場には伝わりにくくなってしまいます。
理想は、経営層に加え、現場の社員や各部門の代表も含めた混合チームをつくること。少人数の組織であれば全員参加、大きな会社であれば各部署から代表者を選ぶなど、自社の規模に合わせて工夫すると良いでしょう。
また、立場や社歴の異なる人を加えることで、いろいろな視点から会社らしい価値観を掘り下げやすくなります。参加者には「このクレドが会社全体の約束ごとになる」という意識を持ってもらうことが大切です。
2. 価値観を言葉にする(クレド原案の作成)
体制が整ったら、チームで「うちの会社らしさ」や「大切にしている考え方」を話し合いましょう。「どんな会社でありたいか」「社員が誇りに思う点は?」など、問いをもとに自由に意見を出し合います。
出てきたアイデアは整理して、重複を省き、3〜7個ほどのシンプルな項目にまとめます。それぞれの項目については、「その言葉が意味する行動」まで定義づけると伝わりやすくなります。例えば「チームワーク」なら、「部署の壁を越えて助け合う姿勢」といったように、誰でも解釈できるようにしましょう。
また、言い回しにも工夫を。会社の雰囲気に合った表現を選ぶことで、社員の印象にも残りやすくなります。堅い表現よりも、「カスタマーファースト」「No.1よりOnly 1を目指す」など、社内で使いやすい言葉の方が浸透しやすいケースもあります。
原案ができたら、社内の他の社員や取引先などにも意見をもらいましょう。「うちの会社らしさが出ているか」「共感できる内容か」を客観的にチェックすることで、より多くの人に響くクレドにブラッシュアップできます。
3. クレドを浸透させる(社内展開)
完成したクレドは、しっかり社内に伝えていくことが大切です。まずは、経営トップから社員に向けて、クレドを発表し、その背景や想いを言葉で伝えましょう。
その後は、日々の仕事の中でクレドを繰り返し使うことがポイントです。ポスターや社内報だけでなく、朝礼や会議で取り上げたり、週次ミーティングで項目を1つずつ振り返るなど、身近な場面に取り入れていきましょう。
管理職が部下との面談や目標設定の中でクレドに触れることで、社員が「これは自分にも関係あること」と実感しやすくなります。「この目標は、クレドのどの項目につながると思う?」と問いかけるだけでも効果があります。
中間管理職の役割も重要です。現場の声をすくい上げて経営陣に伝える役割も果たせますし、クレドに関するワークショップなどで社員同士が意見を交わせる場をつくることも浸透の助けとなります。
さらに、クレドを会社の制度と連動させるのも効果的です。例えば、行動評価や表彰制度にクレドを取り入れる、新人研修に組み込む、社内報でクレドを体現した社員の事例を紹介するといった工夫が考えられます。
採用活動でもクレドを活用しましょう。面接時に「この価値観に共感できますか?」と聞いたり、内定者オリエンテーションで会社の文化として紹介することで、クレドへの理解と共感を深めることができます。
4. 定期的な見直しと改善
クレドは一度作って終わりではありません。会社が成長したり、環境が変わったりすれば、見直しが必要になります。
例えば年に1回、経営会議や合宿などでクレドの内容を振り返り、「今もこの内容は合っているか」「言葉が形だけになっていないか」を話し合うと良いでしょう。必要に応じて表現を更新することも大切です。
また、クレドがちゃんと根づいているかをチェックするには、社員アンケートを定期的に行うのも有効です。「クレドを意識して働けているか?」「職場でクレドが活かされていると感じるか?」などの項目で調査し、結果をもとに改善につなげましょう。
状況に応じて研修を行ったり、社内で行動事例を共有したりすることで、クレドを“生きた指針”として維持し続けることができます。
参考:
American Land Title Association “Four Rules to Develop Core Values”
The Management Center “How to Develop and Use Core Values”
管理職が押さえておくべきクレド運用の注意点

クレドは組織の方向性を示す大切な道しるべですが、運用を間違えると、かえって社員の冷めた反応を招いてしまうこともあります。ここでは、管理職として特に意識しておきたいポイントを整理します。
トップダウンだけでは浸透しない
経営層が一方的に作って現場に伝えるだけのクレドでは、社員の心には響きません。多くの企業で見られるように、「上が決めたものを下に伝えるだけ」のやり方では、理念や価値観も形だけのものになってしまいます。
クレドは、現場の声を反映させながら作ることが大切です。社員が参加できるワークショップや意見募集の場を設け、中間管理職がその橋渡し役を担うことで、現場に根づくクレドを育てることができます。
「掲げただけ」で終わらせない
クレドを作っただけで、日常で使われていなければ意味がありません。むしろ、立派な言葉が現実と伴っていなければ、「結局、口だけだ」と社員の信頼を失ってしまいます。
浸透の鍵は、リーダー層自身がクレドを日々の行動で体現することです。意思決定や会話の中で自然とクレドに触れ、「これはクレドの〇〇に沿った行動だ」と具体的に示すことで、社員の理解も深まります。
また、社内SNSでの発信、朝礼での共有、イベントでの活用など、クレドに触れる機会を定期的に設けることも大切です。継続的に目にすることで、社員の中に自然と根付いていきます。
現場とのズレに注意する
どれだけ良い内容でも、現場の実情とかけ離れていれば、クレドは「絵に描いた餅」になってしまいます。社員が共感し、自分ごととして捉えられるよう、内容にはリアリティが必要です。
例えば、現場でずっと課題とされていることをクレドの一部に盛り込むことで、「会社は本気で変わろうとしている」と伝えることができます。こうした姿勢は、社員の納得感や前向きな気持ちにつながります。
さらに、クレドの運用中も社員からのフィードバックを定期的に集めることが大切です。「ちょっと理想論すぎる」「実際とは違う」といった声があれば、それをもとに説明の仕方を工夫したり、具体的な行動例を追加したりと、柔軟に対応していきましょう。
クレドは「つくって終わり」ではなく、「使いながら育てていく」ものです。現場の実感を大切にしながら、経営の思いと社員の現実の橋渡しをする。それが、管理職に求められる役割です。
参考:
パーソル総合研究所「企業理念・行動指針の認知と浸透に関する定量調査」
American Land Title Association “Four Rules to Develop Core Values”
MIT Sloan Management Review “When It Comes to Culture, Does Your Company Walk the Talk?”
まとめ
クレドは、組織が大切にしたい価値観を言葉にして共有する、大事な道しるべです。ただ掲げるだけでは意味がなく、社員一人ひとりの行動につながってこそ、組織に力を与えるものになります。そのためには、現場の声を反映しながら、自社らしい言葉で作り上げ、日常の中で活用していく工夫が欠かせません。もし今、自社の一体感や価値観の共有に課題を感じているなら、クレド導入をひとつのきっかけにしてみてはいかがでしょうか。組織の未来を見据えた取り組みとして、今こそ行動に移すタイミングかもしれません。