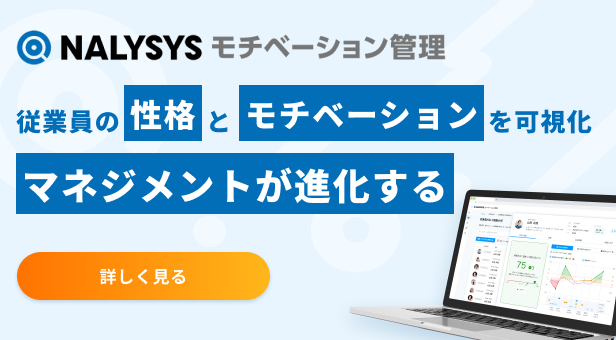このページのまとめ
- 中途社員を採用しても、入社してすぐに離職されてしまうケースがある
- 中途社員は、入社時に「経験者としてのプレッシャー」を感じていることが多い
- 中途・新卒にかかわらず、入社後のサポートを丁寧に行うことが大切
即戦力として採用した中途社員が定着せず、頭を悩ませている企業担当者の方も多いのではないでしょうか。高いスキルを持つ中途社員を採用しても、職場に定着しなければ求めるパフォーマンスを発揮してもらうことはできません。そこで今回は、中途社員の定着を促すための入社後のフォローのポイントについて解説します。中途入社の社員が長く働ける環境をつくるための参考にしてみてください。

この記事の監修者
細谷修平(ほそやしゅうへい)
株式会社人材研究所
横浜国立大学卒業後、人事コンサルティング会社の株式会社人材研究所に入社。IT大手企業の面接代行としてこれまで500人以上の学生を面接。その他にも、不動産系企業を中心に、医療、飲食、マーケティング、物流など業界問わず様々な企業の採用支援に携わる。現在は、人材研究所マネージャーとして部下を育成しながら組織コンサルティングにも従事。
中途社員が入社するメリット
中途社員の入社には、「即戦力としての活躍が期待できる」「教育に時間がかからない」などのメリットがあります。
特に、経験者として入社した社員は業務に必要な知識とスキルをすでに持っているため、入社してすぐに高い成果を上げることもあるでしょう。
未経験者の場合でも、基本的なビジネスマナーが身に付いている分、新入社員よりも短い教育期間で独り立ちできる傾向があります。
中途社員が早期離職する原因
即戦力となる中途社員を採用しても、成果を出す前に早期離職されてしまうケースもあります。
中途社員が早期離職する原因には、次のようなものがあります。
人間関係が上手くいかない
1つ目が、上司や同僚と思うようにコミュニケーションがとれないことです。
「上司が忙しそうにしていて話しかけにくい」「人間関係が出来上がっていて輪の中に入りにくい」などの状況では、心細さを感じてしまうでしょう。
仕事の悩みを相談できる相手がおらず、楽しく働くイメージが持てずに退職を考えてしまうこともあるかもしれません。
即戦力としての期待が大きすぎる
2つ目が、周囲からの期待が大きすぎることです。
たとえば、「経験者だから教えなくても分かるよね」「初月から高めの目標を設定しても大丈夫だよね」のように期待をかけすぎると、中途社員が強いプレッシャーを感じてしまう可能性があります。
分からないことを質問できなくなったり、目標を達成できない自分を過度に責めたりするようになるかもしれません。
中途社員は就労経験を積んできているとはいえ、新しい職場環境に慣れるまでは時間がかかります。
はじめは業務の流れを覚えることに専念してもらい、分からないことは気軽に質問できる雰囲気をつくりましょう。
入社後の業務にギャップを感じる
3つ目が、入社前に抱いていたイメージとのギャップが大きいことです。
たとえば、「顧客満足度を第一に考えた営業ができる」と考えて入社したものの、ノルマに追われて顧客対応が満足にできない状況であれば、大きなギャップを感じてしまうでしょう。
入社後のギャップを埋めるためには、従業員がギャップを感じやすいポイントを把握し、採用面接の段階で伝えておくことが大切です。
中途社員の入社後のフォローのコツ
ここでは、中途社員が入社したあとのフォローのポイントを解説します。
従業員との交流の機会をもたせる
中途社員がほかのメンバーと打ち解けられるように、ランチ会などの機会を設けると良いでしょう。
雑談を交えてコミュニケーションをとることで中途社員の緊張感が和らぎ、業務でもコミュニケーションがとりやすくなります。
また、入社時期の近い従業員との交流機会をつくり、同期のような関係を築けるようにサポートするのもおすすめです。
所属部署の垣根を越えて、中途社員が従業員と親交を深められるように取り計らいましょう。
適切な教育サポートを行う
適切な教育サポートを行うことも非常に大切です。
他社での就業経験があっても、業務の進め方や重視すべきポイントは企業によって異なります。
業務の経験者であっても、「はじめは分からないことがあって当然」と考え、丁寧に教育を行うようにしましょう。
面接時にギャップを埋めるための説明をする
中途社員が入社後にネガティブな感情を抱かないように、選考の段階でギャップを埋める動きを取りましょう。
入社後に感じたギャップについて従業員にアンケートを取り、面接時に求職者に共有しておくと安心です。また、選考とは別に、応募者が就業を希望する部署の従業員と1対1で話せる場を設けるのも良いでしょう。
自社の良い部分と悪い部分の両方を理解した状態で入社してもらうことで、中途社員の定着率向上が期待できます。
まとめ
今回は中途社員の定着を促すための入社後のフォローについて解説しました。
中途社員にこれまで培ってきたスキルを発揮してもらうためには、安心して長く働ける環境を整える必要があります。「経験者だからそこまでフォローしなくても大丈夫」と決めつけず、業務に慣れるまでは適切なサポートを行うことを意識しましょう。
中途社員の適応プロセスは、専門的には「組織再社会化」とも呼ばれ、新卒社員とは異なり前職で身につけた文化や価値観を手放し、新しい文化に馴染む必要があります。このプロセスにおいて、中途社員へのフォローは非常に重要です。
ある企業では、入社後1か月目にアンケートや簡単な面談を実施していましたが、それ以降のフォローは行われていませんでした。そこで、入社後3か月目には社内メンバーとの相互理解を深める研修を実施し、受け入れられている実感を醸成しました。また、業務に慣れ始めた6か月目には、今後のキャリアを見つめ直し現在の業務への向き合い方を考える研修を導入することで、中途社員の定着率やモチベーションの向上に成功しています。