プレイングマネージャーは、企業の成長やチームの活性化に大きな影響を及ぼす存在です。
本記事では、日本国内のプレイングマネージャーの実態をデータから整理し、海外の研究・論文の知見も参考にしながら、プレイングマネージャーのメリット・デメリットや成功の条件について考察します。
日本国内のプレイングマネージャーの現状

日本企業では、管理職が「二足のわらじ」を履く、いわゆるプレイングマネージャーが増えています。リクルートワークス研究所の2019年の調査では、約9割の管理職がプレイングマネージャーであると報告されました。
さらに、産業能率大学の2023年の調査では、「マネジャー業務に専念しプレイヤー業務を持たない管理職がいる企業」はわずか2.1%しかなく、残りの98%の企業では管理職がプレイヤー業務を兼務していることがわかっています。
プレイングマネージャー増加の背景
プレイングマネージャーという役割が一般的になった背景には、1990年代のバブル崩壊後に行われた大規模なリストラや、現代の少子高齢化による人手不足などが挙げられます。
大幅な人員削減によって限られた人数で組織を維持する必要に迫られた結果、管理職が実務も担うスタイルが広がりました。さらに、最近の人材不足の状況も重なり、管理職がプレイヤーとしての業務を兼務する動きは一層加速しています。
プレイングマネージャーが抱える課題
プレイングマネージャーが抱える主な課題は以下が挙げられます。
業務量・労働時間の増大
まず、管理職がプレイヤー業務までこなすことで仕事量が大幅に増加します。産業能率大学の調査では、「3年前に比べて業務量が増加している」と感じる課長が58.9%にのぼり、過去最高を記録しています。
リクルートワークス研究所の分析では、プレイヤー業務が全体の3割を超えるとチームの業績が下がるという結果が出ているにもかかわらず、実際には管理職の約85%がその水準を超えているとされています。
これにより、本来のマネジメントに割く時間が確保できず、チーム本来の力を発揮しにくくなる恐れがあります。
役割・評価基準の曖昧さ
次に、プレイヤーとしての目標と管理職としての目標を同時に求められるため、どちらを優先すればいいのかわからない状況が生まれやすいのも問題です。
例えば、個人の営業目標と部下育成のKPIの両方が設定されると、短期成果を求めるあまり、部下指導が後回しになるケースもあります。
さらに、プレイングマネージャーの努力は可視化されにくく、正当に評価されていないと感じる管理職は多くいます。「自分の評価が成長に結びついている」と思う管理職はわずか8%にとどまるとの報告もあります。
マネジメントスキル不足
また、優秀な現場担当者がそのまま管理職に昇格するため、マネジメントに関する正式な訓練を受けていないケースも多いのが実情です。
リクルートワークス研究所の調査では、管理職が抱える困りごとのトップとして「自分のマネジメントスキル不足」が挙げられており、続いて「メンバーへの対応の難しさ」「プレイヤー業務の増加」が並びます。
こうした状況では、部下育成やチーム力向上の時間が取れず、組織の成長を妨げるリスクが高まります。
長時間労働と過重ストレス
最後に、プレイングマネージャーは長時間労働や過重なストレスのリスクも抱えています。一般社員の残業削減は進んでいる一方で、管理職の労働時間に関する対策はまだ十分とはいえません。
部下の残業を減らすため、管理職自身が深夜まで仕事を肩代わりすることも少なくなく、その結果、心身の健康を損ねる管理職が増えていると指摘されています。もしプレイングマネージャーが疲弊すれば、組織全体の活力が落ちてしまう可能性があります。
日本のプレイングマネージャーは、以上のような業務負担の増加、評価の曖昧さ、スキル不足、長時間労働といった複合的な課題を抱えています。にもかかわらず、この役割を担う管理職はますます増える傾向にあり、企業としては現実に合わせたサポートや制度の見直しが求められています。
参考:
リクルートワークス研究所「管理職の多くがプレイング領域3割以上 負荷の高い1on1も見直すべき」
産業能率大学「『ミドルマネジャーの人事実態調査2023』の結果を発表」
日本の人事部「3年前と比較して「業務量が増加している」58.9%。99.2%の課長がプレーヤーとマネジャーを兼務~『第4回上場企業の課長に関する実態調査』:産業能率大学」
JMAM「プレイングマネジャーとは|増えている背景から抱えている課題まで解説」
Wistant「プレイングマネージャーの業務量は多すぎ!マネージャー体験を改善する5つのポイント」
McKinsey & Company“Are middle managers your next ace in the hole?”
プレイングマネージャーのメリット

プレイングマネージャーは必ずしもデメリットばかりではありません。以下ではプレイングマネージャーのメリットを整理します。
メリット1:現場感覚を維持できる
管理職が自分の手を動かすことで、最新の現場事情や専門知識に触れ続けることができます。技術系や営業系の職場では、そうした現場感覚が欠かせません。
部下から見ても「この上司は現場の苦労をわかってくれている」と思えるため、安心感や信頼感につながります。プレイングマネージャー本人にとっても、第一線でスキルを維持・向上させ続けられるのは大きなメリットです。
メリット2:意思決定をスピーディーに行える
自分が現場業務に関わっているため、細かな情報がダイレクトに入ってきます。報告の手間を省き、即断即決できるのは強みといえます。
顧客対応やトラブル対応などで、詳細を把握している分、スピード感ある行動が可能です。さらに、自ら率先して動く姿を見せることで、部下の士気を高める効果も期待できます。
メリット3:現場と経営層をつなげる役割を果たせる
プレイヤーとマネージャーを兼任しているからこそ、経営の視点と現場の視点の両方を持ち、理解できます。
上層部の戦略や方針をかみ砕いて現場に伝え、現場で生じている課題やアイデアを経営側にフィードバックすることで、組織全体の動きをスムーズにしやすいのが利点です。
海外の事例から見るプレイングマネージャーの実態
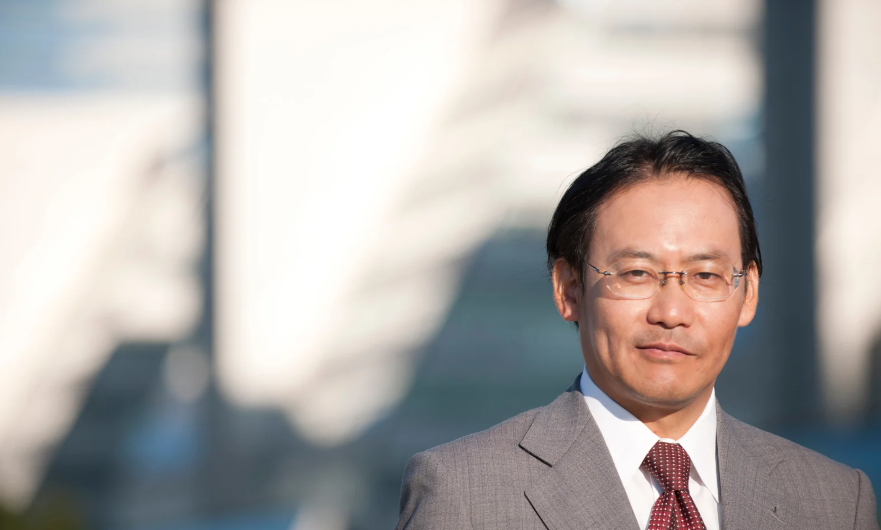
日本ではプレイングマネージャーという働き方が広く定着していますが、海外ではどうなのでしょうか。海外の複数の研究や論文をもとに、海外での管理職の実態について解説します。
1. 日米の管理職がプレイヤー業務に費やす時間の違い
経済産業研究所(RIETI)の調査によると、日本の管理職は全業務のうち33.1%をプレイヤー(担当者)としての業務に充てています。一方、アメリカの管理職は21.8%ほどで、日本のほうが管理職が現場業務をする時間が長いとわかります。
アメリカの管理職は、チーム運営や戦略立案、部下の育成など「管理業務」に多くの時間を割いているといえます。日本には「プレイングマネージャー」という言葉がありますが、アメリカではそこまで一般的ではありません。
2. プレイヤーコーチ(Player–Coach)型がうまくいく条件
海外でも「プレイヤーコーチ(Player–Coach)」と呼ばれるリーダーが存在し、専門知識を活かしながらチームを率いるケースがあります。
マッキンゼーが公開する記事によると、プレイヤーコーチがうまくいく条件として、チーム規模が小さいことや、管理職自身がチームにとって重要な専門能力を持っていることを挙げています。
しかし、部下の人数が多くなったり、管理職が担当者としての業務に時間を割きすぎたりすると、部下との面談やチームマネジメントに時間を割けなくなり、うまくいかない場合もあるようです。
3. スペシャリストとマネージャーを分ける考え方
アメリカなど海外では、「優秀な人は必ず管理職になる」という考え方を見直し、専門分野に特化したキャリアと、チームを率いるキャリアを分ける企業が増えています。
先述のマッキンゼーの記事によると「組織は2つの昇進ルートを用意するのが望ましい」としており、リーダーシップが得意な人と、技術や知識が得意な人が、それぞれ成長できる道を提供することを提案しています。
日本では、現場で成果を上げた人がそのまま管理職になるケースが多いですが、海外の事例は「適性がある人を管理職にしたほうがチーム全体がうまくいく」ことを示唆しています。
4. 中間管理職の役割が組織の成果を左右する
海外でも、プレイングマネージャーを含む中間管理職の重要性は多くの研究で強調されています。例えば、Gallupの調査では、中間管理職の質が社員のやる気や組織の生産性を大きく左右すると報告しています。
特に、「優秀なプレイヤーが必ずしも優秀なマネージャーになるとは限らない」「新任の管理職は十分な準備ができていないままリーダーになることが多い」といった指摘は、海外でもたびたび議論されています。
海外の動向から学べること
海外では、管理職が部下の仕事をサポートしやすい環境を整えたり、専門職と管理職を分けたキャリアパスを用意したりすることで、社員の力を最大限に引き出しています。
日本のプレイングマネージャーは、どうしても「自分が現場を回さないといけない」という思いが強くなりがちですが、海外の例を参考に、チーム運営や人材育成にしっかり時間をかけられるよう工夫することが大切だと言えるでしょう。
参考:
独立行政法人経済産業研究所「第4次産業革命における管理職の役割:日米比較の観点から」
McKinsey & Company“Are middle managers your next ace in the hole?”
Gallup”The Manager Experience”
成功するプレイングマネージャーの条件と対策

プレイングマネージャーとして成果を上げるためには、単に「自分が動く」だけでなく、チーム全体の力を引き出す工夫が必要です。以下では、プレイングマネージャーがうまくその役割を果たし、組織に貢献するためのポイントを紹介します。
効果的な時間管理と業務の割り振りが鍵
プレイヤー業務とマネジメント業務の配分を、意識的にコントロールすることが何より大切です。マッキンゼーが公開する情報によると、プレイヤーとしての仕事が時間の過半数を占める状況では、管理職として十分に機能しづらいといわれています。
つまり、部下への業務委譲やタスクの優先順位づけなどを工夫し、マネージャーにしかできない仕事(例えば部下育成やチーム戦略の立案など)に時間を確保しなければなりません。
最初は「自分でやったほうが早い」と感じるかもしれませんが、長い目で見ればメンバーの自主性を高めることで、チーム全体の成果が底上げされます。
プレイヤーとマネージャーの両立にはリーダーシップが不可欠
プレイングマネージャーに求められるのは、現場を動かす技術力や実行力だけではありません。人を率いる力や、部下の力を引き出すコミュニケーション能力も同時に求められます。普段から部下と密に話し合い、彼らの状況をつかんだうえでアドバイスや指導を行うことが重要です。
1on1のミーティングを定期的に設定するのも一つの方法ですが、無理に頻度を増やして管理職に過度な負担がかかるようなら見直す必要があります 。
プレイヤーとして手を動かすことは大切ですが、あくまでも最終的にはメンバーが自律して動けるようにサポートする姿勢が望ましいと言えます。
企業が取り組むべき支援策
プレイングマネージャーの活躍を支えるためには、企業としての仕組みづくりも欠かせません。以下では、役割の明確化・評価制度・育成プログラム・業務プロセスの見直し、4つの観点から対策を見ていきます。
1. 役割を明確にする
まずは、プレイングマネージャーにどのような役割を期待するかをはっきり示すことです。Gallup社の調査でも、役割があいまいだと管理職のパフォーマンスが下がると指摘されています。
例えば「チーム目標の達成と部下育成を最優先とし、個人の成果はあくまで付随的なもの」といった形でミッションを明確にすれば、管理職は行動の指針を整理しやすくなります。
2. 評価制度の整備
プレイングマネージャーは、プレイヤーとしての成果だけでなく、部下育成やチームの成果をどれだけ高めたかも正当に評価される仕組みが必要です。
部下の成長や離職率の改善など、マネジメントの成果がわかりやすく反映される指標を設定すれば、「個人業績ばかりが評価される」という不満を和らげられます。
3. 育成プログラムや研修の充実
多くの管理職は、マネジメントを体系的に学ぶ機会が少ないまま現場で試行錯誤しているのが現状です。企業内での管理職研修や外部セミナーへの参加など、計画的にマネジメントスキルを習得できる場を提供すると効果的です。
産業能率大学の調査では、「部下育成力」「職場のビジョン構想力」「事業戦略策定力」など課長に必要な能力が多岐にわたると報告されています。こうしたスキルは一度の研修で身につくものではないため、継続的に学べるしくみが望ましいでしょう。
4. 業務プロセスの見直し・権限移譲の推進
プレイングマネージャー1人に仕事が集中しすぎないよう、マニュアル化や情報共有ツールの導入などを通じて、チームが自律的に動ける体制を整備することも大切です。
専門スタッフや外部リソースに任せられる仕事があれば積極的に委託し、管理職が細部に手を出さなくても業務が回る流れをつくります。
働き方改革の中で管理職だけが長時間労働にならないよう、会社全体で「管理職をサポートする」という姿勢を持つことが求められます。
プレイングマネージャーは、現場に深く関わることで生まれる強みと、同時に大きな負担を抱えやすい存在です。
本人が時間管理やコミュニケーションスキルを磨くとともに、企業としても役割や評価を明確化し、研修や業務プロセスの工夫によってサポートすれば、プレイングマネージャーのポテンシャルを最大限に引き出すことができるでしょう。
参考:
McKinsey & Company“Are middle managers your next ace in the hole?”
JMAM「プレイングマネジャーとは|増えている背景から抱えている課題まで解説」
独立行政法人経済産業研究所「第4次産業革命における管理職の役割:日米比較の観点から」
Gallup”The Manager Experience”
まとめ
日本では、人口減少や組織の効率化などの背景から、プレイングマネージャーが今後も増えていくと考えられます。
現場を熟知した管理職がチームを率いることは大きな強みになる一方、重い業務負担や評価の曖昧さ、マネジメントスキルの不足などの課題を放置すると、組織全体の成長を阻害しかねません。
企業としては、プレイングマネージャーを「便利な人材」として使い潰すのではなく、役割を明確にし、適切な評価や研修制度を整えて支援する必要があります。将来的には管理職と専門職を分けるなど、人事制度の見直しも選択肢となるでしょう。
プレイングマネージャーが本来の力を発揮できれば、変化の激しい時代でも高い組織パフォーマンスを維持できる可能性が高まります。

