部下との目標設定面談を実施したものの、具体的な行動に繋がらず、モチベーションの向上にもなっていないと悩んでいる方も少なくないでしょう。
部下との目標設定面談をとおして成果を上げる際に、上司と部下が一緒に目標を設定し、評価・改善していくマネジメント手法であるMBO面談が効果的です。
本記事では、MBO面談の効果的な進め方やメリット・デメリットについて解説します。本記事を読むことで、MBO面談を効果的に実施できる内容となっています。

この記事の監修者
曽和 利光(そわ・としみつ)
株式会社人材研究所 代表取締役社長
新卒で株式会社リクルートに入社後、ライフネット生命保険株式会社と株式会社オープンハウスを経て、2011年に株式会社人材研究所を設立。「人と、組織の可能性の最大化」をテーマに掲げ、人事、採用にコンサルティング事業などを展開。『人事と採用のセオリー』など、これまで多くの書籍を出版し、いずれも大きな話題を集めている。
部下との目標設定(MBO)面談とは

部下との目標設定(MBO)面談について、経営や組織開発を専門とするジョセイ・バス・ファイファー出版社が発行する、トーマス・M・トムソン氏による論文に基づいて解説します。
MBOの概要
MBOとは、Management by Objectivesの略であり、1954年にピーター・ドラッカーによって提唱されたマネジメント手法のことです。
具体的には上司と部下が協力して具体的な目標を設定し、その達成度を評価するプロセスのことを指します。MBOでは、部下の目標と会社の目標や方向性をすり合わせるため、部下のモチベーションや生産性の向上が可能になります。
MBOの目的
MBOの目的は部下のモチベーションの向上と最終的な会社の目標達成です。MBOの目的は、主に以下の3つになります。
- 目標の明確化
- 部下のモチベーション向上
- 成果の評価とフィードバック
MBOでは組織の目標を達成するために、上司と部下の面談で具体的な目標を設定します。自分で設定した目標を達成すると、達成感と満足感が得られるため、部下のモチベーションの向上に役立ちます。
さらに、業績を定期的に見直し、必要に応じて改善策を講じることが可能になり、適切な評価やフィードバックが提供できます。
参考:
OKR・KPIとの違い

OKRは、Objectives and Key Resultの略で、直訳すると「目標と主要な成果」、KPIは、Key Performance Indicatorの略で、直訳すると「重要業績評価指数」となります。
MBOとKPIがマネジメント手法であるのに対し、OKRは目標の達成度合いを測る「指標」とされています。以下は、それぞれの目的と共有対象をまとめた表です。
| 目的 | 共有対象 | |
| MBO | 部下のモチベーション向上や最終的な会社の目標達成 | 部下と上司 |
| OKR | チームの団結力の強化や生産性の向上 | 全社員 |
| KPI | 目標達成のために必要なプロセスが辿れているかを確認できる | チーム内 |
MBOやOKR、KPIはどれか一つを実施するのではなく併用することで相乗効果を得られます。MBOとOKR、KPIの違いについて、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
MBOのメリット・デメリット
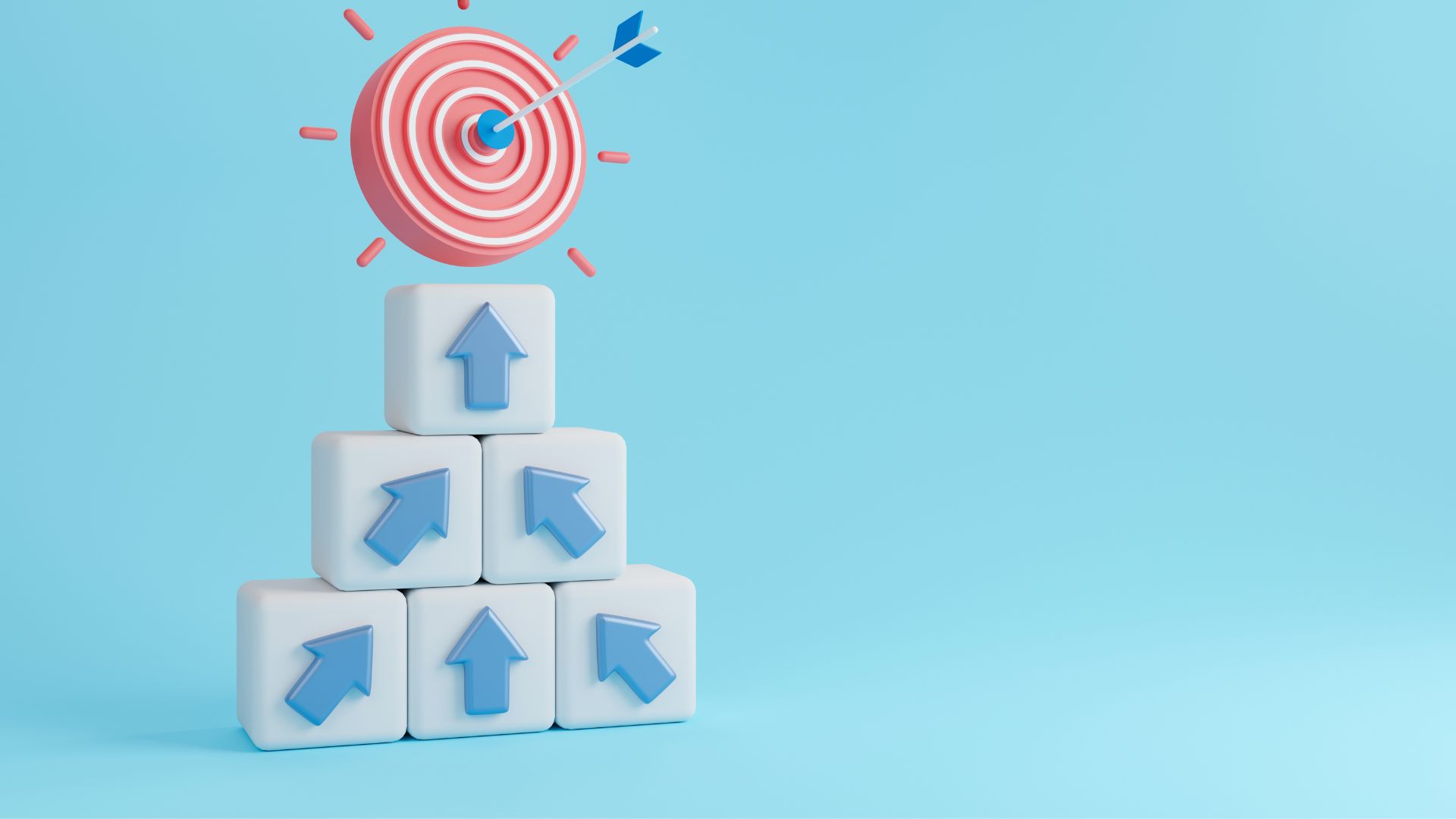
MBOのメリットとデメリットについて、経済社会学者のアダム・ヘイズ氏による記事を参考に解説します。
MBOのメリット
以下では5つのMBOのメリットを解説します。
モチベーションの向上
前述したとおり、MBOは部下のモチベーションの向上に役立ちます。MBOでは目標設定を部下自身が行うため、当事者意識や責任感が高まり、より意欲的に業務に取り組むようになります。
たとえば、従来の上司から一方的な目標設定ではなく、部下が自ら売上目標や顧客獲得目標を設定する場合、達成意欲が高まり、生産性の向上につながりやすくなります。
MBOは、部下のモチベーションと責任感を高める効果的な手法といえます。
パフォーマンスの向上
MBOは、部下の明確な目標と期待値を設定することで、生産性の向上を促進します。目標が明確であることで、部下は何をすべきかを理解し、努力の方向性を定めることができます。
たとえば、漠然と売り上げを伸ばすといった目標ではなく、来期までに新規顧客を20件獲得するといった具体的な目標を設定します。このような具体的な目標や行動計画を立てることで、成果につなげやすくなります。
MBOは、目標達成度を測りやすくすることで、生産性の向上が見込める手法といえます。
コミュニケーションの改善
MBOは上司と部下のコミュニケーションの改善に役立ちます。目標設定や進捗確認のために、定期的な面談が実施されるため、自然とコミュニケーションの頻度が増加し、上司と部下のコミュニケーションの活発化が見込まれるでしょう。
週次の進捗確認や月次の目標達成度レビューなど、定期的なコミュニケーションを通して、業務上の課題や進捗状況を共有することで、相互理解を深め、より良い関係を築くことができます。
明確な目標が立てられる
MBOは、会社全体の目標を明確化し、社員それぞれの努力を会社の目標達成につなげます。会社の目標を達成するために、部下がそのような役割を担い、どのような成果を出すべきかを明確にすることで、会社全体の方向性を統一できます。
企業目標が「市場シェア10%アップ」の場合、営業部は「新規顧客獲得数100名増」、マーケティング部は「クリック率を3%に引き上げる」といった具体的な目標を設定することで、会社全体の目標達成に貢献できるでしょう。
部下の成長が期待できる
MBOは部下の能力開発とキャリアアップを促進が可能なため、部下の成長が期待できます。
目標達成に向けた努力を通して、部下は自身の強みや弱みを認識し、成長に必要なスキルや知識を習得することができます。
目標達成のために必要な研修やセミナーへの参加を促したり、上司がフィードバックやコーチングを行うことで、部下のスキルアップを支援します。
部下に成長の機会を提供することできるため、その結果、組織全体の能力向上に繋がるといえます。
MBOのデメリット
MBOデメリットを解決策もあわせて、解説します。
時間とリソースの消費
MBOは時間設定や進捗確認、評価など、従来のマネジメント手法よりも多くの時間とリソースを必要とします。MBO導入初期は、目標設定や評価基準の策定に時間がかかる上、 MBO導入初期は、目標設定や評価基準の策定に時間がかかる上、上司・部下ともに目標設定のトレーニングも必要となるためです。
たとえば、目標達成度を測るための適切な指標を各部署や個人レベルで設定する必要があるため、多くの会議や調整が必要となります。
しかし、適切なツールやシステムを導入することで、この問題を軽減できます。
具体的な対策:
目標管理ツールを活用し、進捗状況の共有やフィードバックを効率化する
上記のような対策を取ることでMBOへの時間やリソースの消費を抑えることができるでしょう。
短期的な目標に偏る
MBOは、測定可能な目標を設定することに重点を置くため、短期的な成果に偏り、長期的なビジョンや戦略につながりにくい傾向があります。
短期的な目標の方が、達成度合いを明確に示しやすいという側面があるためです。この問題を防ぐには、短期的な目標と長期的なビジョンを結びつけることが重要です。
具体的な対策:
3年後の売上目標を達成するために、今年度は顧客満足度を向上させるといった具体的な目標を設定する
上記のような対策を実施することで、短期目標と長期ビジョンの整合性を測ることができます。
柔軟性の欠如
MBOは一度設定した目標を達成することに固執しすぎると、状況の変化が合った場合に対応が遅れ、柔軟性を欠く可能性があります。
目標設定に固執するあまり、市場の変化や新たなビジネスチャンスを逃してしまう可能性があるためです。
具体的な対策:
定期的に目標を見直し、必要に応じて柔軟に変更する仕組みを設ける
市場動向や競合状況を踏まえ、目標の妥当性を評価し、必要があれば軌道修正を行うことで、柔軟性を維持できます。
チームワークの阻害
MBOは個人の目標達成に重点を置くため、チームワークや協調性を阻害する可能性があります。
個人の目標達成が評価に直結する場合、チーム全体よりも個人の成果を優先してしまうことがあるためです。
たとえば、営業目標達成のために、他の営業担当者との情報共有や協力体制を築かずに、単独で活動してしまうといった状況が考えられます。
具体的な対策:
チーム全体の目標と個人の目標を明確に関連付け、チームワークを促進する評価基準を設ける
チーム全体で目標達成に貢献した個人を評価することで、協調性を高めることができます。
事務処理が増える
MBOは目標設定や進捗報告、評価など多くの事務処理を伴うため、上司や部下の負担が増える可能性があります。
目標設定や進捗状況の記録、評価のための資料作成など、従来の業務に加えて事務処理が発生します。
たとえば、毎月の目標達成度合いを報告するための資料作成や、評価面談のための準備に多くの時間を費やす必要が生じます。
具体的な対策:
目標管理システムやタスク管理ツールを導入し、進捗状況の共有や報告を自動化する
ITツールを活用し、進捗状況の共有や報告の自動化を効率化することで、事務処理の負担を軽減できます。
【進め方】MBO面談のステップ

MBO面談の進め方を、ネブラスカ大学リンカーン校が公開するデポール大学経営学部の教授であるケネス・R・トンプソン氏らによる論文を参考に解説します。
全体目標を設定する
MBOでは、最初に全体目標を明確に設定することが重要です。全体目標と整合性のとれた個人目標を設定することで、組織全体の成果に貢献できます。
たとえば、会社全体の目標が売上10%アップであれば、個人目標も売上アップに関連するものを設定すると良いといえます。全体目標を設定し、共有することで、個人目標も設定しやすくなるでしょう。
事前準備をする
MBOを実施するための準備として、部下をマネジメントする上司への研修を行いましょう。上司への研修は、MBOの目的や進め方、部下との目標設定や評価の方法について、上司の理解を深めることができ、部下への適切な指導に役立ちます。
同論文では、上司を対象に、MBOの背景や具体的な実施手順に関する7回の研修(各2時間半)を実施しています。研修では、目標設定の仕方や進捗管理の方法、フィードバックの仕方などを具体的に指導する必要があります。
個人目標を設定する
上司と部下が面談を行い、個人の目標を設定します。個人の能力やキャリア目標を考慮し、組織目標への貢献度が高い目標を設定しましょう。
論文では、上司が部下と個別に面談を行い、数値化・行動目標化した目標を設定することが重要とされています。目標は具体的、測定可能、達成可能、関連性があり、期限が明確に導き出せるSMART原則に基づいて設定すると良いでしょう。 SMARTについては後ほど解説します。
定期的な評価
設定した個人目標に対する進捗状況を定期的に評価することが重要です。進捗状況を把握し、必要があれば目標の修正や達成するためのサポートを行いましょう。
定期的な評価は、フィードバックや進捗共有の機会として活用し、従業員のモチベーション向上が期待できます。
参考:
「SMART」で目標を決める

部下との目標設定面談で成果を引き出すには、曖昧な「頑張ります」ではなく、明確で測定可能な目標設定が欠かせません。
カナダ・トロント大学の組織行動学教授ゲイリー・レイサムと、米メリーランド大学名誉教授エドウィン・ロックによる「Enhancing the Benefits and Overcoming the Pitfalls of Goal Setting」(2006)という論文では、効果的な目標には「SMART」という5つの条件が重要であるとされています。
これらを活用することで、部下は達成に向けた道筋を明確に描きやすくなり、上司も進捗管理やフィードバックを行いやすくなります。
Specific(具体的)
本論文では「目標が具体的であればあるほど、成果は高まる」という実証結果が示されています。曖昧な目標は自己評価に幅を持たせてしまい、本人が「これくらいで十分だ」と解釈してしまう危険があります。
面談時には、部下が述べた漠然とした目標から、対象・行動・成果の3点を明確化しましょう。そのためには「いつまでに、誰に対して、何を、どのくらい」という5W1Hを使って掘り下げるのが有効です。具体化された目標は行動指針となり、迷いを減らします。
例:
- 営業職:「売上を上げたい」→「主要取引先5社への提案件数を、来月末までに10件に増やす」
- 事務職:「ミスを減らす」→「請求書入力時の誤りを、3か月以内に月1件以下に抑える」
Measurable(測定可能)
論文では、目標は「基準(value standard)」との比較で達成度を判断すべきとされています。数値や指標がない目標は、達成度を正確に測れず、進捗確認や改善点の特定が困難です。
面談では、目標に必ず評価指標を組み込みます。数値(売上金額・件数・比率など)が望ましいですが、業務によってはアンケート結果やエラーレートなどの定性指標も活用できます。また、進捗を測るための中間チェック日程もあらかじめ設定すると、モチベーション維持に役立ちます。
例:
- マーケティング:「Webサイトの訪問者を増やす」→「3か月以内に月間訪問者数を2万PVから2万5千PVに増やす」
- カスタマーサポート:「対応スピードを改善する」→「問い合わせ対応の平均時間を30分以内に短縮する」
Achievable(達成可能)
高い目標は努力と集中力を引き出しますが、知識やスキル不足の場合は逆効果になるとされています。難しすぎる目標は達成意欲を削ぎ、早期の挫折を招きます。
面談では、現状の能力・リソース・業務環境を確認し、達成可能性を見極めましょう。達成が難しい場合は、最初に学習目標(知識習得やスキル向上)を設定し、その後に成果目標へ移行する流れが効果的です。また、達成までのステップを明確化し、小さな成功体験を積ませることで自信を育てます。
例:
- 新人営業:「半年で売上を20%アップ」→達成困難と判断し、「3か月以内に全商品ラインナップを理解し、提案時に最低5種類の商品を説明できるようにする」に変更
- 新任リーダー:「プロジェクトを全て期限通りに完了」→「進行管理ツールの操作を1か月以内に習得し、全案件の進捗を可視化」
Relevant(関連性)
論文では、目標が組織全体の「上位目標(superordinate goal)」と結びつくことで、協力関係や一体感が生まれるとされています。部下個人の目標が、部署や会社の方向性と無関係だと、努力が組織成果に結びつかず、本人の貢献実感も薄れます。
面談では、個人の業務目標と組織の戦略・方針をリンクさせ、その意義を丁寧に説明しましょう。これにより部下は、自分の目標達成が組織全体の成果にどう貢献するかを理解し、やる気を高められます。
例:
- 部署目標が「新規顧客開拓率15%向上」の場合:営業担当の個人目標は「毎月5件の新規商談を獲得」
- 部署目標が「顧客満足度向上」の場合:サポート担当の個人目標は「アンケートで90%以上の満足評価を獲得」
Time-bound(期限設定)
大きな目標は中間目標(sub-goal)に分割し、期限を設けることで達成確率が高まると論文では述べられています。期限のない目標は先延ばしされやすく、モチベーションも低下します。
面談では、最終期限だけでなく、途中のチェックポイントやマイルストーンを設定します。また、進捗レビュー日程をあらかじめ決めておくことで、期限意識が高まり、遅れの早期発見が可能になります。期限は短すぎても長すぎても効果が下がるため、業務内容に応じて適切な期間を設定することが重要です。
例:
- 営業職:「半年で売上を15%増」→中間目標として「3か月で8%増を達成」
- 企画職:「1年間で新サービスを立ち上げ」→「2か月以内に企画書完成」「4か月以内に試作品完成」などマイルストーンを設定
MBOで注意すべきポイント

MBOで注意すべきポイントについて、ビジョン・イン・レジャー&ビジネスが公開する、オクラホマ大学助教授のヘンリー・アイゼンハート氏らによる論文を参考に解説します。
上司と部下の双方が積極的に参加する
MBO面談は、上司と部下がともに目標設定を行う、双方向のコミュニケーションが重要な手法です。上司からの一方的な指示ではなく、部下の意見や考えを反映することが、目標に対する当事者意識を高め、モチベーション向上につながります。
目標設定の際には、上司が一方的に目標を提示するのではなく、部下自身の考えや希望を聞き、共に目標を検討するプロセスを大切にします。
双方が積極的に意見交換することで、目標に対する共通認識を深め、より効果的な面談にすることができます。
問題を特定し、解決策を検討する
目標設定だけでなく、目標達成を阻害する可能性のある問題点についても、面談で話し合い、解決策を検討することが重要です。問題を事前に特定し、対策を立てることで、目標達成の可能性を高めることができます。
資源不足やスキル不足、組織体制の問題など、目標達成を阻害する可能性のある要因を洗い出し、具体的な解決策を上司と部下が共に考えます。
問題解決に向けて上司が積極的にサポートすることで、部下の不安を軽減し、安心して目標達成に集中できる環境を作ることができます。
建設的なフィードバックを行う
MBO面談では、目標達成の度合いやプロセスに対する評価だけでなく、部下の成長を促すような建設的なフィードバックを行うことが重要です。
具体的な行動や成果を挙げて、フィードバックすることで、部下は自身の強みや弱みを客観的に認識し、今後の行動改善につなげることができます。
目標を達成できた場合は、具体的な行動や成果を挙げて適切に評価し、改善点がある場合は、具体的な行動指針を示すことで、次につなげられるように促します。
建設的なフィードバックは、部下のモチベーションを高め、成長を促進する上で非常に重要です。
参考:
まとめ
本記事では、部下との目標設定を適切に進めることができるMBO面談のメリットデメリットや進め方について解説しました。
MBOは、正しく運用することで、部下のモチベーションやパフォーマンスの向上、組織全体の目標達成に大きく貢献する効果的なマネジメント手法です。
本記事を参考にしてMBOを導入し、より良い組織作りを目指しましょう。


