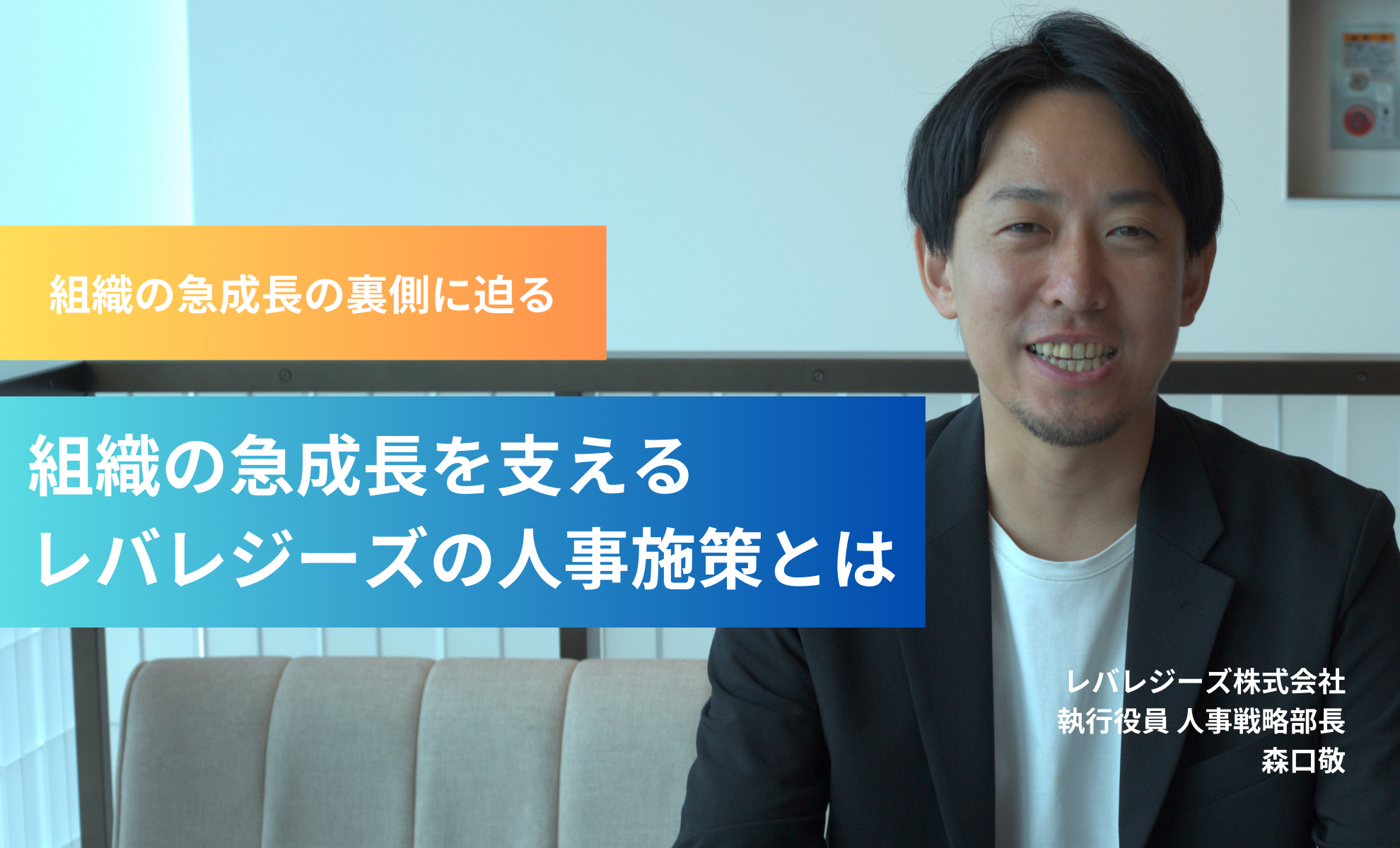「社員の離職が増えて困っている」
「社員の仕事に対するモチベーションを向上させたい」
そのように悩んでいる方もいらっしゃると思います。
今回は、中堅中小企業向けのコンサルティング会社を経て、レバレジーズに入社し、大阪支店の立ち上げやメディカル事業部の統括、そして現在の人事戦略部の設立など、多岐にわたる経験を持つ森口さんに、レバレジーズの成長を支える人事施策についてお伺いしました。
| 森口 敬 2011年にレバレジーズに中途採用で入社。前職では中堅中小企業向けのコンサルティング会社で新規事業立ち上げや採用活動に従事。レバレジーズではメディカル事業部の大阪支店立ち上げでジョインし、支店長を務めた後に人事部門で新卒採用の責任者に。現場に戻り名古屋支店の再建を果たした後、メディカル事業部長、レバレジーズメディカルケアの役員として医療介護分野に貢献。現在は複数の人事機能を統合し人事戦略部として、人材育成や組織開発、評価報酬を含めた制度設計を担当。 |
森口さんのこれまでのご経歴

Q. これまでのご経歴について教えてください
私は2011年に中途採用でレバレジーズに入社しましたが、前職は中堅中小企業向けのコンサルティング会社に新卒で入社しており、3年半ほど勤務していました。主に新規事業の立ち上げに従事しており、新卒の人材紹介、採用コンサルティング、そして研修を中心とした組織改善の提案に携わってきました。
レバレジーズに入社後、最初に担当したのはメディカル事業部(現:看護エージェント)の大阪支店立ち上げです。3年半ほど大阪支店におりまして、支店長を務め、その後、人事部門に異動し、新卒採用の責任者を務めました。
しかし、メディカル事業部の組織状況を鑑み、再び現場に戻ることになり、名古屋支店に赴任。約8ヶ月間、支店の立て直しに取り組みました。その翌年にメディカル事業部長に就任。2018年に医療・介護・ヘルスケア領域に特化したレバレジーズメディカルケア株式会社を立ち上げ、役員として、主に看護師の人材紹介と人材派遣を担当し、7年間ほど従事していました。
2022年には事業側から中途採用などコーポレート側を兼任しながら、現在は分かれていた複数の人事機能を統合し人事戦略部を立ち上げ、人材育成や組織開発、配置や人事評価報酬を含めた制度の設計などを管掌しています。
レバレジーズが主に取り組んでいる人事施策とは

Q.これまでレバレジーズ社内で組織改善のために実施した主な施策については、どのような施策がありますか?
離職率の改善、生産性の向上、人材の最適配置、若手社員の抜擢、採用力の向上など様々ありますね。
その中でも起点となるのは社員や組織の現状把握です。モチベーションサーベイや面談を通じて、社員の状況を把握しています。
モチベーションサーベイは7年ほど前から導入し、各部署で徐々に展開してきました。そのサーベイの結果を分析し、対策を講じています。
把握した情報に基づいて、各事業部や人事戦略部が対応にあたります。例えば、離職リスクが高い社員については、部門長とともに状況を確認し、必要な施策を講じる形です。また、上司と部下の関係に問題がある場合は、フィードバックや場合によっては配置転換を行い、問題を解消しています。
現場の改善などはそれぞれの部門長が主体となって施策を実行していく必要がありますが、私たちはそのサポート役としてフィードバックや提案を行い、組織全体の改善を目指しています。
離職率改善

Q.離職率改善についてはどのような施策に取り組まれてきましたか?
離職率低減に向けて取り組んできた施策の一環として、適切なタイミングでのフォローアップ研修の実施、従業員の配置転換、称賛文化の醸成、部門長や事業部長の評価制度改善、そのほか月給比率の見直しにも取り組んできました。
過去には入社1、2年目のフォローアップに問題があった時期があり、上記のような施策を中心に対策を講じた結果、今では大幅に改善されました。1、2年目のフォロー以外に、他社でもよく課題として上がる話として「経験を積んで活躍している3〜5年目の離職があると思います。実際、弊社内でも課題として捉えています。
活躍している社員だからこそ、問題がないと思ってしまい、状況の把握が遅れ、転職先が決まってしまうこともあります。「相談してくれたら、社内のキャリアも提示できたのに」というようなことが発生しないように、しっかりと本人のWillや状況を把握し、社内でのキャリアを見せていくことが大切ですが、規模が大きくなるとその難易度が上がるのも事実です。
このような状況を防ぐために、モチベーションサーベイや適性検査、面談を通じて状況を把握し、対策を打つことが大切です。
加えて、活躍社員は成果が出ていることもあり、足りない点のフィードバックをもらえる機会が減り、成長を感じづらくなり社内でのキャリアに不安を覚えるということもあります。結果として、社外でチャレンジしたいというような施工に至る場合もあります。
そういったことが起きないように、弊社の今後の課題として挙げられるのは、フィードバック文化の強化です。レバレジーズ全体において、ポジティブフィードバック文化は活発でかなり浸透していますが、ネガティブなフィードバックや上司に対して適切な意見を伝えることが弱い傾向にあります。
適切なフィードバック文化が醸成されていくと、セルフアウェアネスが高まることと適切なマネジメントがよりなされるようになります。その結果、役職や年次に関わらず組織にいることによっての成長実感をより持てるようになることが離職率低減に繋がると考えています。
生産性の向上

Q.続いて、生産性の向上についてお聞かせください。現在はどのような取り組みをされていますか?
生産性向上については、各部署によってアプローチが変わってくるのですが、営業やキャリアアドバイザーにおいては、1人当たりの生産性をモニタリングし、どのタイミングでどれくらいの利益に貢献できるかを予算に基づいてグラフ化しています。合わせて、どのタイプの人材がどの部署での活躍確率が高いかという分析も行っています。これにより、活躍確率が高く、組織としても生産性が高くなる部署に人材を配置する方針を取っています。
加えて大切になるのは、部署ごとでの生産性を高めるために、成約などの結果指標だけでなく、成約に至るまでの「先行指標」を設定し、問題が発生する前に対処することです。
先行指標は事業部によって異なりますが、先行指標をモニタリングする仕組みを設計し、やるべきことを確実に実行するKPIマネジメントを実践しています。
ただ、それだけでは主体性が失われたり、仕事の面白みを感じられなくなる恐れもあります。そこで、社員が自ら考えて提案する風土や仕組みを整え、必須事項(Must)の完遂の先に、自分たちの意志(Will)を反映させられる意義を見出せるようサポートしています。
その一環として、1on1やコーチングの仕組みを取り入れたり、新規事業や改善提案を誰でも行える場の提供を行い、社員の成長と意欲を引き出すことにも注力しています。
1on1の質の向上

Q.1on1の質の向上についても施策として取り組まれているとのことですが、具体的にはどのようなことを行っているのでしょうか?
まず、一般的に理想的な1on1とは、1on1を受ける側の社員の課題が解決される場であることです。一方悪い1on1は、上司が伝えたいことだけを伝えて終わってしまうパターンで、あまり効果的ではありません。
「Will Can Must」を用いて中長期的なキャリアについて話し合い、業務の悩みに対して解決策を見つけることが理想です。ただ、どうしても業務の優先度が上がり、中長期的なキャリアについて話し合う時間が取れない場合も発生します。
そういったことを解決するために、弊社ではこの理想の1on1を実現するためにも、「社内コーチング制度」と呼ばれる制度があり、コーチングに興味がある社員や学んでいる社員がコーチとして選ばれる仕組みがあります。
この制度では、研修を受けたコーチからのコーチングを受けられるため、直属の上司以外に話を聞いてもらうことで、新たな気付きを得ることができます。
またコーチにもコーチングを受けた側からフィードバックをもらうようにしており、コーチングスキルが伸びるような仕組みを設計しています。
これにより、1on1の場で適切に成長につながるコミュニケーションが行われているかを可視化し、フィードバックの質向上を実現できると考えています。
若手社員の抜擢

Q.レバレジーズでは、若手社員が活躍しているイメージがありますが、社内で取り組まれている施策や人事制度はありますか?
若手社員の抜擢は制度よりも文化によって促進されています。レバレジーズでは優秀な若手社員に仕事を任せた方が組織として良い結果を生むという文化が根付いています。
この文化の醸成は代表の影響が大きく、年次や年齢に関係なく、優秀な人にはどんどんチャレンジさせるべきだという考えを持っており、それを実際に実行してきた結果、若手社員の抜擢が進んできました。
過去には代表に「こういう仕事をさせてください」と直談判をして抜擢されるケースがありました。このように優秀な人材を抜擢できることはよいことなのですが、自ら手を挙げる社員以外にも抜擢すべき適切な人材は社内に多くいると思っています。
現時点で優秀な人材の能力を適切に把握するためにも、定量的な指標や適性検査を活用すると同時に、素養のある人材を把握できるように努力しています。さらに、各事業内でも年次・年齢関係なく、適任な人材を把握するように日々社員とのコミュニケーションを取ってくれています。
これにより、リーダー候補やマネージャー候補、事業部長候補となりうる人材を見つけ出し、人材開発会議でのサクセッションプランの作成に役立てています。
このように制度というよりも、創業期から培われてきた文化が若手社員の抜擢に繋がっていますが、組織の拡大に伴い、より定量的なアプローチで人材を発掘する取り組みを進めているところです。
人事施策における今後の展望は

Q.人事施策における今後の展望について教えてください。
これからもレバレジーズを「成長できる場所」だと感じてもらえる組織にしていきたいと考えています。そのためには社員一人ひとりが成長に貪欲であり、事業や社会課題に積極的に取り組む姿勢を持つことが重要です。そうした姿勢を持つ社員が「この会社にいるからこそ、面白いことができ、成長できる」と感じてもらえるような組織を目指しています。
そのような組織を実現するために、社員に多くの経験を積んでもらうことが必要です。
また同時に、私の個人的な考えですが、常にオープンな組織でありたいと強く思っています。部署が違ったり、年次や年齢、役職や役割が異なっていても、オープンに意見を言い合える環境が理想です。
もちろん、経験を積まれている方には敬意を払うべきだと思いますが、その敬意を持ちながらも、言うべきことはしっかりと言い、それを受け入れる姿勢が大切です。
こうした相互の尊重とオープンなコミュニケーションが根付いた組織は、働いていて楽しく、より世の中に良い価値を提供できると感じてます。そして、拡大していく中でもそのような環境を維持発展させることができれば、組織全体が成長し続けることができると感じています。心配りをしながらも、必要なことはしっかりと伝え合うことが、組織の持続的な成長に繋がると考えています。
まとめ
今回はレバレジーズで取り組む人事施策の全体像についてお伺いしました。組織の急成長を支える人事施策の裏側には近道はなく、日々の小さな積み重ねにより、大きな結果を生み出していることがうかがえました。
今後はそれぞれの人事施策についてより詳しく掘り下げていきます。社内の人事施策で何を実施するべきか悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。