「部下が全然仕事をしてくれなくて困っている…」
「部下に仕事をさせるにはどうすればいい?」
このような悩みや疑問を持つ管理職も多いでしょう。部下が仕事をしないときはさまざまな原因が考えられ、上司の心配り次第で大きく改善できる可能性があります。
本記事では、仕事をしない部下の特徴や対処法について解説します。部下が前向きに仕事に取り組める職場づくりを目指す方は、ぜひ参考にしてください。
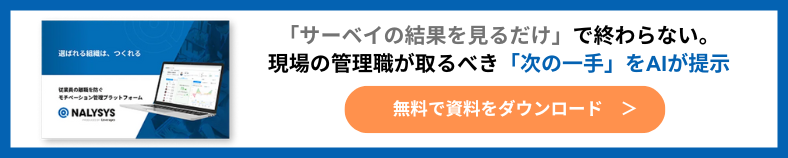
仕事をしない部下の特徴

仕事をしない部下によくある特徴を解説します。
責任感がない
責任感が欠けている部下は、与えられた仕事をしない傾向にあります。
株式会社ネクストレベルが実施した「こんな部下は困る!ランキング」によると、困った部下の特徴としてもっとも多く挙げられたのが「責任感がない」でした(34.9%)。以下は、同調査で挙げられた「責任感がない部下の行動例」の一部です。
- 指示した仕事を、「わからない」という理由で他の社員に押し付ける
- 仕事の締め切りギリギリになって「できない」と泣きつく
- 仕事の説明を受けている途中で、断りもなく昼食に出かける
- 急に連絡が取れなくなり、そのまま引継ぎもなく休職する
上記を見ると、責任感がない人には「当事者意識が欠如」していることがわかります。自分が仕事をしないことで、会社や周囲がどれだけ迷惑を被るのか理解できておらず、「自分がやらなくても周りが何とかしてくれる」と考えているのでしょう。
やる気がない
部下が仕事をしない原因として、モチベーションが極端に低い可能性も考えられます。株式会社ネクストレベルの調査でも、困った部下の特徴として、33.7%が「やる気・意欲がない」と回答しています。
過去に実施された多数の研究により、「従業員のモチベーションと仕事のパフォーマンスには強い関連性がある」ことがわかっています。たとえば、ギャラップ社の調査結果によると、「意欲的な従業員はそうでない者と比べ、生産性が14%も高い」というデータが出ています。モチベーションが高いほど会社への愛着も強く、「会社のために貢献したい」という意欲が高まるのでしょう。
逆に、やる気のない部下は会社のために尽くそうという意欲が弱く、少しでも面倒だと感じた仕事は避けてしまうのかもしれません。
個々のモチベーション低下は、業務量の偏りや公正感、心理的安全性など“組織の前提条件”に起因することも多いです。まずは現場の温度感を短時間で定点観測してみましょう。
指示がないと動かない
部下が「指示された仕事しかしない」ことにいら立つ人も多いでしょう。株式会社ネクストレベルの調査でも、困った部下の特徴として、33.7%が「指示待ち・受動的」を挙げています。
もちろん、新入社員のようにまだほとんど仕事を覚えていない場合は、指示待ちになっても仕方がありません。しかし、ある程度経験を重ねているはずなのに、指示がないと動かない部下の心理としては、主に以下の2パターンが考えられます。
- モチベーションが低く、言われたこと以外はやりたくない
- 失敗を極端に恐れ、指示されたことしかできない
前者は部下のモチベーションを高めることで、後者は失敗に寛容な文化を築くことで解決できるかもしれません(詳細は後述)。
年下の上司を軽視している
サイボウズ株式会社の調査によると、会社において「直属の上司が年下」であるケースは近年増えており、従業員2,000人以上の大企業ではその割合が30%にも達するといいます。そのような中で、年下の上司を軽視し、仕事の指示を聞き入れない者も少なくないでしょう。
マンパワーグループ株式会社が「年上の部下を持つ管理職」を対象に実施した調査によると、21.3%が「業務上やりにくい」と回答しています。以下は、やりにくいと感じる要因として挙げられた意見です(括弧内は回答者の割合)。
- 年齢への意識が強い(28.2%)
- 過去の実績にとらわれすぎていて、変化できない(24.7%)
- 上司・部下の関係を理解してくれない(20.0%)
- 指示に従ってくれない、反論ばかりする(20.0%)
上記を見ると、年上部下の中には長年働いてきたプライドから、自分よりも経験が浅い年下上司を見下す者がいることがわかります。
今後は年功序列型から成果主義への移行や、定年引き上げに伴うシニア社員の増加などの影響で、「年下上司・年上部下」の関係性はさらに増えると考えられます。そのため、年上部下をうまくマネジメントし、その良さを引き出す能力が上司には必要だといえます。
仕事の能力が低い
部下の態度や人間性に問題がある訳ではないものの、能力が低いために仕事を任せることができないケースもあるでしょう。マンパワーグループ株式会社が管理職を対象に実施した調査でも、9割以上が「部下に仕事を任せられないと感じた経験がある」と答えています。仕事を依頼されなければ、当然部下は何もすることがないため、仕事をしない人間に見られても仕方がありません。
なお、部下の仕事の能力が低い場合、その原因は部下自身だけにあるとは限りません。上司や先輩社員の教育・指導方法に問題があり、うまく力が発揮できていない可能性もあるからです。
仕事ができない部下の能力を引き出す方法について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
参考:
PR TIMES「166人の上司が選んだ「こんな部下は困る!ランキング」発表」
PR TIMES「年下の上司に聞く「年上の部下へのマネジメント」調査」
マンパワーグループ「年上の部下との仕事のやりやすさ、やりにくさの実態とは?」
マンパワーグループ「管理職の9割超が「部下に仕事を任せられない」と感じた経験あり。実践している部下の指導方法とは?」
仕事をしない部下を持つ上司が心がけるべきポイント

職場に仕事をしない部下がいる場合に、上司が心がけるべきポイントを解説します。
明確な期待を示す
先ほども述べたように、与えられた仕事をきちんとしない部下の中には、責任感が欠如している者が多いとされています。ハーバード・ビジネス・レビューに掲載されている記事によると、従業員の責任感を育むためには、まず上司から明確な期待を示すことが重要といいます。人間は期待をかけられれば、その期待に応えようとする可能性が高いからです。
同記事では、期待の内容をより明確にするために、「形容詞を使わず、代わりに名詞と動詞に置き換える」ことを推奨しています。形容詞は人によってイメージや基準が異なるため、部下が努力の方向性を誤ってしまう恐れがあるのです(例:「協働的に行動してほしい」→「マーケティング担当者の評価を確認し、それをあなたの分析に反映させてください」)。
動機付け要因を充実させる
先ほども述べたように、モチベーションが低い部下は主体的に仕事に取り組まない傾向にあります。部下のやる気を高めるための策として、昇給や昇進などを積極的に行っている企業も多いでしょう。しかし、このような報酬が必ずしも部下のモチベーション向上につながるとは限りません。
従業員のモチベーションは、「衛生要因」と「動機付け要因」の2種類の要素によって左右されるといわれています。
- 衛生要因:仕事への不満度を左右する要素(例:給料、福利厚生、労働条件)
- 動機付け要因:仕事の満足度に影響を与える要素(例:仕事のやりがい、成果が認められること)
ハーバード・ビジネス・レビューに掲載されている記事によると、給料や福利厚生などの衛生要因はあくまで仕事の不満を取り除くものであり、これだけでモチベーションが高まるものではないとのことです。したがって、従業員のモチベーションを高め、主体性も育むためには、「衛生要因と動機付け要因の両方を充実させる」ことが重要といえます。
動機付け要因を継続的に高めるには、「何に満足/不満か」「どこに手当てが効くか」をサーベイで可視化→打ち手に直結させる運用が有効です。以下の記事では、設問の作り方について解説しています。
失敗から学ぶ文化を築く
先ほども述べたように、仕事をしない部下の中には失敗することを極度に恐れ、指示待ち人間になっているタイプもいます。そのため、部下が主体的に仕事に取り組めるよう、「失敗から学ぶ職場文化」を築くことが重要です。
ハーバード・ビジネス・レビューに掲載されている記事によると、失敗は以下の3種類に分けられるとされています。
- 不注意などによる「予防できる失敗」(例:重要な会議に遅刻する)
- 想定外の「避けられない失敗」(例:会社で使用しているシステムのエラー)
- 成長につながる「知的な失敗」(例:新商品のモニターを実施したところ、同様の批判が集まった)
上記のうち、「予防できる失敗」は当然避けるべきだが、人間誰しもミスを犯すことはあります。そんなときは、上司は部下に対して「将来に向けた質問」をすべきだといいます。
たとえば、部下の準備不足が原因で、取引先との契約が成立しなかったと仮定しましょう。このとき、「どうしてちゃんと準備しなかったんだ?」など、過去を問う質問をしてしまうと、部下は自身の失態を上司から責められているように感じる恐れがあります。
一方、「次に同じような商談があったらどうする?」など、未来に焦点を当てた質問をした場合は、部下は二度と同じ失敗をくり返さないよう、上司と建設的な話し合いができる可能性が高いです。こうすることで、上司と部下が関係性を悪化させることなく、失敗から学ぼうとする職場文化も形成されると期待できます。
ベテラン社員の良さを引き出す
ベテラン社員は業務の経験や知識が豊富なため、何かしら問題に直面した際は頼りになることが多いです。また、若手社員の教育・指導役を買って出てくれる場合もあるでしょう。そのため、部下の中に年上のベテラン社員がいる場合は、彼らの良さをうまく引き出すことが重要です。
ただし、中には年下上司のことを軽視し、言うことを聞いてくれない者もいるかもしれません。ハーバード・ビジネス・レビューに掲載されている記事によると、年上の部下を効果的にマネジメントするためには、以下のポイントを意識することが大切といいます。
- 自信を持つ:年上を敬いつつも自信を持って接することで、相手の信頼も得られる
- 意見を求める:自分の意見はきちんと持った上で、相手の意見にも耳を傾けて議論を進める
- 学ぶ姿勢を見せる:積極的に周囲からのフィードバックを求めて、常に改善しようとする姿勢を示す
年上部下のマネジメント方法について詳細を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
指示を聞かない場合は処分を検討する
部下が正当な理由なく仕事をしないのは「業務命令違反」に該当し、処分の対象になる可能性があります。とはいえ、仕事を一度拒否した程度で解雇するのは「不当解雇」とみなされる恐れがあるため、状況に応じた処分方法を検討することが重要です。
咲くやこの花法律事務所の見解によると、問題社員に対しては以下の手順で対処するのが適切といいます。
- 改善のための指導を行う
- 改善が見られない場合は軽い処分から順に科す(戒告・けん責/言及/出勤停止/降格)
- なお改善が見込めない場合は退職勧奨を行う
- 退職勧奨でも解決しない場合は解雇を検討する
業務命令に従わない部下の対処方法に迷う場合は、上長や専門家に相談するのも一つの手です。
▼仕事をしない部下の解雇が認められた事例
| Y社は、業務に対する積極性に欠け、自分が得意な仕事以外は引き受けないX職員に対し、入社当初からくり返し指導し、改善を求めていた。しかし、Xに改善しようとする姿勢がまったく見られなかったことから、就業規則の解雇事由にあたるとし、Y社はXを解雇。Xは解雇の無効を主張し、雇用契約上の地位確認と解雇後の賃金支払を求めた。裁判所は、Y社がXに対して基本的かつ根本的な仕事に対する姿勢の問題を長年にわたって指摘していたにもかかわらず、Xが自己の問題を理解し改善しなかったと認定した。さらに、Y社がPIP(パフォーマンス改善計画)を実施し、改善指示を出していたことも考慮し、本件解雇には客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当であると判断。Xの請求は棄却された。 |
参考:
DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー「責任感と思いやりが調和したチームをいかに構築すべきか」
DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー「モチベーションとは何か:社員の自発性を高める」
DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー「失敗に学ぶ経営」
DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー「部下がミスを犯したら、上司はどんな言葉をかけるべきか」
Harvard Business Review “Leading Older Employees”
Harvard Business Review “When You’re Younger Than the People You Manage”
咲くやこの花法律事務所「問題社員など辞めさせたい社員がいる場合の正しい解決方法」
仕事をしない部下から逆パワハラを受けたときの対処法

部下が指示された仕事をしないだけでなく、上司に対して攻撃的な言動をとる場合は、「逆パワハラ」に該当する可能性があります。
上司も1人の人間であり、部下から逆パワハラを受ければ傷つくはずです。過去には実際に、部下の逆パワハラによって精神的に病み、自殺に追い込まれた事例もあります。もし、部下に逆パワハラが疑われる言動が見られる場合は、被害が大きくなる前に対処しましょう。
厚生労働省では、以下の3つの要素を満たす言動をパワーハラスメントと定義づけており、部下から上司への行為もこれに含まれます。
- 優越的な関係に基づいて行われる行為
- 業務の適正な範囲を超えて行われる行為
- 身体的若しくは精神的な苦痛を与える、または就業環境を害する行為
▼具体例:逆パワハラになりうるケース
- 運営上重要な業務知識・スキルを有している部下が、上司の指示を無視する
- 上司に対し暴言を吐いたり、暴力をふるったりする
- 注意・指導を行う上司に対して「パワハラだ」と脅す
また、Authense法律事務所によると、部下から逆パワハラを受けた場合は、以下のように対応するのが適切といいます。
- 毅然とした態度で注意・指導を行う
- 注意・指導した記録を残しておく(懲戒処分を科す際の証拠となる)
- 注意・指導しても改善が見られない場合は、上長や専門の窓口に相談する
参考:
弁護士法人Authense法律事務所「逆パワハラとは?上司が取るべき対応を弁護士がわかりやすく解説」
まとめ
仕事をしない部下の特徴や対処法について解説しました。
部下が仕事をしないときはさまざまな原因が考えられ、上司の心配り次第で大きく改善できる可能性があります。ただし、中にはいくら注意・指導しても態度を改めない者もいるため、その場合は適切に処置することが重要です。
本記事で紹介したポイントをふまえ、部下が前向きに仕事に取り組める職場づくりを目指してください。

