ゆとり世代とさとり世代は、デジタルネイティブであり、現代社会を担う重要な人材です。しかし、それぞれの世代の特徴を理解した育成やマネジメントを行わなければ、ゆとり世代やさとり世代の能力を最大限に引き出すことはできません。
本記事では、ゆとり世代とさとり世代の違いをわかりやすく解説し、それぞれの世代に適した育成ポイントを紹介します。
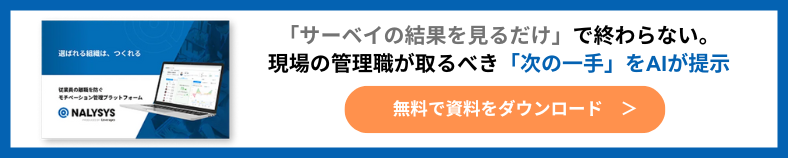
ゆとり世代とさとり世代の違いとは
ゆとり世代とさとり世代の違いについて、厚生労働省の経済社会の推移と世代ごとにみた働き方を参考に解説します。ゆとり世代とさとり世代には明確な定義がないため、本記事では、ゆとり世代を1987年〜2004年生まれ、さとり世代を1996年〜2005年生まれとします。
ゆとり世代
2002年から実施された「ゆとり教育」の影響を受けた最初の世代です。ゆとり教育の影響を大きく受けたことが、ゆとり世代と呼ばれる由来になったとされています。ゆとり世代は、バブル崩壊後の経済低迷期に幼少期を過ごし、デフレや不況が当たり前の時代に育った世代です。
ゆとり世代は、それまでの詰め込み型の教育ではなく、個々のペースに合わせて教育を行うゆとり教育の影響で学習内容が削減され、授業時間が減り、思考力や自主性を重視した教育を受けました。
また、インターネットや携帯電話が普及する中で育ち、デジタルデバイスに触れる機会も多かったため、デジタル機器の扱いに慣れているITリテラシーが高い世代といえます。
さとり世代
さとり世代は、ゆとり世代と同じ時代を過ごしたこともあり、ゆとり世代と同様に不況やデフレの時代に育ちました。さとり世代は、約10年間続いた「ゆとり教育」が見直され、「脱ゆとり教育」を受けた世代です。
さとり世代は、物欲が少なく、消費に対しては非常に合理的で、必要なものだけを必要な分だけ購入する傾向があることから、まるで「悟りを開いている」かのような世代であるとして、インターネットを通じて「さとり世代」という呼び名が広まったとされています。
さとり世代は、パソコンや携帯電話、インターネットが普及した環境で育ったデジタルネイティブ世代です。ITリテラシーが高く、デジタル機器を使いこなすことに長けている傾向があります。
ゆとり世代とさとり世代の違い
ゆとり世代とさとり世代は重なる部分も多いですが、育った時代背景や教育環境によって、以下のような違いが見られます。
さとり世代は、ゆとり世代よりも社会の厳しい現実を目の当たりにしてきたため、将来への危機感が強い傾向にあります。そのため、さとり世代は物欲が少なく、安定した生活を求める傾向が強いです。また、さとり世代は、安定した生活のために、必要であれば能動的に学習するといった特徴もあります。
ゆとり世代は、さとり世代に比べて危機感が薄くで、競争を強いられず個性を育む教育を受けたことから、学習意欲も低い傾向にあります。さとり世代は、ゆとり世代よりもさらに現実的で、堅実な生き方を重視していると言えます。
ゆとり世代は、さとり世代ほど将来への危機感は強くなく、心に余裕がある一方で、物事に意欲的に取り組むことや競争に弱いといった特徴があります。
ゆとり世代とさとり世代の具体的な年齢
ゆとり世代の具体的な年齢は、2024年時点で37歳〜19歳、さとり世代は、28歳〜18歳となります。
先述のとおり、ゆとり世代とさとり世代の明確な定義はなく、上記の年齢は本記事が定めたゆとり世代を1987年〜2004年生まれ、さとり世代を1996年〜2005年生まれの年齢です。
ゆとり世代とさとり世代の仕事への考え方

ゆとり世代とさとり世代の仕事観について解説します。
ゆとり世代の仕事への考え方
ゆとり世代の仕事への考え方について、リクルート・マネジメント・ソリューションズが公開した2012年新入社員意識調査 ゆとり世代の新入社員は何を求めているのか?を参考に解説します。
ゆとり世代は、バブル崩壊後の経済低迷期に育ち、競争より協調を重んじる教育を受けました。そのため、仕事においても良好な人間関係を築くことを重視し、周囲と助け合いながら働きたいと考えています。
また、ゆとり教育で個性を尊重されてきたため、職場でも個性を認め、受け入れてほしいと願っています。単に温かい雰囲気だけでなく、それぞれの個性を尊重し、自由に意見を言い合える風通しの良い職場環境を求めているのです。
仕事への意欲は高く、高い成果を出したいと考えていますが、同時にスマートに成果をあげたいという意識も持っています。目立たず、効率的に仕事を進め、成果を上げることを理想としています。
そのため、上司には、適切な距離感で的確な指導をしてくれることを期待しています。過干渉ではなく、困ったときに相談でき、的確なアドバイスを受けられる関係を望んでいるでしょう。
さとり世代の仕事への考え方
ゆとり世代とさとり世代の仕事観について解説します。さとり世代は、バブル崩壊後の不況やリーマンショック、東日本大震災など、経済的・社会的に不安定な状況を目の当たりにして育ってきました。
そのため、仕事に対しては「安定」と「堅実さ」を求める傾向が強いです。具体的には、以下のような点が挙げられます。
- 長期的な雇用が見込める企業や安定した収入を得られる職種を志望している
- ワークライフバランスを重視している
- 精神的な負担が少なく穏やかな職場環境を求めている
- 仕事にやりがいを感じ自分の成長につなげたい
- 過度な競争やプレッシャーは避けたい
さとり世代は人生において、必ずしも仕事が第一ではなく、人生における幸福や充実感を重視しています。そのため、仕事はあくまで人生の一部であり、プライベートの時間も大切にしたいと考えているのです。
また、デジタルネイティブ世代であるため、ITスキルを活用した効率的な働き方を好み、無駄な残業や非効率な作業を嫌います。そのため、企業側も、さとり世代の価値観を理解し、対応できる範囲で、働きやすい環境を整備することが重要となるでしょう。
ゆとり世代とさとり世代の育成ポイント

どちらの世代も、コミュニケーション能力の育成は共通の課題として挙げられています。企業は、世代ごとの特性を理解した上で、それぞれの長所を伸ばし、短所を補うような育成プランを設計することが重要です。
厚生労働省の「平成23年版 労働経済の分析」を参考に、ゆとり世代とさとり世代の育成ポイントを解説します。
ゆとり世代
ゆとり世代は個性を重視する一方、主体性やチャレンジ精神が不足しがちと言われます。育成の鍵は、長所を伸ばし短所を補うアプローチです。
まず、個性を尊重し、多様な意見を活かせる環境づくりが重要です。得意分野に合わせた役割分担や、自由な意見交換ができる雰囲気は、彼らのモチベーションを高められます。
また、主体性を育むには、目標達成プロセスを明確化し、こまめなフィードバックを実施しましょう。ゆとり世代に小さな成功体験を積み重ねさせることで、自信と責任感を育むことができます。
さらに、チャレンジ精神を養うには、失敗を恐れず挑戦できる環境づくりが不可欠です。心理的安全性を確保し、新しい試みを奨励することで、成長を促します。
コミュニケーションは具体的かつ論理的に行い、精神論は避けましょう。また、キャリア支援として、長期的なキャリアプランを一緒に考える機会を提供することも効果的です。
さとり世代
さとり世代は安定志向で堅実な反面、コミュニケーションやストレス耐性に課題を抱えているため、育成には「安心」と「成長促進」のバランスが重要です。
安心できる環境づくりとして、長期的なキャリアパスや安定した雇用環境を整えましょう。加えて、公正で透明性の高い評価基準を設けることで、納得感とモチベーションを維持します。
さらに、コミュニケーション能力向上のため、チームワークや人間関係構築の研修を実施すると良いでしょう。ストレス耐性向上のため、ストレスマネジメントやメンタルヘルス研修の実施も、メンタルを安定させながら仕事に取り組む上で効果的です。
成長促進においては、時間をかけて小さな成功体験を積み重ねる段階的なアプローチが効果的です。ワークライフバランスを重視した制度や職場風土も、長期就業を促進する上で重要です。
これらの取り組みを通じて、さとり世代の強みを活かしつつ、弱点を補うことで、企業にとって貴重な人材へと育成できるでしょう。
まとめ
ゆとり世代とさとり世代は、どちらもデジタルネイティブ世代ですが、育った時代背景や教育環境の違いから、仕事への価値観や考え方に違いがあります。ゆとり世代は、ゆとり教育の影響で個性重視ですが、主体性やチャレンジ精神に欠ける傾向があります。
一方、さとり世代は、脱ゆとり教育を受け、安定志向で堅実ですが、コミュニケーション能力やストレス耐性に課題があります。育成においては、ゆとり世代には個性を尊重しつつ、主体性やチャレンジ精神を養うことが、さとり世代には安心できる環境を提供しつつ、成長を促すことが重要です。
どちらの世代にも共通する課題として、コミュニケーション能力の向上があります。企業は、これらの世代の特徴を理解し、適切な育成プランを設計することで、ゆとり世代やさとり世代を会社の戦力となる社員として育成することができるでしょう。

