現在、会社で管理職を務めている人の中には、「自分は管理職の器じゃない気がする…」と悩む人も多いでしょう。
管理職は一般社員よりも幅広い能力が求められるため、不向きな人がいるのも当然といえます。しかし、管理職としての自らの課題や問題点を理解し、適切な改善策を講じることができれば、多くの人は優れた管理職になれるはずです。
本記事では、管理職に向いていない人の特徴や、不向きだと感じたときの対処法を解説します。部下から尊敬・信頼される管理職になり、職場の生産性や人間関係の向上を目指す方は、ぜひ参考にしてください。
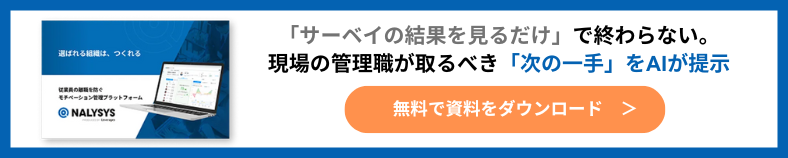
「自分は管理職の器じゃない」と感じる人は多い

現在会社で管理職を務めているものの、「自分は管理職の器じゃない」と悩む人は多いはずです。
実際に、株式会社ビズヒッツが管理職経験者を対象に実施した調査でも、「自分が中間管理職に向いていると思いますか」との問いに、64.7%が「向いていない」と回答しています。以下は、その理由として挙げられた主な意見です。
- 上層部と部下の板挟みになるのが辛い
- 一人で黙々と仕事をしたい
- 性格的に向いていない(他人に嫌われたくない、人に厳しくできないなど)
人はそれぞれ能力や性格が異なるため、不向きな人がいるのは当然といえます。しかし、「自分は管理職に向いていない」と決めつけてしまうと、それは課題から目を背ける言い訳になってしまうかもしれません。
自分の管理職としての課題や問題点を理解しつつ、より優れた管理職になるためにはどうすべきかを考え、改善策を講じることが大切です。
参考:
PR TIMES「【中間管理職がつらいと思う瞬間ランキング】238人アンケート調査」
管理職の器じゃない人の特徴

管理職に不向きな人によく見られる特徴を紹介します。
権力に溺れやすい
管理職になったことで、思考や行動が悪い意味で変化する「権力に溺れやすい」人は、管理職に不向きといえます。
以下は、権力に溺れている人がとりがちな行動の例です。
- 部下に高圧的な態度をとる
- 部下に非現実的な目標を課す
ハーバード・ビジネス・レビューの記事によると、人の脳は自らが「権力を持っている」と感じたとき、お金や報酬を得たときと同様の快感が得られる仕組みになっているといいます。
そして、権力に溺れる者はより大きな快感を得るために、さらに権力を振りかざすようになるとのことです。このような状態に陥ると、管理職と部下の関係性は悪化し、やがて職場全体の士気や生産性が低下することにつながるでしょう。
管理職が権力に溺れるのを防ぐには、上記のような脳の性質を理解し、部下の視点を忘れず持ち続けることが大切です。
たとえば、新規プロジェクトのスケジュールを設定する際は、独断で決めるのではなく、各メンバーとすり合わせながら決めるべきだといえます。
部下を注意・指導できない
部下に対して言いたいことを言えない人は、管理職に不向きといえます。部下が仕事上で何かしら問題を起こした際に、注意・指導することも管理職の重要な務めだからです。
仮に、定時に遅刻して出社してきた部下に対して、管理職が一切注意しなければどうなるでしょうか。遅刻した部下は自身の行動を反省することなく、また同じ過ちをくり返す恐れがあります。また、周囲の社員からは「あの人は管理職なのに、部下の遅刻さえ注意できない」と失望されるかもしれません。
管理職が部下に強くものを言えない主な原因として、「部下に嫌われたくない」という心理が考えられます。
しかし、米国で行われた研究によると、従業員の72%は「管理職からの批判的なフィードバックが自らのキャリア開発において重要だ」と考えているといいます。
また、率直なフィードバックを与える能力が高い管理職のもとでは、エンゲージメント(会社への愛着度を表す指標)も高くなる傾向があるという結果も出ています。
これらの結果からも、管理職が部下を厳しく注意・指導する重要性が見て取れます。ただし、業務上必要な範囲を超えた指導(例えば、長時間拘束して説教する、暴力をふるうなど)は、パワハラになる恐れがあるため注意が必要です。
目先の利益ばかり追い求める
目先の利益ばかり追い求める人は、管理職に向いていない可能性が高いです。
あらゆる業界において、市場は常に変動し続けるものです。企業が競争力を維持するためには、中長期的な視点でトレンドやニーズの変化を予測し、適切に対応することが求められます。
逆に、短期的な視点しか持たない管理職のもとでは市場の変化に対応できず、組織として成長できずに取り残される恐れがあります。
ただし、中長期的な視点で物事を考える能力は訓練によって鍛えることができるため、現時点ではその能力が欠けていても大きな問題ではありません。
ハーバード・ビジネス・レビューの記事では、その訓練方法として、「3~6ヶ月後にチームをどこに導きたいか」について考える時間を毎月確保することを推奨しています。そして、そこから逆算し、目標を達成するために今何をすべきかを考えるのです。
このような訓練を実践することで、常に未来について考え、未来を予測する習慣が身につくといいます。
部下に仕事を任せられない
部下に仕事を任せることができない人は、管理職に不向きだといえます。
ハーバード・ビジネス・レビューの記事によると、管理職が部下に仕事を割り振ることで、以下のようなメリットが得られるとされています。
- 部下の成長が促進される:さまざまな業務を経験することで幅広い知識やスキルが身につき、問題解決能力も向上する(例:若手社員に定例会議の進行をさせる)
- 自分自身のスケジュールに余裕ができる:自分にしかできない重要なタスクに十分な時間を割ける(例:部下の業績評価、新規プロジェクトの発案など)
一方で、仕事を一人で抱え込むタイプの人が管理職になると、自身の負担が大きくなるだけでなく、部下の能力も向上せず、結果的に組織全体の成長が停滞する恐れがあります。
もちろん、部下に仕事を丸投げし、一切フォローもせず放置することは避けるべきです。しかし、部下に仕事を適切に割り振り、その都度成長を促すことも管理職の非常に重要な役割といえるでしょう。
常に完璧を求めている
ハーバード・ビジネス・レビューの記事によると、常に完璧であることを求める「完璧主義者」が管理職になると、さまざまな弊害が生じる恐れがあるとされています。
同記事では、完璧主義者を主に以下の3タイプに分類しています。
- 自己中心型:「自分自身が完璧であること」を重要な信念として持っているタイプ。自らが理想とする水準に達しないと、過度に自分を責める傾向にある
- 社会規定型:「周囲が自分に完璧さを求めている」と誤解するタイプ。部下から尊敬され、受け入れられるためには、周囲が課す基準を完璧に満たすことが条件だと考えがち
- 他者志向型:「他者が完璧であること」を重視するタイプ。部下に対して最高のパフォーマンスを求め、基準に達しない場合は厳しく評価する傾向にある
上記のうち、「自己中心型」および「社会規定型」の完璧主義者は、自分自身に過度なプレッシャーをかけることで、燃え尽き症候群や精神疾患を患いやすいとされています。
また、「他者志向型」の完璧主義者は、部下が自分の期待に応えられなかった場合に、過剰に不安を煽ったり怒りを示したりし、良好な人間関係を築けないことが多いです。
いずれのタイプにしても、完璧主義者は仕事上で何かしら問題やトラブルを引き起こす可能性が高く、管理職には不向きといえます。
そもそも、仕事上においては正解のない問題が多く、完璧であることは難しいため、ある程度のラインで妥協することも管理職として大切です。
参考:
DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー「優れたリーダーになることを妨げる脳の3つの性質」
DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー「部下への厳しいフィードバックを恐れてはならない」
DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー「仕事を任せられないリーダーは、ステップアップできない」
DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー「完璧主義が仕事にもたらす負の影響に気づいているか」
「自分は管理職の器じゃない」と感じたときの対処法

「自分は管理職の器じゃない」と感じたときに、管理職がとるべき対処法を紹介します。
自己認識力を高める
優れた管理職として部下から尊敬・信頼されるためには、「自己認識力」を高めることが重要です。自己認識力とは、自分自身の思考や価値観、感情などを正しく理解する能力を指します。
ハーバード・ビジネス・レビューの記事によると、自己認識力が高いリーダーは判断力やコミュニケーション力に優れ、部下との関係も良好であるという研究結果が示されています。
なお、自己認識力は大きく以下の2種類に分けられるとされています。
- 内面的自己認識:自分自身のことを自分で正確に理解する能力
- 外面的自己認識:自分が他人にどう見られているかを正確に理解する能力
「内面的自己認識」および「外面的自己認識」は、どちらか一方だけが優れていても効果は十分ではありません。
たとえば、内面的自己認識が優れていても外面的自己認識が欠けていれば、他者の視点に立つことができず、良好な人間関係を築くことが難しいでしょう。
逆に、内面的自己認識が不足している場合は、周囲の目を気にしすぎて自分にとって重要な選択ができなくなる恐れがあります。
一方で、内面的自己認識と外面的自己認識の両方がバランスよく優れていると、自他双方に満足のいく行動をとりやすくなります。
以上のことから、管理職として成功するためには、内面的自己認識と外面的自己認識の両方をバランスよく向上させることが不可欠です。
▼【具体例】自己認識力を高める訓練方法
| ・「管理職の業務に関して、自分にプレッシャーを感じさせる要因は何だろうか」と自問自答する(内面的自己認識のトレーニング) ・複数人の部下に対し、「あなたたちとより質の高いコミュニケーションを取るために、私がすべきことを1つ教えてください」と尋ねる(外面的自己認識のトレーニング) |
弱みをさらけ出す
管理職としての自分の能力に問題があると感じている場合は、あえて自らの弱みをさらけ出すことも有効なアプローチかもしれません。
ありのままの自分を部下に見せることで、部下も虚勢や見栄を張る必要がなくなり、オープンで信頼できる関係を築きやすくなるためです。
実際に、世界的な大企業であるマイクロソフトやスターバックスのCEOは、自分の課題や短所を従業員に包み隠さず示すことで、企業文化に変革をもたらし、結果的に業績も大きく向上させたといわれています。
ハーバード・ビジネス・レビューの記事によると、管理職が部下に対して自分らしさをさらけ出すためには、以下のポイントを意識することが効果的です。
| ポイント | 具体例 |
|---|---|
| 知らないことは素直に「知らない」と伝える | 部下から質問された際に、「その点については私も詳しくないので、一緒に調べましょう」と伝える |
| 困ったときは周囲に助けを求める | 一人で対応しきれない締め切り間近の仕事について、「このタスクに手が回っていません。Aさん、手伝ってくれませんか?」と声をかける |
| ミスや間違いを犯したら、自分の非を認めて謝罪する | プロジェクトのスケジュールに遅れが発生した際に、「私の見積もりが甘かったです。申し訳ありません」と素直に謝罪する |
| 自分の課題や欠点を周囲と共有する | 新しいツールの使い方について、「このツールの使い方にはまだ慣れていません。今後勉強して、使用方法をマスターします」と共有する |
参考:
DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー「リーダーに不可欠な「自己認識力」を高める3つの視点」
DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー「リーダーに必要なのは虚勢ではなく弱さを見せる勇気」
まとめ
管理職に向いていない人の特徴や、不向きだと感じたときの対処法について解説しました。
「自分は管理職の器じゃない」と感じている人は、まずは具体的にどのような能力が自分に欠けているのかを理解した上で、適切な改善策を講じることが重要です。
本記事で紹介したポイントをふまえて、部下から尊敬・信頼される管理職になり、職場の生産性や人間関係の向上を目指してください。

