以前とは異なる部下の行動が、部下に嫌われているサインかもしれないと悩んでいる管理職の方もいるでしょう。部下に嫌われると、部下のモチベーションや生産性が低下し、最悪の場合、離職につながるケースも考えられるため、早期に対応することが大切です。
本記事では、部下に嫌われているサインや嫌われる上司の特徴について解説します。また、優れた上司になるための考え方についても解説するので、参考にしてください。
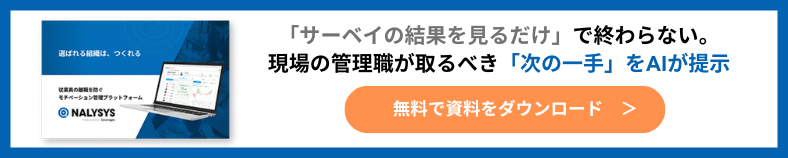
部下に嫌われているサイン

部下に嫌われているサインについて、フォーブスが公開するリーダーシップコーチであるエリカ・アンダーセン氏による記事を参考に解説します。
会話が止まる
上司が部屋に入ると会話が止まる場合、部下が上司を恐れているか、上司に対してネガティブな感情を抱いている可能性があります。上司が近づくと部下たちの会話が途切れ、目を合わせようとしなかったり、そそくさと席を立ったりする場合は、部下から避けられている可能性が高いです。
このような状況は、上司と部下の信頼関係が築けていないことを示しており、改善が必要といえるでしょう。
過剰に媚びる
多くの部下が、上司に過剰に媚びへつらうのは、上司への信頼ではなく、保身のためである可能性が高いです。実際に尊敬や信頼に基づいた関係であれば、部下は率直な意見やフィードバックを共有できます。
しかし、媚びへつらいが横行する環境では本音が言えず、上司は、正確な情報を知ることができないでしょう。上司の意見に常に賛同し、過剰に媚びている部下が多い場合、部下は上司を恐れていたり、ご機嫌取りをしている可能性があります。
このような状況は、健全なコミュニケーションを阻害し、チームの生産性を低下させる要因となります。
部下が発言しない
部下が会議などで発言しない場合、上司へ恐怖や不信感を持っている可能性があります。上司が部下の意見を尊重し、安心して発言できる場を提供していれば、部下は自信を持って発言することができるでしょう。
さらに、上司が意見を求めても部下が無言で、反応がない状態が続く場合、発言することへの不安や、無関心を感じている可能性があります。部下が発言しないことは、チームの創造性や問題解決能力を阻害し、部下の主体性を育むことが難しくなってしまいます。
問題を報告しない
問題が発生しても報告が上がってこない場合、部下が上司に報告することへの恐怖を感じている可能性があります。問題を報告しない部下は、問題を報告することで上司から叱責を受けたり、責任を問われたりするのではないかと恐れていると考えられます
部下が上司に早期に問題を共有することができなければ、問題は隠蔽され、状況が悪化するまで表面化しないでしょう。問題を報告しないケースが増えている場合、組織全体に深刻な影響を与える可能性があり、迅速な対応が必要となります。
参考:
上司が部下に嫌われる原因

部下に嫌われる上司の特徴について、フォーブスが公開するリーダーシップ・アドバイザーであるデデ・ヘンリー氏による記事を参考に解説します。
部下を見下している
部下を見下す上司は、皮肉を言ったり、軽蔑的な態度で接し、部下の努力や貢献を認めないでしょう。このような態度は、部下のモチベーションを著しく低下させ、他の社員へ悪影響を与え、職場環境を悪化させます。
部下の意見を嘲笑したり、能力を過小評価する発言は、典型的な見下す行動です。上司は、部下を尊重し、努力や貢献を適切に評価しなければいけません。
感情的になりやすい
感情的な上司は、怒りや不満を爆発させ、部下を萎縮させます。厚生労働省の職場におけるハラスメント対策パンフレットには、脅迫や名誉棄損、侮辱、ひどい暴言などは、パワハラに該当する場合があるとされています。
些細なミスで部下を大声で叱責したり、物に当たるなどの行動は、感情的な上司の特徴です。このような上司の下では、部下は安心して仕事に取り組めません。
上司は、感情をコントロールし、冷静かつ理性的に行動しなければいけません。
マイクロマネジメントをする
マイクロマネジメントをする上司は、部下の仕事に過剰に介入し、自主性を奪います。部下は、常に監視され、指示されることで、モチベーションを失い、創造性を発揮できなくなるでしょう。
マイクロマネジメントは、部下の能力を活かせない非効率な管理手法とされています。部下の作業手順を細かく指示したり、常に進捗状況を確認するのは、マイクロマネジメントの典型例です。
このような上司の下では、部下は指示待ち人間になりがちです。指示待ちの部下について、より詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
上司は、部下に適切な権限を与え、自主性を尊重する必要があるでしょう。
手柄を横取りする
部下の功績を自分のものにしてしまう上司も部下から嫌われてしまうでしょう。手柄を横取りする上司は、部下のアイデアを横取りし、自分のアイデアとして発表します。また、チームの成功を自分の功績だと主張し、部下の貢献を軽視し、評価しない傾向があります。
手柄を横取りする上司は、部下からの信頼を失い、チームの士気を低下させ、最終的には組織全体の生産性にも悪影響を与えます。
些細なことに固執する
些細なことに固執する上司は、目標を見失うだけでなく、部下の時間を無駄にします。些細なミスやルールにこだわりすぎることで、部下は、本来の重要な業務に集中できなくなり、生産性が低下します。
たとえば、報告書の誤字脱字に過剰に反応したり、細かい規則に厳格すぎるのは、些細なことに固執する上司の特徴です。このような上司は、部下のモチベーションを低下させ、ストレスを増大させます。
上司は、重要な目標に焦点を当て、些細なことは許容する柔軟性を持つ必要があるでしょう。
参考:
上司が部下に嫌われるデメリット

上司が部下に嫌われるデメリットについて、ハーバードビジネスレビューが公開するペンシルバニア大学ウォートン校の経営コミュニケーションの講師であるデボラ・グレイソン・リーゲル氏らによる記事を参考に解説します。
信頼関係が崩れる
上司が部下から嫌われると、相互の信頼関係が崩れる可能性があります。上司が部下から嫌われている状態では、指示が適切に伝わらず、部下からの報告も滞ります。上司を嫌うようになった部下は、上司からの指示を素直に受け取らず、指示の裏にある意図を深読みしたり、誤解したりする可能性があるでしょう。
さらに、上司が嫌いになった部下は、感情を爆発させるおそれがあり、職場の友好的な雰囲気が損なわれる可能性があります。上司が部下に嫌われることで風通しの悪い職場環境が生まれ、他の社員にも悪影響が及ぶことも考えられます。
生産性が低下する
上司が部下から嫌われると、部下やその他の社員の生産性が低下します。上司との関係が悪いために、モチベーションが低下した部下は、仕事への意欲を失い、パフォーマンスが低下します。
生産性が低下した部下は、指示された業務を必要最低限しか行わなくなったり、新しいアイデアを出さなくなったりします。また、協力体制も崩れ、部署全体のチームワークが悪化することで、全体の生産性も低下する可能性があります。
離職が増える
上司が部下から嫌われると、離職が増える恐れがあります。嫌な上司の下で働き続けたい人は少なく、働きやすい環境を求めて、優秀な人材が流出する可能性が高まります。上司との関係が悪化した部下は、転職活動を始めたり、退職を検討したりするようになるでしょう。
関係の良くない上司からはフィードバックを得られず、成長機会を失った部下は離職を選びます。株式会社アシロの20〜50歳の現役世代に聞いた上司とのコミュニケーションの実態によると、全体の6割以上が上司を理由に、会社を辞めたいと思ったことがあると回答しています。
出典:株式会社アシロ|20~50歳の現役世代に聞いた上司とのコミュニケーションの実態
尊敬できない、あるいは信頼できない上司の下では、部下のモチベーションは低下します。仕事への意欲が削がれ、パフォーマンスも低下する悪循環に陥ります。成長意欲のある部下であれば、より良い環境を求めて転職を考えるようになるでしょう。
参考:
優れた上司になるための考え方

優れた上司になるための考え方について、ハーバード・ビジネス・レビューに掲載されたハーバード・ビジネス・スクール 教授であるリンダ A. ヒル氏らによる記事を参考に解説します。
自ら模範を示す
優れた上司は、部下にとってのロールモデルとなるべく、自ら模範的な行動を示すことが大切です。部下は上司の行動や言動をよく観察し、模倣する傾向があります。上司が模範的な行動を示すことで、部下は具体的な行動指針を理解し、実践しやすくなります。
また、尊敬できる上司の行動を参考にすることで、部下のモチベーション向上や主体性の育成にもつながります。たとえば、担当業務に責任感を持って取り組み、最後までやり遂げる姿勢を見せたり、困難な課題にも積極的に挑戦し、粘り強く取り組む姿勢を示したりといった行動を心掛けましょう。
また、部下や同僚、顧客など、周囲の人すべてに敬意を払い、丁寧に接する姿勢や部下の意見や悩みに真摯に耳を傾け、共感することも大切です。上司が率先して模範を示すことで、部下は具体的な行動を学び、成長を加速させることができます。
成長を怠らない
優れた上司であり続けるためには、知識やスキルの向上に日々努力し、成長し続けることが不可欠です。ビジネス環境は常に変化しており、上司に求められるスキルや知識も変化し続けています。常に学び続けることで、変化に対応し、部下を適切に指導することが可能になります。
成長を怠らない上司の行動の例は以下になります。
- 自己分析……自分の強みと弱みを分析し、成長領域を明確にする
- 継続的な学習:…ビジネス書やセミナーなどで、新しい知識やスキルを学ぶ
- フィードバック:…部下や同僚からのフィードバックを受け止め、改善に繋げる
- 新しい手法の実践:…学んだマネジメント手法を積極的に実践し、効果を検証する
- 成功・失敗体験の振り返り…成功・失敗体験を分析し、次なる行動に活かす
成長を怠らないことは、優れた上司であり続け、変化の激しいビジネス環境の中で部下を導き、組織の成長に貢献することにつながります。
部下を育成する責任を持つ
優れた上司は、部下の育成を自らの責任と捉え、積極的に育成に取り組みます。優れた上司と普通の上司の最大の違いは、部下の成長を真剣に考え、個別にサポートやフォローを行うかどうかです。
単に業務を指示するだけでなく、部下の成長をサポートすることで、部下は能力を高め、組織への貢献度を高めるでしょう。部下育成の責任を持つ上司は、部下と定期的に面談を行い、キャリア目標やスキルアップ目標の設定をサポートしたり、部下の業務成果や行動に対して、具体的で建設的なフィードバックを提供したりします。
また、部下が気軽に相談できる雰囲気を作り、困っている時に適切なアドバイスやサポートを提供することも大切です。部下の育成に責任を持つ上司は、部下の成長を促すと同時に、チーム全体の能力向上、ひいては組織全体の業績向上に貢献し、上司自身もマネジメント能力を高め、リーダーとして成長することができます。
参考:
Linda A. Hill.(2013).優れた上司であり続けるための3つの要素.Harverd Business Review.https://dhbr.diamond.jp/articles/-/1945
Sydney Finkelstein.(2018).The Best Leaders Are Great Teachers.Harverd Business Review.https://hbr.org/2018/01/the-best-leaders-are-great-teachers
まとめ
部下に嫌われているサインについて解説しました。上司との関係が上手くいかないと、部下はモチベーションや生産性が低下し、最悪の場合、離職につながる場合もあるため、早期に対応することが大切です。
部下に嫌われているサインについて、心当たりがある場合、部下を感情的に叱責していないか、マイクロマネジメントで部下の主体性を奪っていないか、など自身の行動を振り返ってみましょう。優れた上司は、成長を怠らず、部下の模範となる行動をとり、部下を育成する責任を持つことが大切です。
上司は、部下から信頼され、尊敬されることで、より働きがいのある職場環境を作り出し、組織の活性化に大きく貢献できるでしょう。

