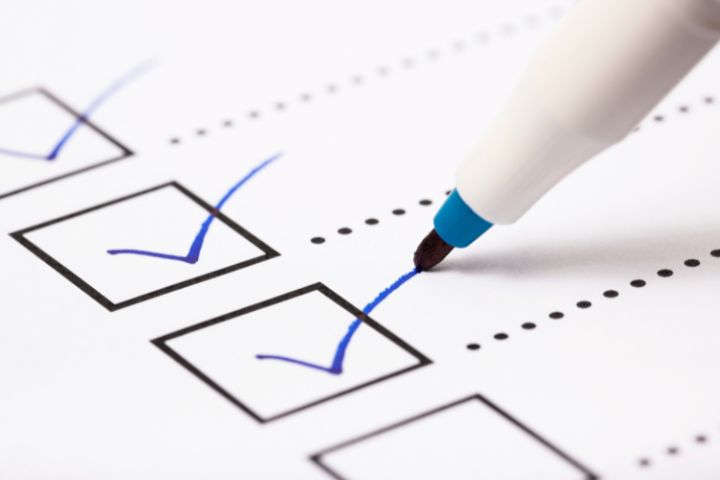リファレンスチェックとは、採用候補者の現職や前職の上司・同僚など第三者から、その人の働きぶりやスキル、人柄について情報を収集する採用手法です。
書類選考や面接だけでは見えにくい「実際の仕事ぶり」を把握し、採用のミスマッチを防ぐために活用されます。近年、国内企業でも導入が進んでおり、応募書類や面接では判断しづらい候補者の能力や人物像を、第三者の視点から確認できる点が大きなメリットとされています。
本記事では、企業の経営者・人事担当者・管理職の方に向けて、リファレンスチェックの重要性やメリット、具体的な実施方法や注意点、さらには国内外の導入事例について詳しく解説します。
リファレンスチェックの重要性
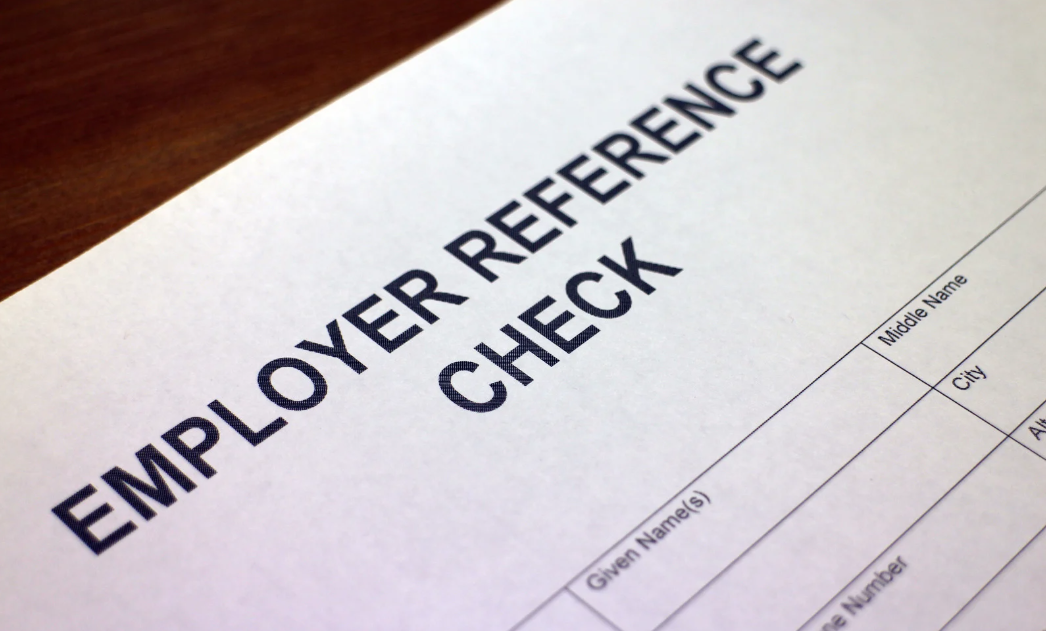
採用のミスマッチは、企業にとって大きな課題です。新卒・中途採用ともに3年以内の離職率が約30%にのぼり、多くの企業が早期退職による影響を受けています。こうしたミスマッチを防ぐために、リファレンスチェックが注目されています。
採用のミスマッチが引き起こす問題
厚生労働省の調査では、新卒採用者の約3割が3年以内に離職すると報告されています。また、中小企業庁の委託調査によると、中途採用者においても約30%が3年以内に退職しているとされています。さらに、マンパワーグループの調査では、人事担当者の8割以上が「新卒採用後にミスマッチを経験した」と回答しています。
採用がうまくいかないと、採用・研修コストの損失に加え、業務の引き継ぎ負担やチームの士気低下といった問題が発生します。エン・ジャパンの試算では、早期離職者1名あたりの損失額は約187.5万円にのぼるとされ、海外の調査では不適切な採用が企業に与える損害は年収の3倍に相当すると報告されています。
ミスマッチによる職場への影響
採用の失敗は、単なるコストの問題にとどまりません。適性に合わない人材が採用されることで、既存社員の負担増加や不公平感が生じ、職場の信頼関係を損なう要因になります。
特に、適性に欠ける人材が配属されると、業務を肩代わりする社員の負担が増えたり、「なぜこの人が採用されたのか?」という疑問が職場全体の士気を下げたりすることがあります。そのため、慎重な人材選びが求められます。
履歴書・面接だけでは判断が難しい理由
応募者の履歴書や面接だけでは、スキルや実際の働き方を正確に把握するのは難しいとされています。ある調査では、応募書類の3分の1に何らかの誇張や虚偽の情報が含まれているとも言われており、企業側には慎重な検証が求められます。
また、面接では応募者が自分を良く見せようとするため、実際の職場での働きぶりとのギャップが生じることもあります。そのため、客観的な情報を得る手段としてリファレンスチェックが重要になります。
参考:
厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)を公表します」
中小企業庁委託株式会社野村総合研究所「中小企業・小規模事業者の人材確保と育成に関する調査」
マンパワーグループ「新卒採用におけるミスマッチは8割超!ミスマッチによる悪影響の1位は採用した社員の早期退職」
エン・ジャパン株式会社「早期離職のコスト損失はどれくらい? 費用項目と金額の目安を解説」
U.S. Merit Systems Protection Board“Reference Checking in Federal Hiring: Making the Call”
University of Florida“Reference Check Guidelines”
リファレンスチェックのメリット

リファレンスチェックは、企業と求職者の双方にとって大きなメリットがあります。以下では、企業側と求職者側それぞれの視点から、そのメリットを詳しく見ていきます。
企業側のメリット:適切な人材の採用と離職リスクの低減
リファレンスチェックの最大のメリットは、不適切な人材の採用を防ぎ、早期離職や業務パフォーマンスの低下を抑えることです。
履歴書や面接だけではわからない応募者のスキルや仕事ぶりを、第三者からの客観的な評価を通じて事前に確認できるため、「入社してみたら想像と違った」という事態を減らすことができます。
米国連邦政府の人事管理における公平性や効率性を監督する独立機関”U.S. Merit Systems Protection Board”が公開する米国企業を対象にした調査によると、リファレンスチェックを導入したことで、新入社員の離職率が55%から9%へと大幅に改善したという報告があります。これは、事前にしっかりと適性を見極めたことで、採用の質が向上し、ミスマッチが減少したためだと考えられています。
また、適材適所の採用が進めば、組織全体の生産性向上や、既存社員の士気の維持にもつながります。適性に合った人材が加わることで、チームのパフォーマンスが向上し、「採用の失敗」による現場の混乱や不信感を防ぐことができます。
求職者側のメリット:自分の実績を正当に評価してもらえる
リファレンスチェックは企業だけでなく、求職者にとってもプラスに働く仕組みです。過去の実績や働きぶりが第三者によって裏付けられることで、自分の経歴や強みがより公正に評価されやすくなります。
特に、面接では伝えきれなかった長所も、元上司や同僚の証言を通じて補足されることで、採用担当者に伝わりやすくなる点が大きなメリットです。
また、リファレンスチェックが適切に運用されれば、求職者自身も「自分に本当に合った企業かどうか」を見極める機会になります。実績を正当に評価してくれる企業であれば、入社後も安心して働けるため、結果的に入社後の活躍や定着率の向上にもつながるでしょう。
参考:
U.S. Merit Systems Protection Board“Reference Checking in Federal Hiring: Making the Call”
リファレンスチェックの実施方法

リファレンスチェックを効果的に行うには、適切な手順を踏み、明確な質問を用意することが大切です。以下では、基本的な流れや質問例を解説します。
リファレンスチェックの基本的な流れ
1. 候補者への説明と同意の取得
リファレンスチェックを実施するには、事前に候補者の同意を得ることが必須です。最終選考の段階で、リファレンスチェックの目的や流れを説明し、書面やメールで正式に同意をもらいます。その際、「採用後のミスマッチを防ぐため」といった目的を明確に伝えると、候補者の理解も得やすくなります。
同意が取れたら、候補者に過去の上司・同僚・取引先など、仕事ぶりをよく知る2~3名の推薦者を選んでもらいます。候補者自身が推薦者に依頼する場合と、企業側が直接連絡を取る場合があるため、どちらの方法をとるか事前に決めておくとスムーズです。
2. 質問の準備と実施の計画
リファレンスチェックでは、「どのような情報を得たいのか」を明確にし、質問リストを作成します。確認すべき内容としては、以下のようなものがあります。
- 職務経歴やスキル
- 仕事への取り組み方や姿勢
- 対人関係やチームワーク
- 退職理由
ただし、年齢・宗教・家族構成など、業務と関係のない個人的な内容は聞かないよう注意が必要です。
また、リファレンスチェックの実施方法も決めておきましょう。一般的には電話で行いますが、メールやアンケートフォームを活用するケースもあります。電話で実施する場合は、推薦者と事前に日程を調整し、所要時間(通常15〜30分)を伝えておくとスムーズです。
3. リファレンスチェックの実施
実施の際は、以下のような手順で進めるとスムーズです。
- 自己紹介と目的の説明
まずは企業名と担当者名を伝え、「リファレンスチェックの目的」を簡潔に説明します。
- 候補者の職務内容の確認
具体的な業務内容や成果、在職期間などを事実ベースで確認します。
- 仕事の進め方や成果に関する質問
チームワーク・リーダーシップ・ストレス耐性など、候補者の強みや課題について具体的なエピソードを聞き出します。
- 率直な評価の確認
候補者の良い点だけでなく、改善が必要な点についても尋ね、客観的な評価を収集します。
4. 結果の分析と採用判断への活用
収集した情報は、人事担当者や採用マネージャーと共有し、履歴書や面接の内容と照らし合わせながら慎重に分析します。例えば、候補者が「リーダーシップがある」と自己評価していた場合、推薦者の意見と一致するかどうかを確認することで、信頼性を高められます。
万が一、懸念点が浮かび上がった場合は、追加で確認を行ったり、候補者本人に補足質問をするなど、慎重に対応しましょう。
また、リファレンスチェックで得た情報は機密情報として扱い、関係者以外に共有しないことが重要です。
リファレンスチェックの質問例
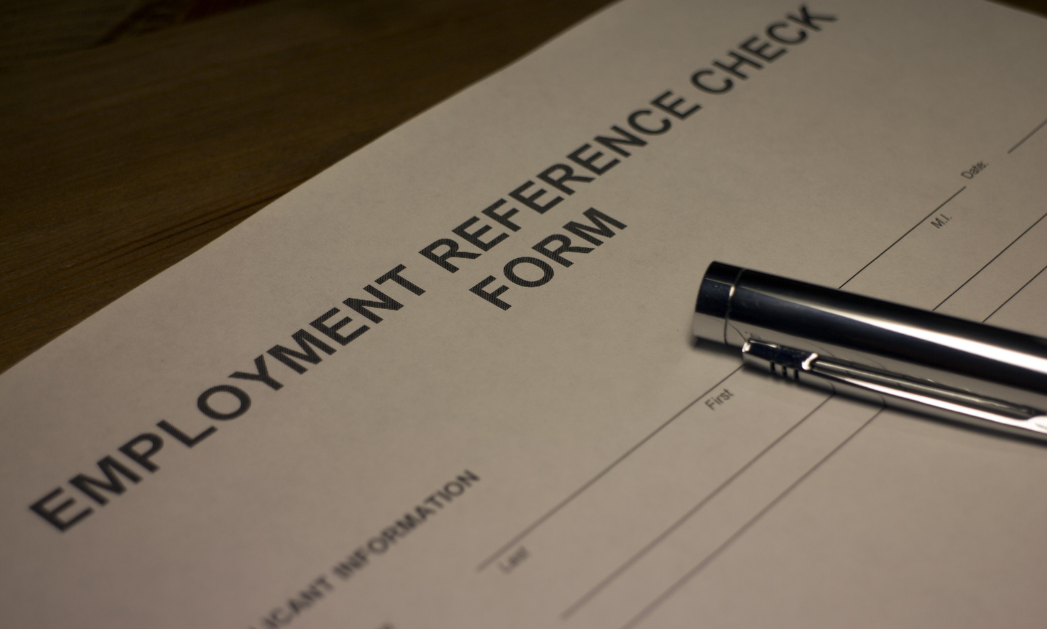
リファレンスチェックでは、事実確認と評価確認の両面から質問を行います。以下は、フロリダ大学やネバダ大学ラスベガス校のガイドラインを参考にした質問例です。
1. 経歴・勤務状況の確認
「〇〇さんの在職期間は20XX年X月から20XX年X月で間違いないですか?」
「当時の役職や担当業務、具体的な実績に相違はありませんか?」
「勤怠状況に問題はありませんでしたか?」
履歴書や面接での申告内容と事実を照合するための基本的な質問です。
2. 職務能力・仕事ぶりの評価
「候補者の強みはどこにありますか?また、改善が必要な点は?」
「〇〇さんはチームで働くのと個人で働くの、どちらが得意でしたか?」
「業務の納期や締切を守るうえで、信頼できる方でしたか?」
「ストレスの多い状況での対応はどのようなものでしたか?」
候補者の業務遂行能力や働き方を具体的に把握するための質問です。
3. 対人関係・リーダーシップ
「同僚や部下、取引先との関係性は良好でしたか?」
「チームの中でどのような役割を果たしていましたか?」
「リーダーシップやマネジメントスキルについて、どのような評価をされていますか?」
候補者のコミュニケーション能力や組織内での立ち位置を確認するための質問です。
4. 退職理由・再雇用の意向
「〇〇さんが退職(異動)した理由を、可能な範囲で教えていただけますか?」
「もし機会があれば、再び〇〇さんと一緒に働きたいと思いますか?」
退職の背景や、職場での評価を知ることで、リスク要因を把握できます。
質問のポイント
リファレンスチェックの質問は、すべて業務に関連した内容に限定し、公平かつ一貫性のある聞き方を意識することが大切です。
また、できるだけオープンな質問形式を取り入れ、推薦者が具体的なエピソードを交えて回答しやすいよう工夫すると、より深い情報を得ることができます。
例:
×「〇〇さんはリーダーシップがありますか?」
○「〇〇さんはチーム内でどのような役割を担っていましたか?」
このように質問を工夫することで、より自然な情報を引き出せます。
参考:
University of Nevada, Las Vegas (UNLV)“Reference Check Guidelines and Sample Questions”
University of Florida”Reference Check Guidelines”
まとめ
今後、リファレンスチェックは採用プロセスの新たなスタンダードの一つとなり、応募者もそれを意識して前職での信頼関係の構築や実績の積み重ねにより一層力を入れるようになるかもしれません。
ただし、重要なのはリファレンスチェックは「候補者を知るための手段の一つ」であり、最終的な判断は企業が自社の状況や総合的な評価をもとに行うべきという点です。リファレンス情報を参考にしつつ、面接で感じた人柄や適性とのバランスを考慮し、総合的な採用判断につなげることが大切です。
適切にリファレンスチェックを活用することで、ミスマッチの少ない採用が実現し、入社後の活躍や定着にもつながるでしょう。人材獲得競争が激しくなるこれからの時代、リファレンスチェックを効果的に取り入れ、「企業と人材の双方が納得できる採用」を目指していきましょう。