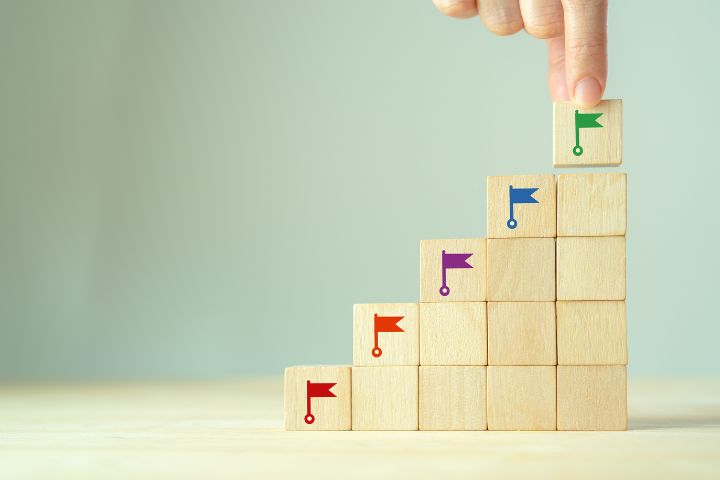「チームがうまくまとまらない」「いい雰囲気だったのに、最近ギクシャクしている」そんな悩みを感じたことはありませんか?
チームの立ち上げ時や新しいメンバーが加わったとき、あるいは環境が変わったときなど、チームづくりの難しさを感じる場面は誰にでもあるものです。
そんなときに参考になるのが、チームの成長過程を5つの段階で整理した「タックマンモデル」です。チームで起こる変化の流れを知ることで、今の状況を客観的に捉えやすくなり、対応のヒントも見つかります。
本記事では、タックマンモデルの各段階の特徴や職場でよくある行動、対立の乗り越え方、リーダーとしてできる対応などをわかりやすく解説します。チームの力を引き出すためのヒントとして、ぜひ活用してみてください。
タックマンモデルとは?

タックマンモデルは、心理学者ブルース・W・タックマンが1965年に4段階モデル(Forming, Storming, Norming, Performing)として提唱し、1977年にタックマンとメアリー・A・ジェンセンが5段階目「Adjourning(散会期)」を追加したことで現在の5段階モデルとなりました。
このモデルは、チームビルディングやマネジメントに携わる多くの人たちに活用されており、今でも多くの現場で引用されています。特に日本の職場では、対立や本音のぶつかり合いを避ける傾向が強いため、「混乱期」でチームが停滞しやすいと言われています。
タックマンモデルを理解しておくと、「今チームはどの段階にいるのか」「何が問題なのか」が見えやすくなり、適切な対応や声かけがしやすくなります。リーダーやマネージャーにとって、チームをより良い方向に導くための大切な視点となるでしょう。
参考:
infed.org “Bruce W. Tuckman – Forming, Storming, Norming and Performing in Groups”
チーム発達の5段階と職場で見られる行動

タックマンモデルでは、チームは5つのステージを経て成長するとされています。それぞれの段階では、メンバーの行動や感情に特徴が表れます。ここでは、職場でよく見られる様子を交えながら、各ステージの特徴を紹介します。
1. 形成期(Forming)- チームが動き始める段階
チームが結成されたばかりのこの時期、メンバーはお互いをよく知らず、不安と期待が入り混じっています。日本の職場では、まずは丁寧で礼儀正しいやり取りが交わされ、衝突を避ける傾向があります。
メンバーは「自分はここで何を求められているのか?」を探っており、リーダーに対して明確な指示や方向性を求める場面が多くなります。まだ遠慮が強く、本音を言いにくい時期でもあります。
2. 混乱期(Storming)- 意見がぶつかり始める時期
しばらくすると、チーム内で意見の食い違いや役割への不満が出てきます。進め方や優先順位を巡って摩擦が生まれ、雰囲気がピリッとすることもあります。
職場では表立った口論は少ないかもしれませんが、水面下では不満が蓄積していたり、遠回しなやり取りが増えたりします。例えば、若手とベテランの意見の違い、部署ごとの考え方のズレなどが、見えない対立の原因になることがあります。
この時期を乗り越えることで、チームの本当の信頼関係が育ち始めます。
3. 統一期(Norming)- 協調と信頼が生まれる時期
混乱期を経て、チームの中に少しずつまとまりが出てきます。お互いの強みや役割が見えてきて、自然と協力し合う雰囲気が生まれます。
職場では、暗黙のルールや「阿吽の呼吸」が育まれやすいのもこの時期です。メンバー同士が安心して意見を交わせるようになり、対立が起きても建設的に話し合えるようになります。信頼と一体感が徐々に深まる段階です。
4. 機能期(Performing)- チームが力を発揮する時期
この段階では、チームは成熟し、それぞれのメンバーが自律的に動けるようになります。役割を柔軟に補い合い、リーダーの細かな指示がなくてもスムーズに目標に向かって動けます。
日本企業でもこの状態のチームは、生産性が高く、報告・連絡・相談(報連相)も自然に行われ、トラブルも少なくなります。チーム内には強い信頼と結束があり、難しい課題にも前向きに取り組む姿勢が見られます。
5. 散会期(Adjourning)- チームの一区切り
プロジェクトが完了したり、チームの役割が終わったりして、解散を迎える段階です。日本では、メンバーが別の部署に異動するケースもあります。
この時期には、達成感と同時に少し寂しさを感じることもあります。打ち上げなどでお互いのがんばりを称え合いながら、次のステップに向けて気持ちを切り替えていくのが一般的です。
参考:
West Chester University “Tuckman’s Stages of Group Development”
MIT Human Resources “Stages of Team Development”
混乱期に起こりやすい対立と職場での影響

チームの成長にとって、混乱期は避けて通れない重要な時期です。しかし、日本の職場文化には「なるべく衝突を避けたい」「表立った対立は好ましくない」という空気が強くあります。
以下ではよく起きる対立のパターンについて紹介します。
職場で見られる典型的な対立パターン
- 役割や権限のあいまいさ
若手とベテランで意見が食い違ったり、「誰が決めるのか」が不明確で混乱が起こることがあります。
- 目標や手段の違い
部署ごとに評価軸が違うため、優先順位をめぐってすれ違うケースが起こりやすくなります。
- コミュニケーション不足
遠慮や忙しさから十分に話し合えず、誤解や不信感が生まれることもあります。
対立を放置するとどうなるか?
放っておくと、チームの士気や生産性が下がるだけでなく、深刻な問題に発展することもあります。厚生労働省所管調査を用いたJournal of Occupational Health Psychology(2015)の二次解析では、13,609事業所のうち約10%が「深刻なストレスによる長期休職・退職者がいる」と回答し、その原因の約4割が人間関係の対立だったと報告されています。
重要なのは、対立を避けることではなく、「安全に意見をぶつけ合える」場をつくることです。混乱期を乗り越えるには、リーダーが勇気を持って対立に向き合い、安心して本音が言える空気づくりを意識することが大切です。
参考:
ミツカリ「タックマンモデルとは?チームの成長を5段階で理解する理論」
各発達段階に応じた効果的リーダーシップ戦略

チームはどの段階にあるかによって、リーダーに求められる対応は変わってきます。ここでは、タックマンモデルの5つの段階ごとに、チームを前に進めるためのリーダーシップのポイントを紹介します。
形成期:安心感と方向性を与える
チームが結成されたばかりの形成期では、メンバーは「自分はここで何をするのか?」「どう関わればいいのか?」と不安を抱きやすいものです。リーダーはこの時期、まずチームの目的や目標をしっかり共有しましょう。
例えばキックオフミーティングを開いて、「このチームで何を目指すのか」「それぞれにどんな役割を期待しているのか」を具体的に伝えると、安心感が生まれます。日本の職場では、顔合わせや軽い懇親会なども効果的です。
リーダーは、どんな小さな質問にも丁寧に対応し、「いつでも相談していい」という雰囲気づくりを大切にします。この時期は基本的にリーダー主導でも問題ありません。まずは安心して動ける土台を整えましょう。
混乱期:対立を認め、チームの軸を再確認
混乱期には、メンバー同士の考え方や価値観の違いが表面化し、ぎくしゃくする場面が増えます。ここで大切なのは、「対立は悪いことではない」と伝えることです。
例えば、「意見がぶつかるのはチームが本音で話せている証拠です」と前向きに位置づけると、対立が必要なプロセスであることを理解してもらえます。そして、いま一度チームの目的やゴールを共有し、全員の意識を同じ方向に整えましょう。
また、「意見が対立したときのルール」も決めておくと安心です。例えば「相手の話を一度オウム返しで確認する」「批判ではなく提案の形で話す」など、建設的に話し合うためのルールを作ると効果的です。
日本の職場では、表立った対立を避ける文化がありますが、会議の前後に個別に話を聞いて調整する“根回し”も有効です。
統一期:協力体制を支え、自主性を後押しする
統一期に入ると、メンバー同士の信頼が生まれ、徐々に協力し合えるようになります。この時期は、リーダーが前に出すぎず、裏方に回って支えることがポイントです。
具体的には、意思決定をメンバーに委ねたり、会議で「皆さんで方向性を決めてみましょう」と促すことで、チーム内に自律性を育てることができます。
また、メンバーに思い切って重要なタスクを任せてみるのも効果的です。例えば大事なプレゼンを部下に任せる、リーダー不在でも進行できる会議を設けるなど、信頼して任せる姿勢が、さらなる成長を促します。
一方で、信頼関係ができてきたこの時期だからこそ、チームの動きが慣れに頼りすぎたり、停滞し始めたりしないよう注意が必要です。目標を見直したり、定期的に振り返る機会をつくることで、常に前向きな動きを保つことができます。
機能期:障害を取り除き、さらなる成長へ導く
チームが高い成果を出せる段階に入ると、リーダーの役割は「支えること」が中心になります。日々の仕事はメンバーに任せ、リーダーは外部との調整や、障害の除去に注力します。
例えば、他部署との連携を取り持ったり、経営層とのやりとりを担ったりして、メンバーが安心して仕事に集中できる環境を整えましょう。
この時期は、チームの惰性を防ぐために、新たなチャレンジや目標を提示することも大切です。「次はこんなテーマに挑戦してみよう」と声をかけることで、さらに一歩進んだチームづくりができます。
リーダー自身が実務に関わることも効果的です。「一緒にやってみよう」と自ら行動で示すことで、対等なパートナーとしての信頼も強まります。
散会期:感謝と次への一歩を支える
プロジェクトの完了などでチームが解散する散会期。リーダーには、「このチームで何を成し遂げたか」をしっかりと振り返り、メンバーに感謝を伝える役割があります。
例えば報告会を開いて成果を共有したり、打ち上げなどでお互いの健闘を称え合ったりすることで、気持ちよく一区切りをつけられます。
また、「この経験が次にどう活きるか」を一緒に考えることも大切です。チームで得た学びをテキストにまとめ、今後の業務や他チームへの共有資料として活用しましょう。
解散は終わりではなく、新たなスタートです。リーダーは「また一緒に働こう」「いつでも相談していいよ」といった声かけを通じて、信頼関係のネットワークを次につなげる役割を果たします。
参考:
West Chester University “Tuckman’s Stages of Group Development”
MIT Human Resources “Stages of Team Development”
まとめ
タックマンモデルは、チームの変化を理解し、適切な対応を考えるうえで非常に役立つフレームワークです。各段階の特徴を知ることで、今のチームに必要なリーダーシップが見えてきます。
衝突や停滞も成長の一部と捉え、丁寧に向き合うことが、信頼と成果につながる第一歩です。チームづくりに悩んだときは、ぜひ本記事を参考にしてみてください。