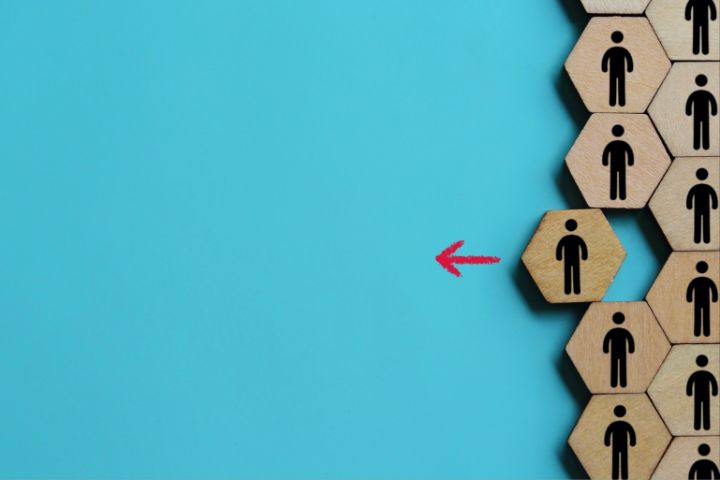このページのまとめ
- 自律型人材とは、主体的に考えて行動できる人材のこと
- 自律型人材の増加により、管理職の負担軽減が期待できる
- 自律型人材を育成するためには、責任のある仕事を命じるなど、挑戦できる環境を作る
企業が成長するためには、自分の力で考え、行動できる自律型人材の活躍が必要です。主体的に行動できる人材が増えれば、企業運営も行いやすくなるでしょう。しかし、自律型人材の育成は簡単ではなく、成長するための環境整備が大切です。今回は、自律型人材を育成するメリットや育成方法を解説します。従業員の能力を伸ばすための参考にしてみてください。
自律型人材とは
自律型人材とは、目標達成に向けて自分で考えて行動できる人材のことです。一般的には、主体的に考えて行動できる人材を自律型人材と呼びます。社会の変化が急激に進む現代社会では、変化に柔軟に対応できる自律型人材の育成が求められています。
依存型人材とは
自律型人材と比較されやすいのが、依存型人材です。依存型人材とは、自分で考えることはせず、与えられた指示だけをこなす人材のことです。指示に忠実に動けるという長所はあるものの、指示がなければ動くことができません。従業員の主体性を重視する企業では、依存型人材の評価は低くなってしまうでしょう。
自律型人材が必要な理由
自律型人材が必要な理由には、主に次の3点があげられます。
社会の変化に対応するため
自律型人材が求められる理由は、急速に変化する社会に対応するためです。グローバル化やダイバーシティの流行など、日本を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。企業が存続し、成長を続けていくためにも、自分の力で考えられる人材が必要です。自律型人材であれば、今後も見込まれる社会変化に柔軟に対応できるでしょう。このように、企業は自律型人材を育成し、柔軟性のある組織を作ることが必要です。
働き方が多様化しているため
日本でも働き方改革が推進され、働き方が多様化しています。テレワークの導入や時短勤務など、新しい働き方を取り入れている企業も多いことでしょう。働き方の多様化にともなって重要になるのが、従業員の自己管理です。働き方の自由度が増すほど管理が難しくなり、従業員自身で判断して業務を行うことが求められます。自律型人材であれば企業の管理負担も減り、働き方の多様化にも対応できるでしょう。
成果主義の流行
日本では、年功序列型から成果主義へと変わる企業が増加しています。成果主義を実現するためには、自分で考えて成果を出せる、自律型人材の存在が必要です。従来の年功序列型であれば、成果に関係なく、在籍年数が評価されていました。しかし、成果主義は在籍年数ではなく、若くても成果次第で評価されます。成果を評価するには、自分で目標達成を目指し、成果を出すために努力する自律型人材が必要です。指示を待っている人材だけを抱えても、企業の成長は見込めないでしょう。
自律型人材の特徴
自律型人材を雇用するために、どのような人材が自律型人材なのか知りましょう。自社の従業員から、自律型人材を探すための参考にもしてください。
主体性がある
自律型人材の一番の特徴は、主体性があることです。自分で考え、行動できる特徴を持ちます。
目標達成への努力や行動の改善、新しい戦略の立案など、さまざまな場面で行動できるでしょう。
自律型人材を採用する際には、主体性を持っているかどうかで判断しましょう。
責任感が強い
責任感が強い人物も自律型人材の特徴です。成功も失敗も自分の行動に原因があると考えます。
他者のせいにせず、自分の行動に責任を持てる人物は自律型人材だと言えるでしょう。
自分の軸を持っている
周囲の意見に流されず、自分の軸を持っているのも自律型人材の特徴です。考えとなる軸を持っているため、指示を待たなくても、考えて行動ができます。また、指示を受けた場合でも一度自分の頭で考えます。指示がおかしい場合はきちんと意見が言えることも、自律型人材の特徴です。
自律型人材が組織にいるメリット
自律型人材が組織にいるメリットは次のとおりです。
管理職の負担軽減
自律型人材が自ら考えることにより、管理職の負担軽減が期待できます。管理職にしかできない業務に集中してもらうことが可能です。たとえば、自律型人材はトラブルが発生しても、自分で考えて対処可能です。トラブルを放置したり、管理職が来るまで何もできない状況を避けることができます。自律型人材は、現場でのイレギュラーに対しても主体的に行動できます。自律型人材が組織に入れば、管理職の負担軽減につながるでしょう。
新しい提案が期待できる
自律型人材は自分で考えることにより、新しい発想を生み出すことができます。指示を待つだけでは思いつかない発想が出てくるでしょう。上司では気付かなかった内容も、現場ならではの目線で発見可能です。さまざまなチャレンジを行うなかで、新しい提案が期待できるでしょう。
環境の変化に適応しやすい
自律型人材は、環境の変化に適応しやすいメリットがあります。新しい環境でも、自分の考えや経験をもとに、どのようにすれば適応できるか考えられるためです。自律型人材は、自分の役割を意識したり、他者の期待を察知する能力に長けています。新しい環境でも、すぐに自分の役割を意識し、行動に移せるでしょう。このように、自律型人材は人事異動など環境の変化があっても、適応しやすいメリットがあります。
自律型人材を育てる方法
自律型人材を増やすためには、自社で育てることが大切です。既存の従業員を自律型人材に育成できるように工夫しましょう。ここでは、自律型人材を育てる方法を紹介します。
挑戦しやすい環境を作る
自律型人材の育成には、挑戦しやすい環境が重要です。
若手社員でも重要なプロジェクトに抜擢するなどの施策が大切です。挑戦を否定する環境では、従業員から主体性を奪ってしまいます。自分で考えて行動する姿勢を大切にする、挑戦しやすい環境を作りましょう。
企業理念を共有する
会社の方針や目標に沿って行動するためには、企業理念の理解が重要です。
自立型人材には、企業が求める役割を遂行するために主体的に行動することが期待されます。
従業員に期待する役割を事前に伝え、どのような成果を上げてほしいのかを共有するようにしましょう。
勉強できる環境を用意する
従業員の成長には、勉強できる環境も必要です。
たとえば、研修の参加費用・資格取得費用・書籍購入費用の補助などが実施できます。また、近年では、eラーニングを導入し、従業員が自由に勉強できる環境を整えている企業もあります。
従業員が向上心をもって働けるように、企業全体でサポートすることが大切です。
責任の大きい仕事を任せる
自律型人材を育成するために、責任の大きな仕事を任せてみましょう。
自分の行動が事業の成果に大きく影響する状況に置くことで、自らの力で考えて行動する力を養うことができます。従業員の成長のために、責任のある仕事を任せてみましょう。
上司がサポートを行う
従業員が自立型人材へと成長できるように、上司がフィードバックを行うようにしましょう。
右も左も分からない状態では、従業員はどのような行動をとるべきか判断できません。はじめは上司が従業員へのフィードバックを行い、主体的に考えて行動する基盤を整えることが重要です。
キャリア開発の実施
自律型人材のイメージができるように、キャリア開発を行いましょう。自律型人材に求められる考え方や、期待する役割などを教えます。ロールモデルが社内にいると、さらに理解しやすくなるでしょう。自律型人材のイメージが難しい従業員も多く、手本を見せるとイメージが湧きます。キャリア開発を行い、どのような人材になることが求められているのか、イメージさせましょう。
評価制度を整える
自律型人材を適切に評価するための評価制度を整えましょう。
成果に至るまでの考え方や行動も評価に入れる制度があれば、従業員は前向きにチャレンジしやすくなります。成果がともなわなくても、従業員の主体的な挑戦を認めてあげる環境を作りましょう。
成果とプロセスを分けて評価するなどの工夫をしてみてください。
まとめ
自律型人材を育てるためには、挑戦できる環境を用意し、行動を評価する仕組みを整えましょう。挑戦を評価する雰囲気であれば、従業員の行動も増加します。自律型人材の重要性は今後さらに高まるため、社内で自立型人材の育成に力を入れることが大切です。