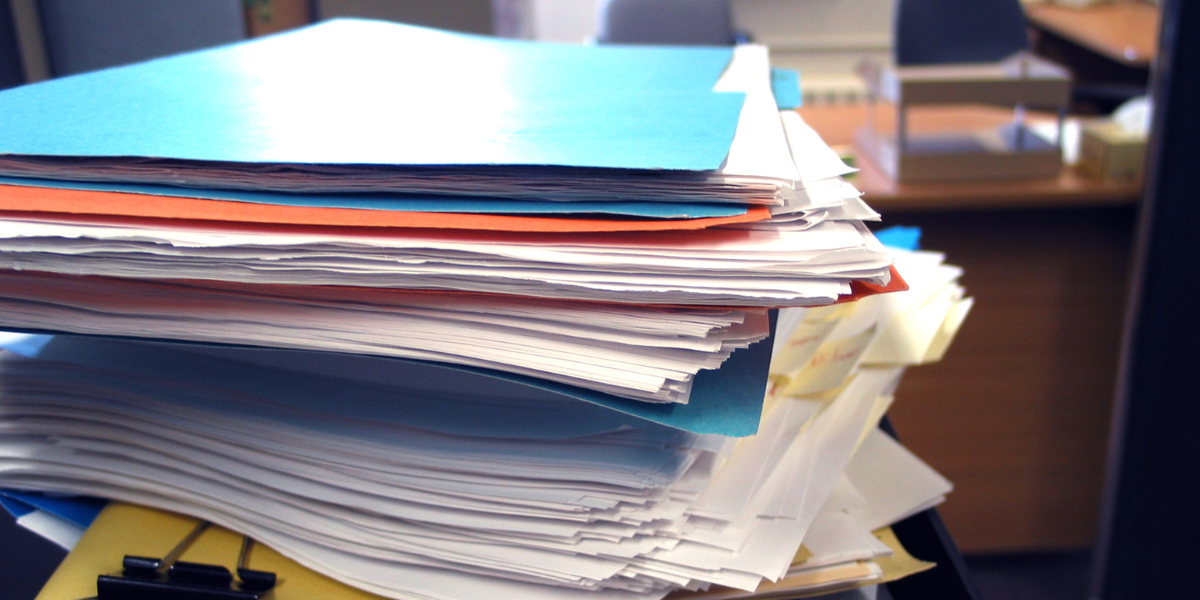「部下の仕事が遅くてイライラする」
「数分でできる作業をなぜ数十分もかかっているのか」
と、部下の仕事にイライラする方も少なくありません。
仕事のスピードには個人差はあるものの、どのようなことが原因で仕事が遅くなっているのかについて考えることも重要です。今回は、部下の仕事が遅くなってしまう原因やその解決方法について解説します。

この記事の監修者
曽和 利光(そわ・としみつ)
株式会社人材研究所 代表取締役社長
新卒で株式会社リクルートに入社後、ライフネット生命保険株式会社と株式会社オープンハウスを経て、2011年に株式会社人材研究所を設立。「人と、組織の可能性の最大化」をテーマに掲げ、人事、採用にコンサルティング事業などを展開。『人事と採用のセオリー』など、これまで多くの書籍を出版し、いずれも大きな話題を集めている。
【組織内】部下の仕事が遅くなってしまう原因とは?

「部下の仕事が遅くなるのはただ効率が悪いからだ」と決めつけてしまうと、その効率の悪さの根本的な原因を見逃してしまうことになります。以下では部下の仕事が遅くなる「組織内」の原因について、複数の海外の論文をもとに解説します。
部下に対する指示が曖昧な場合がある
シャンプレーン大学の記事によれば、部下の仕事が遅い原因に、部下に対する指示が曖昧であることが指摘されています。
指示が曖昧である場合、部下はどれくらいの精度で、いつまでに仕事を完了するべきかがわからなくなり、優先順位がつけづらくなってしまう可能性があります。
たとえば「この仕事なるはやでお願いします」と依頼した際に、部下は「具体的にどのタスクを優先して、どの程度の完成度を求められているのかがわからない」と混乱し、結果的に生産性が低くなってしまう可能性があります。
過労により睡眠不足や体調不良などが起きている可能性がある
オレゴン州大学の記事によれば、慢性的に長時間労働が蔓延している場合、部下は睡眠不足や体調不良を抱えている可能性があります。
上司の見えない部分で多くの仕事を抱えていたり、仕事の問題が解決できずに困ったまま放置されている状態があると、結果的に睡眠不足になり、仕事の効率にも影響を与えるようになります。
スキル、経験不足などで仕事が遅れている
オレゴン州大学の記事によれば、スキル、経験不足などにより、仕事を効率的に進められない可能性があると指摘しています。
上司にとっては当たり前にできると感じることでも、新入社員や若手社員にとって初めておこなう仕事も多いでしょう。
仕事を完遂させるために、調べごとをしたり、確認ごとをしたりしていて時間がかかることもよくあります。
この場合は上司の立場から見て「仕事が遅い」と感じている場合が多く、部下により効率的に仕事をしてもらうためにも、一定の教育が必要になるでしょう。
仕事の目的や意義を感じていないケースがある
McKinsey & Companyが公表している記事によれば、仕事に目的や意義を感じていない場合は仕事が遅くなるとされています。
「この仕事はこの目標に紐づいている」と感じながら仕事をするのと、「なぜこの仕事をやっているのだろう」と思いながら仕事をするのでは、生産性が大きく変わってきます。
部下の生産性を上げるためにも、部下の仕事と目標を紐づける必要があります。
社員が職場に不満を抱えている
社員が仕事や職場に対して不満を感じている場合、その仕事や組織に対するコミットメントが下がる傾向にあり、結果として生産性の低下を招く可能性があります。
「もう仕事を辞めたいな」という思いが強くなるほど、生産性は下がっていくでしょう。この場合は部下の仕事の効率が悪いという問題よりも、組織内に問題が起きている可能性があります。
これは適切な労働環境や条件が整っていない可能性もあり、この状況下で社員の努力で生産性を発揮するのは難しいといえます。
参考:
Champlain College Online”How to Give Constructive Feedback in the Workplace”
Oregon State University”Procrastination”
McKinsey & Company”Who is productive, and who isn’t? Here’s how to tell.”
【個人】仕事が遅い部下の3つの原因

先ほどは組織内で考えられる原因について解説しました。以下では、部下個人に焦点をあて、部下の仕事が遅い原因について解説します。
物事を先延ばしにする癖がある
オレゴン州大学が公表している記事によれば、物事を先延ばしにする癖がある人は、仕事が遅くなる傾向があるとされています。
例えば、重要なプレゼンテーションの資料作成を先延ばしにしたり、上司への報告を先延ばしにしたりして、十分な準備時間を逃している可能性があります。
また、過去に同じ仕事を担当した経験があり、自信のある仕事はすぐに着手できますが、未経験の場合は、億劫になり後回しにしてしまうケースもあります。
時間管理が苦手
コーナーストーン大学の論文によれば、時間管理が苦手なことも、仕事が遅れる原因の一つとされています。
時間管理が苦手な場合、自分の作業にどれくらいの時間がかかるのかを正確に見積もることができません。
その結果、無駄な時間を過ごしたり、締め切りに追われる状況に陥ります。また、優先順位をつけることが苦手な人は、重要でないタスクに多くの時間を費やし、本来の重要な仕事が後回しになることが多いです。時間管理のスキルを向上させるためには、タスクの優先順位を明確にし、効率的なスケジュールを立てることが必要です。
課題を分割して取り組むことができない
課題を分割して取り組むことができないことも、仕事が遅れる原因の一つです。仕事を部下に依頼する際に「このタスク、よろしく」とざっくり投げてしまうこともあるでしょう。
任された後に順序を立てずに大きなタスクに取り組むと、どこから手をつけるべきかわからず、結果として時間がかかってしまいます。
タスクを小さなステップに分割することで、進捗を確認しやすくなり、効率的に作業を進めることができます。しかし、これが苦手な人は、計画を立てる段階でつまずいてしまい、作業全体が遅れることがあります。
参考:
Oregon State University”Procrastination”
DELAY, DELAY, DELAY: HOW TO MANAGE AND OVERCOME PROCRASTINATION SO IT DOESN’T MANAGE YOU
仕事が遅い部下の生産性を向上させる方法
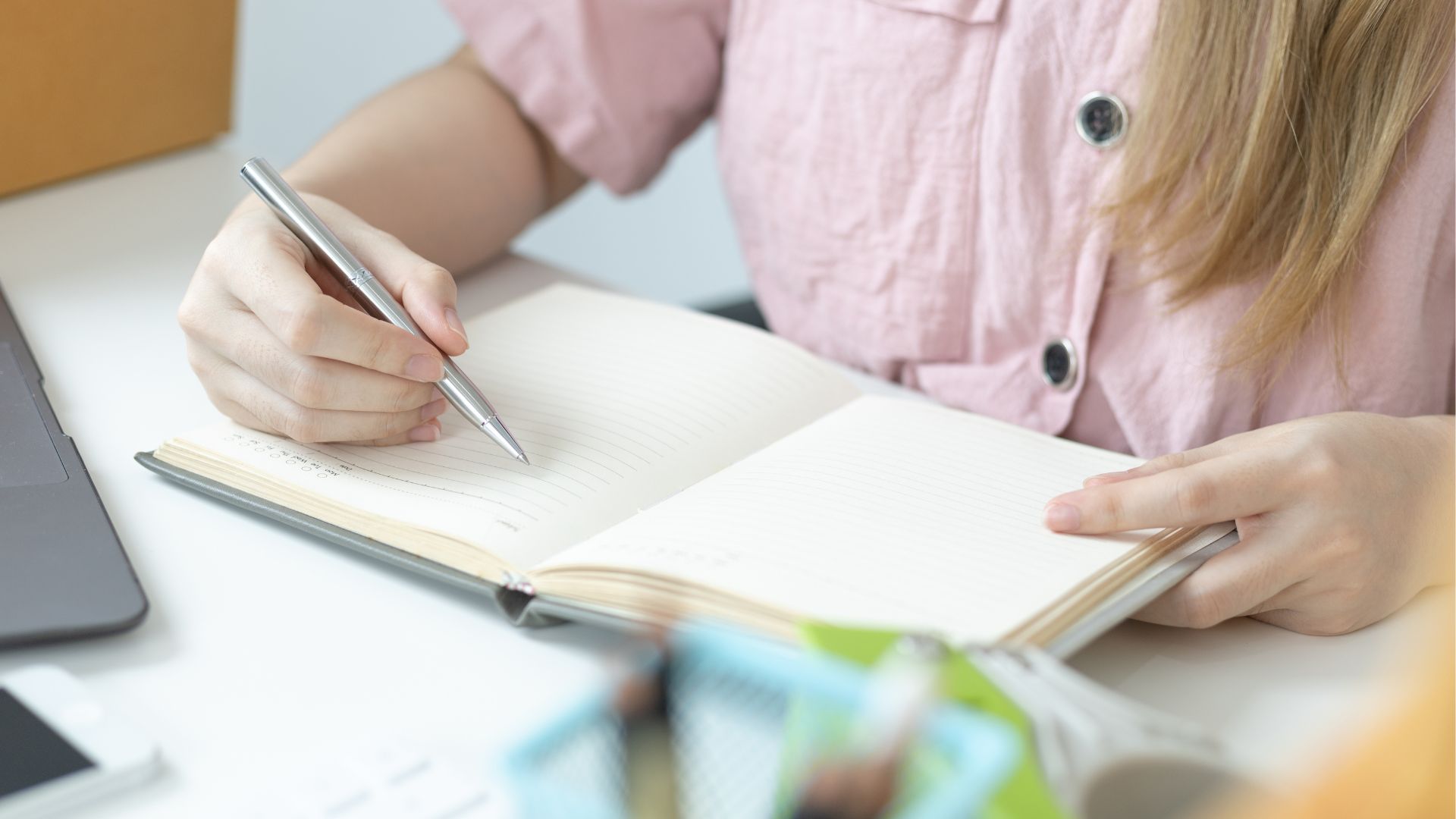
仕事が遅い部下の生産性を上げる方法について、いくつかの論文をもとに解説します。
取り組む仕事の価値と目的を明確にする
コーナーストーン大学の論文によれば、仕事の意義や目的を意識しながら仕事に取り組むことで生産性の向上が期待できるとされています。
例えばいまやっている仕事に対して、「日常の業務が単調に感じられ、何につながっているのかわからない」と意味や目的を感じていない場合、生産性にも悪影響を及ぼすことがあります。
そこで上司は部下に対して「この仕事で得られるスキルや経験は、将来的なキャリアアップにもつながる」と説明することで、それが自分にどのように役立つかを実感し、モチベーションや生産性を高めることができます。
小さな成功体験を積み重ねる
コーナーストーン大学の同論文によれば、大きな仕事を小さく分けて、それぞれを順に達成していくことで、達成感を味わいながら自信をつけ、効率を上げる方法も効果的とされています。
難しいタスクを丸投げするのではなく、「このタスクを終えたら、次のタスクをどう完了させるか一緒に確認しましょう」と伴走することが重要です。
そうすることで、部下は安心して仕事を進めることができるようになり、自分の成長を実感しやすくなります。また、上司と一緒に進捗を確認することで、部下は自分が適切にサポートされていると感じ、やる気やモチベーションが向上します。結果として、部下の仕事のスピードと質が向上し、チーム全体の生産性も高まるでしょう。
決まった休憩時間を設ける
ボーンマス大学の同記事によれば、生産性が下がっている原因に、チーム全体が多忙になり、休憩時間が取りづらくなっているケースもあるとされています。
作業時間の中に定期的に短い休憩を挟むことで、集中力を保ちながら、過剰な精神的負担を避けることが必要です。
上司から「少し休憩を取りましょう」「このタスクが終わったら10分休憩を入れましょう」「休憩を挟んでリフレッシュしたら、次の仕事に取り掛かりましょう」などとまめに休憩を提案することで、健康的に働くことができ、生産性の向上が期待できます。
ツールの活用も検討
部下の仕事が遅くなっている状況を、タスク管理ツールや生成AIなどを導入することで解決できる場合もあります。
例えば、タスク管理ツールを使って仕事の進捗状況を可視化し、優先順位を明確にすることで、部下は自分の役割や次に取り組むべきタスクを把握しやすくなります。また、生成AIを活用することで、ルーチン作業の自動化やデータ分析の効率化を図り、部下がより重要な業務に集中できるようになるでしょう。
こうすることで、部下も仕事に取り組みやすくなり、結果的に生産性の向上が期待できます。
参考:
まとめ
部下の仕事が遅くなる原因は様々なので、部下が直面している状況についてまずは注目する必要があります。その上でどのような対策が必要か考えてみましょう。
部下の仕事が遅くなる原因の一つに、ワークエンゲージメントの低下があります。ワークエンゲージメントの低下は、「職務特性理論」という5つの要素(多様なスキルを活かせる・タスクの全体像を理解できる・タスクの重要性を認識している・裁量がある・フィードバックを受ける機会がある)に注目することで、低下の要因を発見し部下のやる気と生産性向上の糸口を見つけやすくなります。
例えば、いつも期日に追われていたある部下の場合では、タスクの全体像や重要性の理解、フィードバックが不足していることが分かりました。そこでコミュニケーションを増やしこれらを改善した結果、部下のモチベーションが向上し依頼された仕事を期日前に提出できるようになりました。