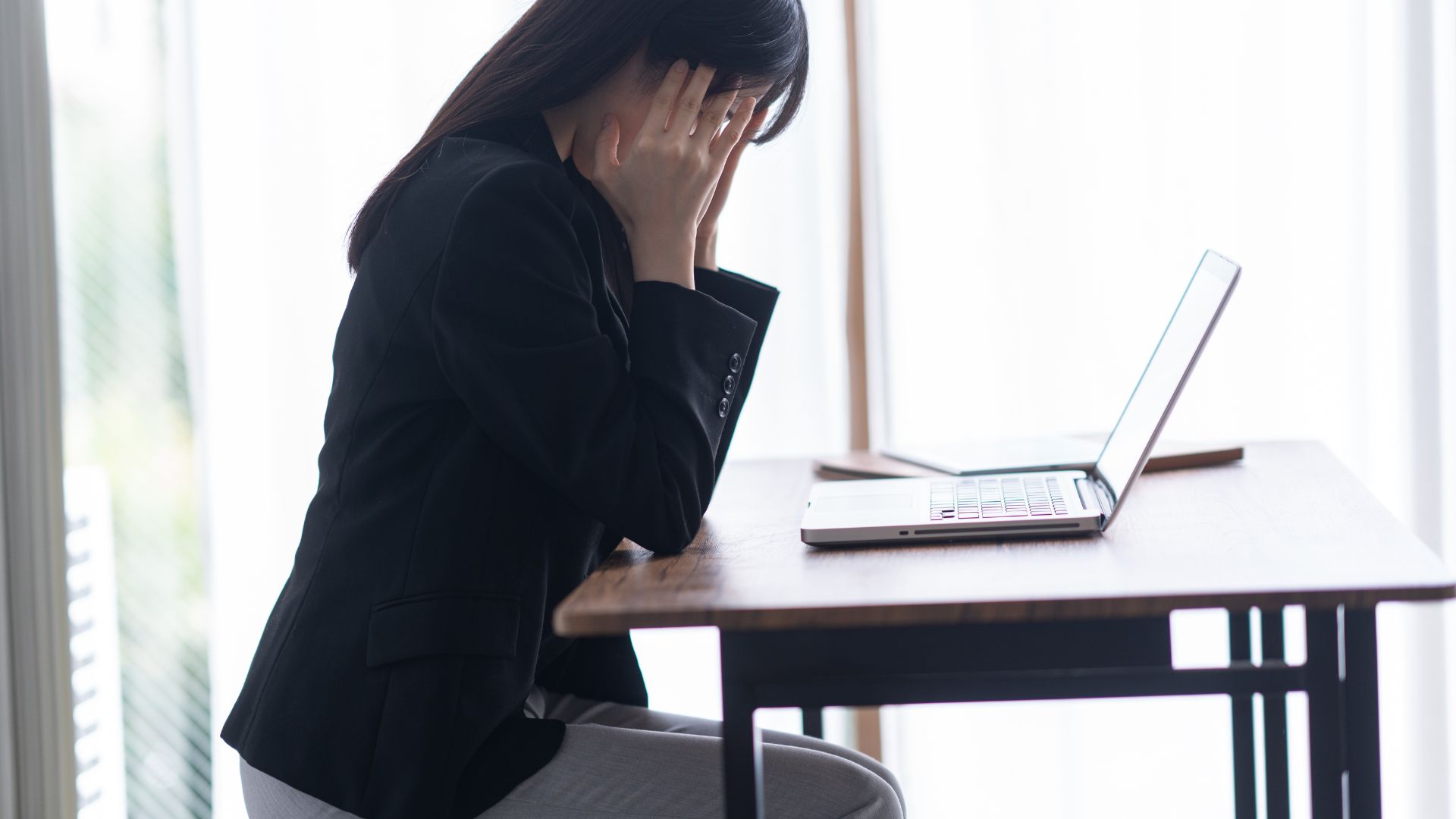部下数十名を抱えるプレイングマネージャーとして、若手社員の指導に悩むことはありませんか?特に、若手社員がどのような悩みを抱えているのかを理解し、その対策方法を知ることは、効果的なマネジメントの鍵となります。
本記事では、複数の論文をもとに、若手社員の悩みとその対策方法について詳しく解説します。チームの若手社員が直面する悩みを理解し、組織全体の成長に貢献する方法を見つけましょう。
若手社員が抱える7つの悩み

以下では若手社員が抱える具体的な悩みについて解説します。
人間関係の構築
若手社員は、職場の人間関係の構築が難しいと感じています。若手社員は、同僚や上司、会社全体との強い繋がりを感じることが少ないため、職場でのエンゲージメントが低いと感じる傾向があります。
会社や上司は、若手社員が会社で孤立しないように、職場での人間関係を構築する機会をつくるべきでしょう。
新しい技術や働き方へのプレッシャー
若手社員は、新しい技術や働き方に適応することにプレッシャーを感じています。若手社員は、職場でのストレスや燃え尽き症候群を上の世代よりも多く感じています。
また、若手社員はキャリアアップへの意欲が高く、同時にワークライフバランスも重視するため、柔軟な働き方を求めます。
企業は、若手社員の成長を促す機会を提供し、適切なフィードバックを行うことで、不安を軽減し、長期的なキャリア形成を支援する必要があるでしょう。
過度な労働
若手社員は、過度な労働へのストレスに悩んでいる可能性があります。若手社員は、 ワークライフバランスを重視し、キャリアアップへの強い願望を持つ傾向があります。
しかし、職場での適切な指導やフィードバックが不足しているケースも少なくありません。
スキル不足を感じて、残業や休日出勤によって過度な労働が続いてしまうこともあるでしょう。
過度な労働により、心身の健康を損ない、離職につながる可能性も懸念されます。企業は、若手社員のキャリアへの願望を理解し、定期的なフィードバックを通して成長を支援することが重要です。
ワークライフバランス
多くの若手社員にとって、ワークライフバランスの実現が大きな悩みとなっています。若手社員が新しい職を選ぶ際、給与や福利厚生と同じくらい、ワークライフバランスを重視しています。
しかし、キャリアアップとワークライフバランスの両立が難しく、ストレスの原因となっているケースが多く見られます。さらに、ワークライフバランスが取れないことで、離職リスクが高まる可能性も指摘されています。
このような状況を踏まえ、企業には柔軟な勤務形態の導入や、メンタルヘルスケアの充実が求められるでしょう。若手社員のワークライフバランス実現を支援し、若手社員の成長と企業の発展につなげることが重要です。
キャリアアップ
先述したとおり若手社員は、キャリアアップについて悩んでいます。若手社員はキャリアアップへの強い意欲を示す一方で、職場での成長の機会や適切なフィードバックの不足を感じている傾向にあります。
その要因は企業によって異なりますが、ベテラン社員との交流や上司からの定期的なフィードバックの不足もその要因の一つでしょう。
上司は定期的なフィードバックや明確な目標設定を通じて、若手社員の成長をサポートしていくことが重要です。
支援不足が招く「放置されている」という不安
また、ALL DIFFERENT株式会社の若手社員1,200人調査によると、社会人1年目の5人に1人が業務支援を「全く受けていない」と回答しています。入社直後で右も左も分からない状況にもかかわらず放置されていると感じ、強い不安を抱えている実態がうかがえます。基本的な業務の進め方に関する支援がないことが、若手の孤独感や不安を増大させる大きな要因となっていると考えられます。
視野と人脈を狭める「身内だけ」の支援
同調査によると、支援者が同じチームの先輩に偏るため、「新しい切り口での考え方」や「業務に詳しい関係者の紹介」といった支援は1割以下と乏しい状況です。このため、若手は視野を広げたり、組織内の人脈を形成したりする機会を失っているという問題が指摘されています。
参考:
【ラーニングイノベーション総合研究所「若手社員1,200名の意識調査(業務支援編)」】
若手社員の悩みを放置するリスク

若手社員の悩みを放置するリスクについて、公衆衛生局長官室 (OSG) が公開した、経営学修士を取得するヴィヴェック・H・ムルシー氏による論文を参考に解説します。
健康に関する問題の増加
若手社員の悩みを放置すると、ストレスにより健康に関する問題の増加につながります。若手社員が安心して働き、健康を維持できるよう、企業は職場環境の改善やワークライフバランス支援などに積極的に取り組む必要があります。
職場におけるメンタルヘルスとウェルビーイングへの投資は、従業員の健康状態の改善だけでなく、生産性や離職率の改善にもつながり、最終的には組織の業績向上に貢献するでしょう。
人間関係への悪影響
若手社員の悩みを放置すると、職場での人間関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。職場での悩みにより、メンタルヘルスの問題を抱えた場合、そのことを隠したり、助けを求めることをためらったりする人が多く、孤立してしまうリスクがあります。
仕事でストレスを抱えていると、イライラしやすくなったり、家族や友人とのコミュニケーションが減ったりするなど、私生活の人間関係にも悪影響が及ぶ可能性も考えられるでしょう。
生産性と業績の低下
若手社員の悩みを放置すると、生産性と業績の低下につながります。若手社員の悩みによるストレスは、心身の健康問題を引き起こし、結果としてパフォーマンスの低下や離職につながる可能性があります。
企業は労働者の安全と健康を優先し、職場環境を改善することで、生産性と業績を向上させることができます。具体的には、ワーク・ライフ・バランスの実現や適切な休息の確保、上司からの定期的なフィードバックなどが挙げられます。
離職率の増加
長時間労働や柔軟性のない職場は、若手社員のワークライフバランスを阻害し、離職に繋がる可能性が高まります。さらに、職場での孤立や上司からのパワハラなど、職場の居心地が悪くなると、従業員のモチベーションやエンゲージメントが低下し、離職率の増加につながります。
優秀な人材の流出は、組織の競争力を低下させるだけでなく、採用や教育にかかるコストの増加を招く可能性があります。若手社員の悩みや不安に適切に対処し、職場環境を改善することで、離職率の増加を防ぐことができるでしょう。
参考:
若手社員の定着率を高める7つの方法

若手社員の定着率を高める方法について、ハーバードビジネスレビューに掲載された、マサチューセッツ大学アマースト校の社会学教授のドナルド・トマスコヴィッチ・デヴィー氏らによる記事を参考に紹介します。
職場でのつながりを築く
若手社員の定着率を高めるには、職場での「つながり」を重視することが不可欠です。若手社員は、仕事にやりがいを求めるだけでなく、職場での人間関係や帰属意識を重視する傾向があります。
たとえば、上司と部下、同僚同士、そして顧客との間で信頼関係を築くことは、孤独感を軽減し、ストレスや不安への対処を助け合える環境を作ります。また、チームワークを重視し、定期的なコミュニケーションを活性化することで、一体感が生まれます。
単なる仕事仲間ではなく、共に助け合い、成長できるコミュニティを形成することが、現代の若手社員にとって重要な定着要因といえるでしょう。
役割を明確にする
若手社員の定着率を高めるには、役割を明確に伝えることが重要です。若手社員は職場経験が浅いため、仕事内容や役割、期待値に対する理解が不足している場合が多いです。
そのため、若手社員は会社での自分の役割の不明確さが不安やストレスとなる可能性があります。若手社員にとって、新しい環境に適応し、成果を上げるためには、自分が何をすべきか、何が求められているかを具体的に理解することが不可欠です。
若手社員が安心して仕事に取り組める環境として、若手社員が質問しやすい雰囲気作りや、定期的な1on1ミーティングの実施も効果的といえるでしょう。
企業文化の理解
企業文化は、若手社員の行動や意思決定に大きな影響を与えます。若手社員が企業文化を理解し、共感することで、組織への帰属意識が高まり、定着率向上につながります。
企業理念や価値観を共有する機会を設けたり、社内イベントに積極的に参加させたりすることで、企業文化を体感させることができるでしょう。
自信をつけさせる
若手社員の定着率を高めるには、自信を付けさせることが有効です。自信をつけさせることで、仕事にやりがいを感じ、積極的に業務に取り組むことができます。
自信を高めるための具体的な施策として、上司からの定期的なフィードバックや、スキルアップのための研修機会の提供などが挙げられます。
若手社員の自信を高めることは、個人の成長を促進するだけでなく、組織全体の活性化、ひいては定着率向上に大きく貢献すると言えるでしょう。
1on1など継続的なサポート
社員の定着率を高めるには、継続的なサポートが有効と考えられます。若手社員は職場に適応しつつ、職場が自分にとって働きやすい環境かどうかを見極めています。
継続的な上司からのフィードバックや質問しやすい環境づくりは、若手社員が安心して仕事に慣れ、成長を感じられる環境を構築するために重要です。1on1ミーティングの導入や若手社員にとって働きやすい職場環境、質問しやすい風土づくりなどが、若手社員の定着率向上につながるでしょう。
若手社員の意見を積極的に聞く
若手社員の意見を積極的に聞くことは、満足度と定着率の向上につながります。若手社員は自分の意見が無視される環境では働きがいやモチベーションを失いやすくなります。
そのため、お互いの尊重と信頼を築くことが、若手社員が職場に留まるための重要な要素となります。1on1などを通して、上司と若手社員が双方向のコミュニケーションをとることも有効といえます。
若手社員が自分の意見や疑問を尊重してもらえる環境を作ることを意識しましょう。
キャリアパスを示す
若手社員の定着率を高めるためには、キャリアパスを明確に示すことが有効です。若手社員は、長期的なキャリアの展望が見えない職場に対して不安を感じることが多いです。
上司は若手社員との面談で、積極的にキャリアパスについて質問したり、キャリア目標となる社員と話す機会を作ったりすることが大切です。
キャリアパスを明確に示すことで、若手社員は長期的に職場にとどまり、企業全体の成長に貢献する意欲を持つことができます。
参考:
まとめ
若手社員の悩みや悩みについて解説しました。若手社員は、職場の人間関係の構築や過度な労働、キャリアアップについて悩んでいます。若手社員の悩みを放置すると、生産性の低下による業績悪化にもつながりかねません。
若手社員の定着率を高めるためには、ワークライフバランスの実現やキャリアサポート、社内でのつながりの強化などが有効です。若手社員の悩みを理解し、職場環境の改善や適切な教育を行うことで長期的に戦力となる人材を育てましょう。