人手不足の対策をどうすればいいか分からず、お困りの管理職の方もいらっしゃるでしょう。
待遇を改善したり、複数の採用方法を取り入れたりするほか、自動化技術の導入や業務の外注など、企業で行える対策はさまざまです。
この記事では、日本の現状や人手不足に悩む企業の特徴、企業に生じるリスクなどについても解説します。
日本の人手不足の現状

厚生労働省の「令和6年版 労働経済の分析 -人手不足への対応-」によると、人手不足は2010年代から現在まで続いています。
ハローワークに出された求人のうち、実際に採用につながった割合(=充足率)は年々下がってきています。特にフルタイムの仕事では、2023年に充足率がたったの10.2%と、低い水準を推移しています。つまり、10件求人を出しても、1人しか採用できていないということになります。
フルタイムの仕事では採用までに時間がかかる傾向があるため、企業としては「人が足りない」と感じる状況が、ますます強くなっていると考えられます。
また、今後も高齢化により、人手不足が深刻化する可能性があります。2040年には人口の35%弱を65歳以上の高齢者が占めると見込まれています。
産業を問わず人手不足感が強い
同白書によると、2021年12月以降、すべての産業で雇用人員判断D.I.がマイナスの状態で推移しています。雇用人員判断D.I.とは、人手の過不足について企業の判断を表す指数のことです。マイナスの場合、人手不足の状態だと考える企業の割合の方が多いことを表します。
日本銀行の「全国企業短期経済観測調査(短観)(2023年12月調査全容)」によると、全産業でマイナス35、特に数値が低いのが宿泊・飲食サービスで、マイナス75です。雇用人員判断D.I.の数値から、現状では産業の種類を問わず人手不足感が強く、特に宿泊・飲食サービスで深刻なことが分かります。
全国的に人手不足
同白書によると、2010年代以降、地域間での有効求人倍率の差はあまりみられません。有効求人倍率とは、ハローワークにおける1人の求職者に対する求人数を示す指標です。有効求人倍率はどの地域でも1〜1.5倍となっており、人手不足が全国的であることが分かります。
政府が実施する人手不足対策とは
厚生労働省のWebサイトによると、労働者の採用と定着向上のために労働環境などを向上させようとする事業主に対して、人材確保等支援助成金を支給しています。
そのほか、労働局で労働時間などの設定を改善するための相談ができるほか、ポータルサイトでは社員の働き方や休み方を見直すための情報の閲覧が可能です。
また、人材開発施策についての情報公開、非正規雇用労働者を正規雇用転換した事業主への助成金、ハローワークでの求人と求職者のマッチング支援なども行っています。
参考:
厚生労働省「令和6年版 労働経済の分析 -人手不足への対応-」
厚生労働省「人材確保対策」
日本銀行「全国企業短期経済観測調査(短観)(2023年12月調査全容)」
人手不足が起こる背景

人手不足が起こる背景について解説します。
労働市場における需要と供給のミスマッチ
内閣府の「令和6年度 年次経済財政報告」によると、人手不足が深刻化するなかで、限られた労働力を企業のニーズに的確に結びつけることが求められています。
しかし、労働市場のミスマッチが原因で、2022年度は新規雇用の11%以上が失われていると示唆するデータもあります。
ミスマッチには職種によって需給に差が出る職種間要因と、ある地域では求人が多いのに、別の地域では働きたい人が多く、地域をまたいでうまくマッチングできない都道府県間要因があります。
コロナ禍での移動制限による影響があったことなどから、近年のミスマッチ拡大の主要因は都道府県間要因です。ハローワークでは求職者をほかの都道府県の求人と結びつけるのが困難だったという背景もあり、ミスマッチの拡大と新規雇用の喪失に繋がっていると考えられるでしょう。
離職者の多さ
同白書によると、企業意識調査では人手不足の原因として「離職者・退職者の増加」を挙げた企業が56%程度と一番多い結果でした。
5年前の2019年と比べ、転職等希望者数は約800万人から1,000万人超まで増加しています。これらの背景として、転職への価値観が変化していることなどが考えられるでしょう。
かつては終身雇用が一般的でしたが、現在は転職が当たり前だと考える若者は多くいます。経験が広がったりチャレンジできたりといった、ポジティブなイメージを持つ若年層も少なくありません。
部下が転職する原因については、以下の記事もご覧ください。
人手不足に悩む会社の特徴

以下では人手不足に悩む会社の特徴を紹介します。
業務量が多い
従業員の数に対して業務量が多すぎると、現場では人手不足と感じられることが多くなります。
エン・ジャパンが実施した「人事のミカタ」を利用する企業の人事担当者が対象のアンケートによると、人材不足の部門があると答えた企業のなかで、人材不足の原因について「業績が好調で業務量が増加した」「既存業務が拡大した」という回答はそれぞれ28%でした。
この結果からも、業務が増えているにもかかわらず人員が増えていない企業では、従業員一人ひとりの負担が大きくなり、人手が足りないと感じやすい傾向があることが分かります。慢性的な人手不足に陥る前に、早期の対応が求められます。
待遇が良くない
給与や福利厚生などの待遇が良くない場合、従業員の退職に繋がる場合もあります。その結果、人手不足になるケースもあるでしょう。
2019年8月に小千谷商工会議所が行ったアンケートによると、人手不足の原因として考えられることとして「高い賃金や福利厚生、賞与などの資金を確保できない」と答えた企業は12.6%でした。
この結果から、待遇が悪いことで人手不足に繋がっていると考える企業が一定数いることが分かります。待遇の悪さは従業員の離職に繋がるだけでなく、応募者が集まりにくくなることも考えられるでしょう。
求人条件を満たした応募がない
設定している応募条件が厳しく、該当する求職者が少ない場合、応募も集まりにくくなると考えられます。
帝国データバンクのアンケートによると、人手不足になっている原因として「条件に合う人からの応募がない」と回答した企業は54.6%でした。
即戦力となるスキルの高い人材を求める場合、思うように応募が集まらず採用に繋がらないケースもあると推察できます。
参考:
エン・ジャパン「2024年「企業の人材不足」実態調査ー人事・採用担当者向け情報サイト『人事のミカタ』アンケートー」
小千谷商工会議所「各種アンケート結果」
株式会社帝国データバンク 「特別企画:企業における人材確保・人手不足の要因に関するアンケート」
人手不足が企業に与える悪影響
以下では、人手不足が企業に与える悪影響について解説します。
従業員の負担が増える
人手不足になると、従業員一人ひとりの負担が増える場合もあるでしょう。
東京商工リサーチが行ったアンケート調査によると、5,392社のうち2,821社が「人手不足で悪影響がある」と回答しました。どのような悪影響があるか質問したところ、「従業員の作業負担が増加した」と答えたのは、回答企業2,714社のうち半数以上にあたる1,401社です「従業員の労働時間が増加した」と1,077社が回答していることからも、人手不足になると従業員の負担が増えやすくなることが分かります。
倒産につながる
人手不足になると、人員を確保するための人件費上昇から生じる負担などによって、倒産に繋がる場合もあるでしょう。
「令和6年版 労働経済の分析 -人手不足への対応-」によると、2023年の人手不足関連倒産は調査を開始してから最多となりました。具体的には、70%以上を占める後継者難型、前年から大きく増加した人件費高騰型と求人難型、そして従業員退職型などが内訳です。
参考:
株式会社東京商工リサーチ「「人手不足」の影響広がる、企業の52.3%が実感 大企業は6割超、従業員へのしわ寄せや受注控えも」
厚生労働省「令和6年版 労働経済の分析 -人手不足への対応-」
人手不足対策はどうすればいい?
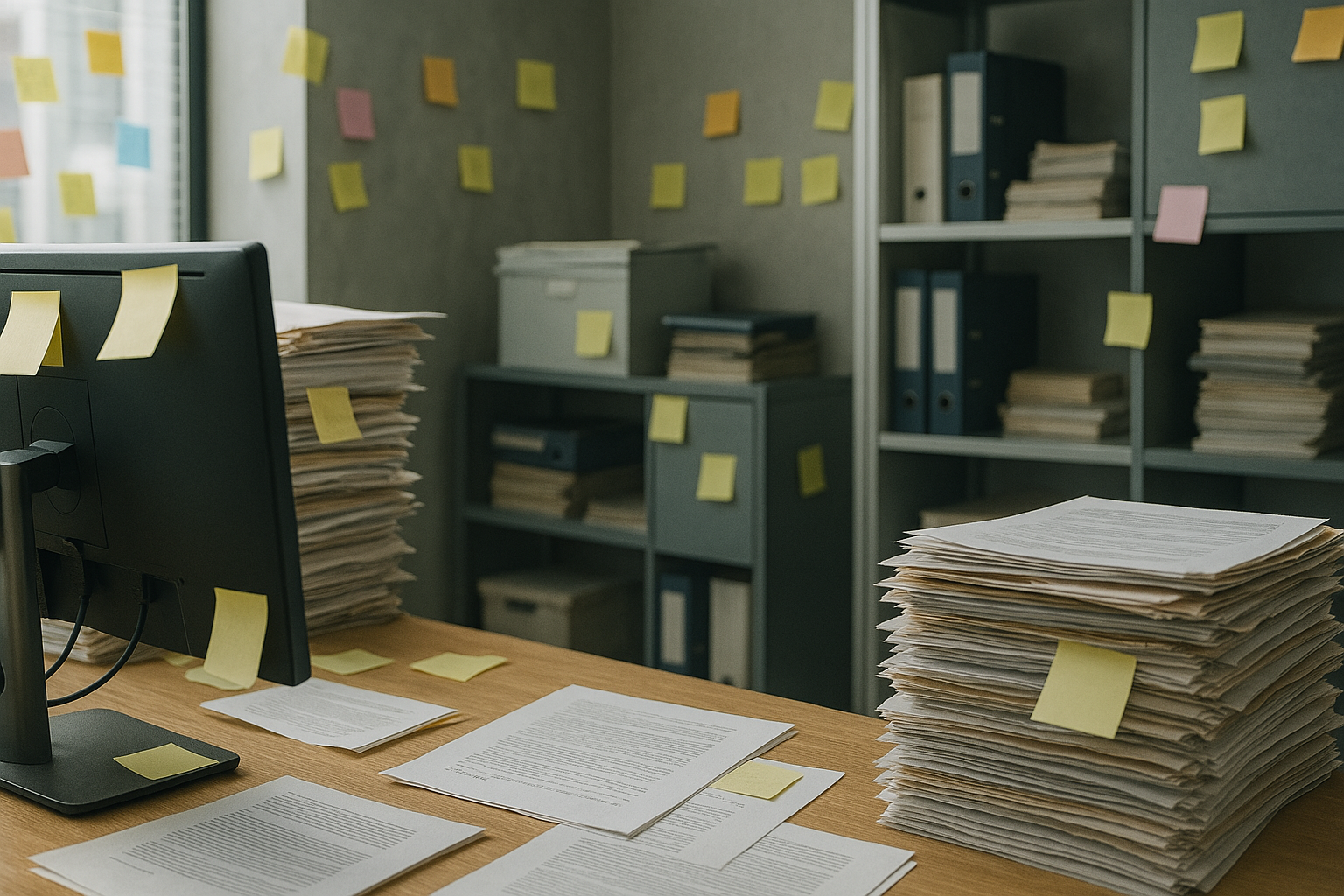
以下では、企業が行うべき人手不足対策について解説します。
待遇を改善する
Syndicat European Trade Union Confederation(シンジカット欧州労働組合総連合)の記事によると、ヨーロッパにおける人手不足解消には待遇の改善が必要とされています。2019年から2022年の間に人手不足が一番増加した部門では労働条件が劣悪な傾向があったほか、類似している労働者間でも低賃金の職業の場合は人手不足が増加したことなどが分かっています。
The European Trade Union Confederation(欧州労働組合連合)の事務局長によると、十分な労働者を見つけるためには賃金を上げることが大切です。また、劣悪な待遇で競争するのではなく、高品質の仕事やテクノロジーに投資して生産性を上げるべきだとしています。
採用方法を変える
SHRMの記事によると、人手不足を緩和するには、さまざまな採用方法を組み合わせることが役立ちます。
リファラル採用を追加したり、見直したりするほか、人材派遣会社の利用、採用効率化ツールの導入、採用フローの簡略化などが一例です。採用方法を広げることで今までアプローチできていなかった人材に出会ったり、人材派遣会社の利用や採用の簡略化などによって、人材獲得までの時間を短縮したりできる可能性も考えられます。
そのほか、人材プールを拡大するため、資格条件を緩和し、大学と連携してインターンシップを開発することも有効でしょう。
業務を外注する
専門的な業務を担当できる人材が集まらない場合、業務を外注するのも一つの方法です。
NACUSO(全国信用組合サービス機構)が公開する情報によれば、ある金融機関が延滞債権を回収する業務をアウトソーシングするメリットが挙げられています。外注すれば、採用や研修コストを削減でき、従業員は得意分野に集中して取り組めます。
外注先を選ぶ際は、管理能力や実績、リスク管理、コンプライアンスなどの観点から探すと良いでしょう。
安心できる職場環境を作る
イギリス政府と企業が共同で推進した、従業員エンゲージメント(仕事への熱意や積極性)を高めるための取り組みENGAGE FOR SUCCESSが公開した情報によると、従業員の定着率を上げるには安心できる職場環境を作ることが大切です。
社員が尊重され、大切に扱われていると実感できる安心感のある職場を作るために、ハラスメント対策をしっかり行いましょう。
厚生労働省のWebサイトによると、パワハラ対策は事業主の義務の一つです。また、セクハラへの対策や、妊娠・出産・育児休業・介護休業などのハラスメント対策についても義務とされ、具体的には、明確化した方針の周知や、労働者からの相談に対応できる体制の整備、再発防止措置を講ずることなどが挙げられています。
ワークライフバランスを整える
同記事によると、従業員の定着率を上げるにはワークライフバランスを整えることが大切です。
具体的には、仕事が終わったあとに連絡したり、休日に業務を依頼して家族との時間を妨げたりするのは避けましょう。部下には「夜遅くまで働くことを望んでいない」と明確に伝え、ワークライフバランスの取れた働き方を促すことが大切です。
テクノロジーに投資する
北米最大の自動化業界団体であるオートメーション振興協会の記事によると、人手不足の解決策として自動化が有効です。
近年では、動作が自動化されたCNC工作機械の管理や溶接など、特定用途の自動化導入プロセスが簡単になったソフトウェアもあります。生産性や利益率の向上などに繋がる可能性もあるため、自社で取り入れられる自動化技術がないか探してみると良いでしょう。
リスキリングを推進する
サンダーバードグローバル経営大学院の記事によると、人材不足解消のためにリスキリングやアップスキリングを行うことも一つの方法です。リスキリングは新しいスキルを習得させることで、アップスキリングは現在のスキルを拡張したり強化したりすることを指します。
職務と従業員の間にスキルギャップがある場合、正社員の新規採用よりも既存従業員のスキルアップを図った方が、約3,000ドルのコスト削減につながると推定されています。
従業員のスキルアップに取り組む場合は、必要なスキルを特定したうえで、研修内容を開始し、継続的な学習を奨励する環境を作りましょう。
従業員に仕事を教える時間が足りない場合の対処法やリスキリングの導入については、以下の記事もご覧ください。
参考:
Syndicat European Trade Union Confederation“Study: Low pay causing labour shortages”
SHRM“Labor Shortages: The Disconnect and Possible Solutions”
NACUSO“Outsourcing as a solution for labor shortage amidst rising delinquencies”
ENGAGE FOR SUCCESS”6 Sure-fire Ways To Improve Employee Retention”
厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」
ASSOCIATION FOR ADVANCING AUTOMATION “Upskilling and Automation: Two Proven Solutions to the Labor Shortage”
Thunderbird School of Global Management “Why is There a Global Talent Shortage and What Can You Do?”
まとめ
現状では、どの産業においても人手不足感があるといえます。そのため、従業員の負担の増加や倒産を防ぐため、企業が対策を取る必要があります。
待遇や採用方法の見直しを行うほか、外注や自動化技術を取り入れるなど、方法はさまざまです。自社で取り組みやすいものから、始めていきましょう。

