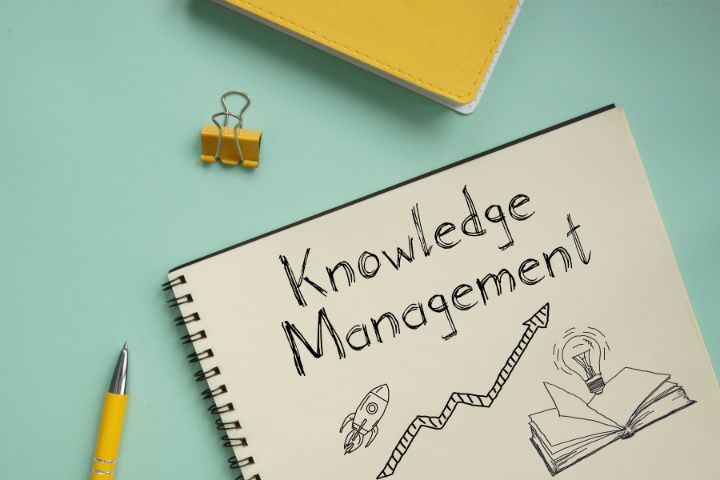このページのまとめ
- ナレッジマネジメントは、個人の知識を企業に還元し、共有する手法のこと
- ナレッジマネジメントで大切なのは「暗黙知」と「形式知」
- ナレッジマネジメントで形式知同士を組み合わせることで、新しいノウハウが生まれる
企業のさらなる成長のために、ナレッジマネジメントが注目を集めています。ナレッジマネジメントとは、従業員一人ひとりが持つノウハウを企業全体で共有し、企業の経営に活かしていく方法を指します。今回は、ナレッジマネジメントの導入方法や導入時の注意点について解説します。「全社でノウハウを共有できる仕組みをつくりたい」という企業担当者の方は、参考にしてみてください。
ナレッジマネジメントとは
ナレッジマネジメントとは、個人が持っている知識やスキルを企業全体で共有し、新しい技術の開発や生産性向上を目指す手法のことです。
ナレッジマネジメントで重要なのが、「暗黙知」を「形式知」に変えることです。
暗黙知とは、文章などで言語化されていない知識を指します。文章や図表などにまとめられていない知識が暗黙知に当たります。一方、形式知は文章や図表でまとめられた知識を指します。
暗黙知は、文章や図表でまとめることによって形式知に変わります。
ナレッジマネジメントの手法
ナレッジマネジメントには、次の4つの手法があります。
経営資本・戦略策定型
経営資本・戦略策定型は、知識をさまざまな角度から分析し、経営戦略へと反映する方法です。
分析には専用のシステムを用います。この手法では、自社の事例はもちろん、競合他社の事例からも分析可能です。業務プロセスから見直しを行うことで、新しい知識の取得や、既存知識のアップデートに役立ちます。
専門知識型
専門知識型は、社内外から得た知識を一つの場所にまとめてデータベース化する方法です。
ヘルプデスクのように問い合わせが多い部署では、知識をデータベース化することで対応スピードの向上が期待できます。
顧客知識共有型
顧客知識共有型は顧客対応のノウハウを蓄積する手法で、販売店やコールセンターなどで活用されています。これまでに発生したトラブルやクレームの内容などを基に、顧客の質問に対する模範解答を作成できます。すべての従業員に模範解答を共有することで、顧客対応の品質を均一にできるメリットがあります。
ベストプラクティス共有型
企業内で優秀な従業員の行動を形式知として扱うことで、企業全体をスキルアップする方法です。
たとえば、優秀な営業がどのようにアポイントを取得し、売上を出しているかを形式知にします。
優秀な従業員の考え方がすべての従業員に共有されるため、企業全体の生産性向上が期待できます。
SECIモデル
暗黙知を形式知に変えるためには、SECIモデルの活用が有効です。
SECIは「Socialization」「Externalization」「Combination」「Internalization」の頭文字を取った言葉です。SECIを構成する4つの要素について詳しく解説します。
Socialization:共同化
共同化とは、同じ経験を行うことで暗黙知を共有する方法です。個人から個人へと暗黙知を引き継ぐための一般的な方法です。
Externalization:表出化
表出化とは、言語化によって、暗黙知を形式知にする方法です。複数人で話し合うことで、暗黙知を文章化します。また、図解によって形式知にするケースもあります。表出化で大切なことは、具体例を出すなどして、誰にでも伝わる内容を示すことです。
Combination:連結化
連結化とは、形式知同士を組み合わせることで、新たな知識やノウハウを作ることです。形式知単体では個人でしか使用できません。そのため、組織でも使用できる知識にするために、形式知を組み合わせます。また、連結化の場合、システムと組み合わせるなども行いましょう。連結化によって、個人が持っていた暗黙知が組織の知識へと変わります。
Internalization:内面化
内面化は、連結化で示された知識が、個人の暗黙知へと変わるプロセスのことです。新しい知識は個人の中に入り、また新しい暗黙知を生み出します。そして、その暗黙知を形式知化し、また組織に還元していく作業の繰り返しがSECIモデルです。
ナレッジマネジメントの導入方法
ここからは、ナレッジマネジメントの導入方法を解説します。順序に沿って、試してみましょう。
従業員の役割を決める
知識やノウハウの創出にあたって、従業員の役割を決めましょう。リーダーを決め、その指示のもとで知識を蓄積していくとスムーズでしょう。
ナレッジマネジメントの目的を周知する
従業員に対して、ナレッジマネジメントの目的を周知しましょう。目的を共有すると、従業員もナレッジマネジメントの大切さを理解して協力してくれるでしょう。
経営方針に合わせて設計する
ナレッジマネジメントは、自社の経営方針に合わせて設計しましょう。
経営方針が変わった場合は、ナレッジマネジメントの設計を軌道修正する必要があります。
システムを用いてデータ運用を行う
ナレッジマネジメントで蓄積された知識は、システムを用いてデータ運用しましょう。
紙の資料で共有しただけでは資料を紛失したり汚れて確認できなくなったりする可能性があるため、データとして管理・運用することが大切です。
ナレッジマネジメント導入時の注意点
ナレッジマネジメントを導入する際には、次の点に注意しましょう。
知識やノウハウが共有できる環境を作る
ナレッジマネジメントを成功させるために、知識やノウハウを共有できる環境を作りましょう。
成果主義の企業の場合、「知識を共有することで自分が評価されにくくなってしまう」と考える従業員がいるかもしれません。従業員が知識を自分だけのものにしようとする状況を避けるためには、知識の共有も人事評価に含める制度が有効です。自身のノウハウ共有が評価される環境であれば、ナレッジマネジメントが推進されるでしょう。
知識を成長させ続ける
ナレッジマネジメントでは、獲得した知識を成長させ続けましょう。形式知と形式知を組み合わせて、また新しい技術を生み出すことが求められます。また、知識を成長させ続けるためには、新しい暗黙知が生まれることも大切です。従業員が新しい知識を獲得できる環境を整え、スキルアップをサポートしましょう。
シニア人材を活用する
暗黙知を持つシニア人材を活用しましょう。シニア人材は、これまでの経験からさまざまな暗黙知を持っています。シニア人材が持つ知識を、企業の発展に積極的に活かしていきましょう。
まとめ
個人が持っている知識を企業全体で共有するために、ナレッジマネジメントを導入しましょう。
知識をどのように共有するかを定め、知識を共有した従業員を評価する制度を整えることが大切です。長年の業務経験によるノウハウを持っているシニア人材を採用し、暗黙知を共有してもらうのも良いでしょう。ナレッジマネジメントを有効活用し、企業の発展に役立ててください。